第四 椎の木かげ(4-26~4-28) [第四 椎の木かげ]
4-26 おもふ事言はでたゞにや桐火桶

季語=桐火桶=火桶(ひおけ、ひをけ)/三冬
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2846
【子季語】桐火桶、火櫃
【解説】円火鉢のこと。桐の木などをくり抜いて内側を真鍮などの金属板を張ったもの。炭火を入れて暖を取る。彩色をほどこしてあったりもする。平安時代以降用いられたもので枕草子にある。
【例句】
細工絵を親に見せたる火桶かな 来山「太胡盧可佐」
霜の後撫子さける火桶哉 芭蕉「勧進牒」
草の屋の行灯もとぼす火桶かな 太祗「太祗句選」
桐火桶無絃の琴の撫でごころ 蕪村「雁風呂」
侘びしらに火桶張らうよ短冊で 蕪村「落日庵日記 」
【参考】藤原俊成(「桐火桶」)(「ウィキペディア」)
定家は為家をいさめて、「そのように衣服や夜具を取り巻き、火を明るく灯し、酒や食事・果物等を食い散らかしている様では良い歌は生まれない。亡父卿(俊成)が歌を作られた様子こそ誠に秀逸な歌も生まれて当然だと思われる。深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれていたという。誠に思慮深く打ち込まれる姿は伝え聞くだけでもその情緒に心が動かされ涙が出るのをおさえ難い」と言った。(心敬『ささめごと』)
句意(その周辺)=この句には、「俊成卿の畫(画)に」との前書があり、「藤原俊成(釈阿)が桐火桶を抱えている肖像画」を見ての一句なのであろう。
句意=俊成卿は、歌を作るときに、「「おもふ事」(心にあること)を、何一つ、「言はで」(言葉には出さず)、「たゞにや」(ただ、ひたすらに、「ウーン・ウーン」と苦吟しながら)、「桐火桶」(桐火鉢)を、抱え込んでいたんだと、そんなことを、この俊成卿の肖像画を見て、実感したわい。
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html
藤原俊成(菊池容斎・画、明治時代)(「ウィキペディア」)
4-27 松を時雨むかしうき世の毬目附
季語=時雨(初冬)
「毬目附(まりめつけ)」=「打毬(だきゅう)」競技(馬術競技)の「違法を監察する武士の職名(役名)」
「打毬」=打毬(だきゅう)は日本の競技・遊戯。馬に騎った者らが2組に分かれ、打毬杖(だきゅうづえ。毬杖)をふるって庭にある毬を自分の組の毬門に早く入れることを競う。
(中略)
江戸時代の方法は、毬門に紅白の験を立てて、毬門内に騎者10人、左右5騎ずつくつわを並べ、控える。騎者の後方左右に、勝負の合図に鉦鼓を打つ役人がいて、毬目付毬奉行門のかたわらでたがいに毬の出入りを検し、勝敗を分かつことを司る。(「ウィキペディア」)
句意(その周辺)=この句は、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書のある二句のうちの一句目の句である。この「河人」という人物は、抱一の俳句仲間というよりも、抱一の世話役のような「酒井家」の重臣のような方で、第八代将軍・徳川吉宗が奨励した馬術競技「打毬」の「目附」役なども担っていたのであろう。
句意=何かとお世話になっている「酒井家」の重臣「河人」の「初七日」に「橋場の保元寺(法源寺)」(参考二)に出掛けた。その寺の「松」に「時雨」が降りかかり、在りししの、馬術競技の「打毬」の「目附」役であった頃の、「河人の英姿」が蘇ってくる。
(参考一) 「打毬図」周辺
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html
「打毬図」(「和歌山市立博物館」蔵)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/281583
≪(解説) 打毬をする紀州藩士の様子を描いている。打毬とは、現在も宮内庁において保存・継承されている古式馬術で、紀元前5~6世紀に古代ペルシャで発祥し、中国を経て平安時代に我が国に伝えられた。和歌山出身の徳川吉宗が武芸として復興し、各藩に奨励したという。≫
(参考二)「保元寺」周辺
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html
江戸名所図会「法源寺・鏡が池」
https://blog.goo.ne.jp/sa194520131207/e/7f5a39c964d373b87b6dad87c965a211
4-28 仙人の碁盤に向ふ巨(炬)燵かな
季語=巨(炬)燵=「炬燵」(三冬)
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2841
【子季語】掘炬燵、置炬燵、敷炬燵、切炬燵、電気炬燵、炬燵櫓、炬燵蒲団、炬燵切る、炬燵張る、炬燵開く、炬燵板
【解説】日本に古くからある暖房器具。近頃は電気炬燵がほとんどだが、昔は、床を切って炉を設け櫓を据えて蒲団をかけ暖を取った。また櫓の中に火種をいれた中子を置いて、蒲団をかぶせたものを置炬燵と言った。
【例句】
住みつかぬ旅のこゝろや置火燵 芭蕉「勧進牒」
きりぎりすわすれ音になくこたつ哉 芭蕉「蕉翁全伝」
寝ごゝろや火燵蒲団のさめぬ内 其角「猿蓑」
つくづくとものゝはじまる炬燵哉 鬼貫「鬼貫句選」
草庵の火燵の下や古狸 丈草「丈草句集」
淀舟やこたつの下の水の音 太祇「太祇句帖」
巨燵出て早あしもとの野河哉 蕪村「蕪村俳句集」
腰ぬけの妻うつくしき巨燵かな 蕪村「蕪村俳句集」
句意(その周辺)=この句にも、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書が掛かる。
句意=「俗界」(「うき世」)を離れて、「仙人」(神通力を修めた「仙客」)と化した「打毬目附」そし「て「囲碁の仙客(達人)」の、その「先人(亡き人)」の「形見分け」の「碁盤」を「炬燵」の上に置いて、しみじみと、「在りし師」の「在りし日(日々)」を偲んでいる。

季語=桐火桶=火桶(ひおけ、ひをけ)/三冬
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2846
【子季語】桐火桶、火櫃
【解説】円火鉢のこと。桐の木などをくり抜いて内側を真鍮などの金属板を張ったもの。炭火を入れて暖を取る。彩色をほどこしてあったりもする。平安時代以降用いられたもので枕草子にある。
【例句】
細工絵を親に見せたる火桶かな 来山「太胡盧可佐」
霜の後撫子さける火桶哉 芭蕉「勧進牒」
草の屋の行灯もとぼす火桶かな 太祗「太祗句選」
桐火桶無絃の琴の撫でごころ 蕪村「雁風呂」
侘びしらに火桶張らうよ短冊で 蕪村「落日庵日記 」
【参考】藤原俊成(「桐火桶」)(「ウィキペディア」)
定家は為家をいさめて、「そのように衣服や夜具を取り巻き、火を明るく灯し、酒や食事・果物等を食い散らかしている様では良い歌は生まれない。亡父卿(俊成)が歌を作られた様子こそ誠に秀逸な歌も生まれて当然だと思われる。深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれていたという。誠に思慮深く打ち込まれる姿は伝え聞くだけでもその情緒に心が動かされ涙が出るのをおさえ難い」と言った。(心敬『ささめごと』)
句意(その周辺)=この句には、「俊成卿の畫(画)に」との前書があり、「藤原俊成(釈阿)が桐火桶を抱えている肖像画」を見ての一句なのであろう。
句意=俊成卿は、歌を作るときに、「「おもふ事」(心にあること)を、何一つ、「言はで」(言葉には出さず)、「たゞにや」(ただ、ひたすらに、「ウーン・ウーン」と苦吟しながら)、「桐火桶」(桐火鉢)を、抱え込んでいたんだと、そんなことを、この俊成卿の肖像画を見て、実感したわい。
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html
藤原俊成(菊池容斎・画、明治時代)(「ウィキペディア」)
4-27 松を時雨むかしうき世の毬目附
季語=時雨(初冬)
「毬目附(まりめつけ)」=「打毬(だきゅう)」競技(馬術競技)の「違法を監察する武士の職名(役名)」
「打毬」=打毬(だきゅう)は日本の競技・遊戯。馬に騎った者らが2組に分かれ、打毬杖(だきゅうづえ。毬杖)をふるって庭にある毬を自分の組の毬門に早く入れることを競う。
(中略)
江戸時代の方法は、毬門に紅白の験を立てて、毬門内に騎者10人、左右5騎ずつくつわを並べ、控える。騎者の後方左右に、勝負の合図に鉦鼓を打つ役人がいて、毬目付毬奉行門のかたわらでたがいに毬の出入りを検し、勝敗を分かつことを司る。(「ウィキペディア」)
句意(その周辺)=この句は、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書のある二句のうちの一句目の句である。この「河人」という人物は、抱一の俳句仲間というよりも、抱一の世話役のような「酒井家」の重臣のような方で、第八代将軍・徳川吉宗が奨励した馬術競技「打毬」の「目附」役なども担っていたのであろう。
句意=何かとお世話になっている「酒井家」の重臣「河人」の「初七日」に「橋場の保元寺(法源寺)」(参考二)に出掛けた。その寺の「松」に「時雨」が降りかかり、在りししの、馬術競技の「打毬」の「目附」役であった頃の、「河人の英姿」が蘇ってくる。
(参考一) 「打毬図」周辺
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html
「打毬図」(「和歌山市立博物館」蔵)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/281583
≪(解説) 打毬をする紀州藩士の様子を描いている。打毬とは、現在も宮内庁において保存・継承されている古式馬術で、紀元前5~6世紀に古代ペルシャで発祥し、中国を経て平安時代に我が国に伝えられた。和歌山出身の徳川吉宗が武芸として復興し、各藩に奨励したという。≫
(参考二)「保元寺」周辺
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html
江戸名所図会「法源寺・鏡が池」
https://blog.goo.ne.jp/sa194520131207/e/7f5a39c964d373b87b6dad87c965a211
4-28 仙人の碁盤に向ふ巨(炬)燵かな
季語=巨(炬)燵=「炬燵」(三冬)
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2841
【子季語】掘炬燵、置炬燵、敷炬燵、切炬燵、電気炬燵、炬燵櫓、炬燵蒲団、炬燵切る、炬燵張る、炬燵開く、炬燵板
【解説】日本に古くからある暖房器具。近頃は電気炬燵がほとんどだが、昔は、床を切って炉を設け櫓を据えて蒲団をかけ暖を取った。また櫓の中に火種をいれた中子を置いて、蒲団をかぶせたものを置炬燵と言った。
【例句】
住みつかぬ旅のこゝろや置火燵 芭蕉「勧進牒」
きりぎりすわすれ音になくこたつ哉 芭蕉「蕉翁全伝」
寝ごゝろや火燵蒲団のさめぬ内 其角「猿蓑」
つくづくとものゝはじまる炬燵哉 鬼貫「鬼貫句選」
草庵の火燵の下や古狸 丈草「丈草句集」
淀舟やこたつの下の水の音 太祇「太祇句帖」
巨燵出て早あしもとの野河哉 蕪村「蕪村俳句集」
腰ぬけの妻うつくしき巨燵かな 蕪村「蕪村俳句集」
句意(その周辺)=この句にも、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書が掛かる。
句意=「俗界」(「うき世」)を離れて、「仙人」(神通力を修めた「仙客」)と化した「打毬目附」そし「て「囲碁の仙客(達人)」の、その「先人(亡き人)」の「形見分け」の「碁盤」を「炬燵」の上に置いて、しみじみと、「在りし師」の「在りし日(日々)」を偲んでいる。
第四 椎の木かげ(4-21~4-25) [第四 椎の木かげ]
4-21 太刀懸に菊一とふりやけふの床
季語=菊=菊(きく)/三秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2597
【子季語】白菊、黄菊、一重菊、八重菊、大菊、中菊、小菊、菊作、厚物咲、初菊、乱菊、千代美草、懸崖菊、菊の宿、菊の友、籬の菊、菊時、菊畑
【解説】キク科の多年草。中国原産。奈良時代日本に渡って来た。江戸時代になって観賞用としての菊作りが盛んになる。香りよく見ても美しい。食用にもなる。秋を代表する花として四君子(梅竹蘭菊)の一つでもある。
【例句】
菊の香や奈良には古き仏達 芭蕉「杉風宛書簡」
菊の花咲くや石屋の石の間 芭蕉「翁草」
琴箱や古物店の背戸の菊 芭蕉「住吉物語」
白菊の目にたてゝ見る塵もなし 芭蕉「笈日記」
手燭して色失へる黄菊かな 蕪村「夜半叟句集」
黄菊白菊其の外の名はなくもなが 嵐雪「其袋」
「重陽」(前書の「重陽」)=重陽(ちょうよう、ちようやう)/晩秋
https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%87%8D%E9%99%BD&x=0&y=0
【子季語】重九、重陽の宴、菊の節句、九日の節句、菊の日、今日の菊、三九日、刈上の節供
【関連季語】温め酒、高きに登る、菊の着綿、茱萸の袋 、茱萸の酒、菊酒、九日小袖
【解説】旧暦の九月九日の節句。菊の節句ともいう。長寿を願って、菊の酒を飲み、高きに登るなどのならわしがある。
【実証的見解】古来、中国では奇数を陽数として好み、その最大の数「九」が重なる九月九日を、陽の重なる日、重陽とした。この日は、高いところにのぼり、長寿を願って菊の酒を飲んだ。これを「登高」という。また、茱萸の実を入れた袋を身につければ、茱萸の香気によって邪気がはらわれ、長寿をたまわるとも信じられていた。日本においては、宮中で観菊の宴がもよおされ、群臣は菊の酒を賜った。また、菊に一晩綿をかぶせ、その夜露と香りをつけたもので身を拭う、菊の着綿という風習もあった。この日に酒を温めて飲む「温め酒」の風習は無病息災を願ったものである。
【例句】
朝露や菊の節句は町中も 太祇「太祇句選」
人心しづかに菊の節句かな 召波「春泥発句集」
【参考】健康を願う「菊の節句」周辺
https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/topics/vol370/
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
雅遊五節句之内 菊月』 国芳 天保10(1839)年頃
≪九月九日は「菊の節句」です。昔の中国では九のような奇数を陽数、八のような偶数を陰数と分類していました。この考え方からすると「九」は一桁の奇数の中で最も大きく、特に九月九日のように陽数が重なることから「重陽」と呼ばれました。また、旧暦の九月は今の十月にあたり、優れた薬効があり不老長寿の花とされる「菊」の時期であることから「菊月」とも呼ばれていました。江戸時代になると、幕府は一月一日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日の季節の節目を「五節句」として制定しましたが、中でも九月九日は「重陽の節句」または「菊の節句」と呼ばれ、盛大に行われていたようです。また、江戸中期になるとこの日を大人の女性の「後(のち)の雛」として雛人形と秋の菊の花を飾り、厄除けや健康祈願をする「大人の雛祭り」の風習も庶民の間で広がりをみせたといいます。
さて、今回の浮世絵は武者絵を得意とする歌川国芳の描いた「雅遊五節句之内 菊月」です。国芳は二人の男の子に相撲を取らせて「菊の節句」を表現しました。しかし筋骨隆々の武者絵と違い、二人の男の子はあどけなく、まわし(ふうどし)に巾着を付けて一戦を交えています。腰の巾着はおそらくお守りや迷子札入れとして母親が手作りしたものでしょう。まわし姿になっても巾着をつけて勝負している様子がなんとも可愛らしいですね。周りでは菊文様の着物の子どもが声援しています。周囲には長寿のシンボルである大輪の菊が多数描かれていて、子どもの健康、長寿の願いを込めたことがわかります。≫
句意(その周辺)=今日は、陰暦の九月九日の「重陽」、「菊の節句」である。「床の間」の、その「太刀掛け」には、今日は「菊一輪(いちりん)」が懸けられている。(蛇足=この「菊一輪」は、酒井抱一が「大名・酒井家」の一員であることを示す、名刀「菊一文字」が「一(ひと)ふり)懸けられている。」
4-21 見劣し人のこゝろや作りきく
季語=作りきく=菊(きく)/三秋
「作りきく」=菊作り=1 菊を栽培すること。また、その人。《季 秋》/2 フグなどの刺身を、皿の上に菊の花のように盛りつけたもの。/3 「菊作りの太刀」の略。(「デジタル大辞泉」)
句意(その周辺)=今日は「重陽」の節句、菊見に出かけた。いろいろな「作り菊」を見て回ったが、「見事なもの」と「見劣るものと」、その区分けは、その「菊」を作る「人のこころ」によるものということを実感した。(蛇足=「料理」の「菊つくり」でも、「太刀」の「菊一文字」と「菊一文字もどき」との違いでも、全く、同じことなのだ。)
4-23 冬の野や何を尾花が袖みやげ
季語=冬の野(三冬)。「尾花」(三秋)も季語だが、この句では「冬野(枯野)の尾花」。
「袖みやげ」=この「袖みやげ(土産)」が難解である。この「袖」は「誰が袖」(匂袋)の「誰が」が「ヌケ」になっているものと解したい。
《古今集・春上の「色よりも香こそあはれと思ほゆれ誰が袖ふれし宿の梅ぞも」の歌から》
1 匂袋(においぶくろ)の名。衣服の袖の形に作った袋を二つひもで結び、たもと落としのようにして携帯した。
2 細長い楊枝ようじさし。
3 桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。
4 衣服の片袖の形や文様を意匠に取り入れた器物。香合(こうごう)・向付(むこうづけ)・茶碗・水指(みずさし)などがある。(「デジタル大辞泉」)
句意(その周辺)=このお土産の「誰が袖(匂袋)」の図柄は、「冬の野の尾花」のようである。「重陽」の節句に、「黄菊白菊其の外の名はなくもなが(嵐雪)」の「菊」の図柄であれば、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)に申し分なかったのに。(蛇足=これでは「見劣り」するわい。)
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
「誰が袖(匂袋)」
4-24 見し夢や時雨の松の畫から紙
季語=時雨(初冬)
「畫から紙」=「桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。」=「誰が袖(屏風)」
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
「誰が袖図屛風」(サントリー美術館蔵)( 六曲一双/)屛風 紙本著色/(各)縦172.0 横384.0/江戸時代 17世紀)
https://www.suntory.co.jp/sma/collection/gallery/detail?id=555
≪ 誰が袖屏風とは、衣桁などに多くの衣装を掛けた様子を描いた作品群のことで、江戸時代初期に流行したと考えられている。基本的に人物は登場せず、衣装や匂い袋、遊戯具など、室内に置かれた持ち物によって、その持ち主の面影を偲ぶという趣向になっている。「誰か袖」とは「これは誰の衣装なのか」という意味で、『古今和歌集』に収められた「色よりも 香こそあはれと思ほゆれ 誰が袖ふれし 宿の梅ぞも」に由来する。なかでも本作はバランスの良い構図と、豪華な描写が高く評価されている。右隻は、菊蒔絵の衣桁の上段に、霞に藤花模様の能装束らしき衣装と匂い袋が配されている。下段には菖蒲模様の袴が見える。右端に置かれているのは能面を入れる面箱と思われ、この部屋の主人公は能を好む人物であるらしい。左隻は、藤蒔絵の衣桁や屏風に、段に胡蝶文、転法輪文、文字散らし文、丸紋散らし文など、多様なデザインの衣装が掛かっている。右手には双六盤があり、盤上や床に石、サイコロ、振り筒が無造作に置かれている。画中屏風には本格的な水墨山水図が描かれており、その筆致が海北派に近いとの指摘がある。本作の作者は不明だが、著色画・水墨画の両方に長けた絵師であったことは間違いない。(『リニューアル・オープン記念展Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY』、サントリー美術館、2020年) ≫
句意=昨日「見し夢」の中で、嘗て、大手門前の「酒井家上屋敷」での一句、「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)が、「重陽の節句の菊に降りかかる時雨の松」となって、当時の面影が、「誰が袖図屏風(「畫から紙」)」として蘇ってきた。それは、同時に、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の名吟、「名月や畳の上に松の影」(『雑談集(其角著)』)を偲ばせるものであった。
(参考一)『雑談集』(其角著)周辺
http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/zoutan.html
(参考二)「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)周辺
https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-6.html
4-25 来ぬ夜鳴く衛や虎が裾模様
季語=「衛」=千鳥(ちどり)/三冬
https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%83%E9%B3%A5&x=0&y=0
【子季語】目大千鳥、大膳、胸黒、小千鳥、白千鳥、鵤千鳥、千鳥足、千鳥掛、磯千鳥、浜千鳥、浦千鳥、島千鳥、川千鳥、群千鳥、友千鳥、遠千鳥、夕千鳥、小夜千鳥、夕波千鳥、月夜千鳥、鵆
【解説】チドリ科の鳥の総称で留鳥と渡り鳥がある。嘴は短く、色は灰褐色。足を交差させて歩むのが千鳥足。酔っ払いの歩行にたとえられる。
【例句】
星崎の闇を見よとや啼千鳥 芭蕉「笈の小文」
一疋のはね馬もなし川千鳥 芭蕉「もとの水」
千鳥立更行初夜の日枝おろし 芭蕉「伊賀産湯」
汐汲や千鳥残して帰る海人 鬼貫「七車」
背戸口の入江にのぼる千鳥かな 丈草「猿蓑」
【参考】「虎が雨」=「虎が雨(とらがあめ)/ 仲夏」(陰暦の五月二十八日に降る雨のこと。曾我兄弟の兄、十郎が新田忠常に切り殺されことを、愛人の虎御前が悲しみ、その涙が雨になったという言伝えに由来する。)の季語だが、この句では、「虎が裾模様」で、季語としての働きはしていない。さらに、この「袖(すそ)模様」は、「前々句」(4-23)からの「誰が袖」の「袖(そで)模様」の変奏なのである。
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
「白繻子地紅梅文様描絵小袖 酒井抱一画」(「国立歴史民俗博物館」蔵)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/136247
≪酒井抱一(ほういつ)(1761~1828)の筆による描絵小袖である。文様は独特な濃淡で紅梅を描き、梅樹の根元には蒲公英(たんぽぽ)や菫(すみれ)など春の情景が表される。「抱一」の朱印がある。本小袖は、紅梅を全面に見事に描いた小袖意匠としても秀逸であり、絵師が直接小袖に図様を描く描絵小袖の数少ない遺例の一つである。≫
句意(その周辺)=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の『句兄弟』に収載されている「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(もと)」(参考)の「本句取り」の一句なのである。
句意=「重陽」の「菊」(「誰が袖」の菊模様の「匂袋」)の句から、「時雨」(「誰が袖図屏風」の「畫から紙」)の句となり、そして、「今」、それらが、「袖」でなく「裾」の、その「虎が雨」の、その「白繻子地紅梅(「虎が雨」の見立て)文様描絵小袖(その「袖」と「裾」絵)の、「虎が雨(「梅」して、「菊」・「千鳥」)」と化している。
(参考)「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(其角)」周辺
https://yahantei.blogspot.com/2007/05/blog-post_23.html
(句合せ四)
※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html
※(謎解き・五十五)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html
四番
兄 粛山
祐成が袖引(き)のばせむら千鳥
弟 (其角)
むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許
(兄句の句意)群千鳥が鳴いている。群千鳥よ、どうか、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けていこうとしているが、その袖を強く引いて引き留めて欲しい。
(弟句の句意)群千鳥が鳴いている。曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けて行った日も、虎御前とともにあって、その夜は厳しい寒さであったことだろう。
(判詞の要点)両句とも、曽我十郎祐成と祐成と契った遊女の虎御前のことについて詠んだものである。「是は各句合意の躰也。兄の句に寒しといふ字のふくみて聞え侍れば、こなたの句、弟なるべし」。判詞中の「冬の夜の川風寒みのうたにて追反せし也」は、紀貫之の「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒みちどり鳴くなり」(『拾遺集』)を踏まえている。
(参考)「粛山(しゅくざん)」については、この其角の『句兄弟』の、「上巻が三十九番の発句合(わせ)、判詞、其角。中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める。下巻は元禄七年秋から冬にかけて東海道・畿内の旅をした其角・岩翁・亀翁らの紀行句、諸家発句を健・新・清など六格に分類したものを収める」(『俳文学大辞典』)の、「中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める」の「粛山」であろう。『句兄弟(上)』の其角の判詞には、「さすか(が)に高名の士なりけれハ(ば)」とあり、この粛山とは、松平隠岐守の重臣・久松粛山のことであろう。
季語=菊=菊(きく)/三秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2597
【子季語】白菊、黄菊、一重菊、八重菊、大菊、中菊、小菊、菊作、厚物咲、初菊、乱菊、千代美草、懸崖菊、菊の宿、菊の友、籬の菊、菊時、菊畑
【解説】キク科の多年草。中国原産。奈良時代日本に渡って来た。江戸時代になって観賞用としての菊作りが盛んになる。香りよく見ても美しい。食用にもなる。秋を代表する花として四君子(梅竹蘭菊)の一つでもある。
【例句】
菊の香や奈良には古き仏達 芭蕉「杉風宛書簡」
菊の花咲くや石屋の石の間 芭蕉「翁草」
琴箱や古物店の背戸の菊 芭蕉「住吉物語」
白菊の目にたてゝ見る塵もなし 芭蕉「笈日記」
手燭して色失へる黄菊かな 蕪村「夜半叟句集」
黄菊白菊其の外の名はなくもなが 嵐雪「其袋」
「重陽」(前書の「重陽」)=重陽(ちょうよう、ちようやう)/晩秋
https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%87%8D%E9%99%BD&x=0&y=0
【子季語】重九、重陽の宴、菊の節句、九日の節句、菊の日、今日の菊、三九日、刈上の節供
【関連季語】温め酒、高きに登る、菊の着綿、茱萸の袋 、茱萸の酒、菊酒、九日小袖
【解説】旧暦の九月九日の節句。菊の節句ともいう。長寿を願って、菊の酒を飲み、高きに登るなどのならわしがある。
【実証的見解】古来、中国では奇数を陽数として好み、その最大の数「九」が重なる九月九日を、陽の重なる日、重陽とした。この日は、高いところにのぼり、長寿を願って菊の酒を飲んだ。これを「登高」という。また、茱萸の実を入れた袋を身につければ、茱萸の香気によって邪気がはらわれ、長寿をたまわるとも信じられていた。日本においては、宮中で観菊の宴がもよおされ、群臣は菊の酒を賜った。また、菊に一晩綿をかぶせ、その夜露と香りをつけたもので身を拭う、菊の着綿という風習もあった。この日に酒を温めて飲む「温め酒」の風習は無病息災を願ったものである。
【例句】
朝露や菊の節句は町中も 太祇「太祇句選」
人心しづかに菊の節句かな 召波「春泥発句集」
【参考】健康を願う「菊の節句」周辺
https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/topics/vol370/
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
雅遊五節句之内 菊月』 国芳 天保10(1839)年頃
≪九月九日は「菊の節句」です。昔の中国では九のような奇数を陽数、八のような偶数を陰数と分類していました。この考え方からすると「九」は一桁の奇数の中で最も大きく、特に九月九日のように陽数が重なることから「重陽」と呼ばれました。また、旧暦の九月は今の十月にあたり、優れた薬効があり不老長寿の花とされる「菊」の時期であることから「菊月」とも呼ばれていました。江戸時代になると、幕府は一月一日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日の季節の節目を「五節句」として制定しましたが、中でも九月九日は「重陽の節句」または「菊の節句」と呼ばれ、盛大に行われていたようです。また、江戸中期になるとこの日を大人の女性の「後(のち)の雛」として雛人形と秋の菊の花を飾り、厄除けや健康祈願をする「大人の雛祭り」の風習も庶民の間で広がりをみせたといいます。
さて、今回の浮世絵は武者絵を得意とする歌川国芳の描いた「雅遊五節句之内 菊月」です。国芳は二人の男の子に相撲を取らせて「菊の節句」を表現しました。しかし筋骨隆々の武者絵と違い、二人の男の子はあどけなく、まわし(ふうどし)に巾着を付けて一戦を交えています。腰の巾着はおそらくお守りや迷子札入れとして母親が手作りしたものでしょう。まわし姿になっても巾着をつけて勝負している様子がなんとも可愛らしいですね。周りでは菊文様の着物の子どもが声援しています。周囲には長寿のシンボルである大輪の菊が多数描かれていて、子どもの健康、長寿の願いを込めたことがわかります。≫
句意(その周辺)=今日は、陰暦の九月九日の「重陽」、「菊の節句」である。「床の間」の、その「太刀掛け」には、今日は「菊一輪(いちりん)」が懸けられている。(蛇足=この「菊一輪」は、酒井抱一が「大名・酒井家」の一員であることを示す、名刀「菊一文字」が「一(ひと)ふり)懸けられている。」
4-21 見劣し人のこゝろや作りきく
季語=作りきく=菊(きく)/三秋
「作りきく」=菊作り=1 菊を栽培すること。また、その人。《季 秋》/2 フグなどの刺身を、皿の上に菊の花のように盛りつけたもの。/3 「菊作りの太刀」の略。(「デジタル大辞泉」)
句意(その周辺)=今日は「重陽」の節句、菊見に出かけた。いろいろな「作り菊」を見て回ったが、「見事なもの」と「見劣るものと」、その区分けは、その「菊」を作る「人のこころ」によるものということを実感した。(蛇足=「料理」の「菊つくり」でも、「太刀」の「菊一文字」と「菊一文字もどき」との違いでも、全く、同じことなのだ。)
4-23 冬の野や何を尾花が袖みやげ
季語=冬の野(三冬)。「尾花」(三秋)も季語だが、この句では「冬野(枯野)の尾花」。
「袖みやげ」=この「袖みやげ(土産)」が難解である。この「袖」は「誰が袖」(匂袋)の「誰が」が「ヌケ」になっているものと解したい。
《古今集・春上の「色よりも香こそあはれと思ほゆれ誰が袖ふれし宿の梅ぞも」の歌から》
1 匂袋(においぶくろ)の名。衣服の袖の形に作った袋を二つひもで結び、たもと落としのようにして携帯した。
2 細長い楊枝ようじさし。
3 桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。
4 衣服の片袖の形や文様を意匠に取り入れた器物。香合(こうごう)・向付(むこうづけ)・茶碗・水指(みずさし)などがある。(「デジタル大辞泉」)
句意(その周辺)=このお土産の「誰が袖(匂袋)」の図柄は、「冬の野の尾花」のようである。「重陽」の節句に、「黄菊白菊其の外の名はなくもなが(嵐雪)」の「菊」の図柄であれば、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)に申し分なかったのに。(蛇足=これでは「見劣り」するわい。)
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
「誰が袖(匂袋)」
4-24 見し夢や時雨の松の畫から紙
季語=時雨(初冬)
「畫から紙」=「桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。」=「誰が袖(屏風)」
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
「誰が袖図屛風」(サントリー美術館蔵)( 六曲一双/)屛風 紙本著色/(各)縦172.0 横384.0/江戸時代 17世紀)
https://www.suntory.co.jp/sma/collection/gallery/detail?id=555
≪ 誰が袖屏風とは、衣桁などに多くの衣装を掛けた様子を描いた作品群のことで、江戸時代初期に流行したと考えられている。基本的に人物は登場せず、衣装や匂い袋、遊戯具など、室内に置かれた持ち物によって、その持ち主の面影を偲ぶという趣向になっている。「誰か袖」とは「これは誰の衣装なのか」という意味で、『古今和歌集』に収められた「色よりも 香こそあはれと思ほゆれ 誰が袖ふれし 宿の梅ぞも」に由来する。なかでも本作はバランスの良い構図と、豪華な描写が高く評価されている。右隻は、菊蒔絵の衣桁の上段に、霞に藤花模様の能装束らしき衣装と匂い袋が配されている。下段には菖蒲模様の袴が見える。右端に置かれているのは能面を入れる面箱と思われ、この部屋の主人公は能を好む人物であるらしい。左隻は、藤蒔絵の衣桁や屏風に、段に胡蝶文、転法輪文、文字散らし文、丸紋散らし文など、多様なデザインの衣装が掛かっている。右手には双六盤があり、盤上や床に石、サイコロ、振り筒が無造作に置かれている。画中屏風には本格的な水墨山水図が描かれており、その筆致が海北派に近いとの指摘がある。本作の作者は不明だが、著色画・水墨画の両方に長けた絵師であったことは間違いない。(『リニューアル・オープン記念展Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY』、サントリー美術館、2020年) ≫
句意=昨日「見し夢」の中で、嘗て、大手門前の「酒井家上屋敷」での一句、「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)が、「重陽の節句の菊に降りかかる時雨の松」となって、当時の面影が、「誰が袖図屏風(「畫から紙」)」として蘇ってきた。それは、同時に、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の名吟、「名月や畳の上に松の影」(『雑談集(其角著)』)を偲ばせるものであった。
(参考一)『雑談集』(其角著)周辺
http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/zoutan.html
(参考二)「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)周辺
https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-6.html
4-25 来ぬ夜鳴く衛や虎が裾模様
季語=「衛」=千鳥(ちどり)/三冬
https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%83%E9%B3%A5&x=0&y=0
【子季語】目大千鳥、大膳、胸黒、小千鳥、白千鳥、鵤千鳥、千鳥足、千鳥掛、磯千鳥、浜千鳥、浦千鳥、島千鳥、川千鳥、群千鳥、友千鳥、遠千鳥、夕千鳥、小夜千鳥、夕波千鳥、月夜千鳥、鵆
【解説】チドリ科の鳥の総称で留鳥と渡り鳥がある。嘴は短く、色は灰褐色。足を交差させて歩むのが千鳥足。酔っ払いの歩行にたとえられる。
【例句】
星崎の闇を見よとや啼千鳥 芭蕉「笈の小文」
一疋のはね馬もなし川千鳥 芭蕉「もとの水」
千鳥立更行初夜の日枝おろし 芭蕉「伊賀産湯」
汐汲や千鳥残して帰る海人 鬼貫「七車」
背戸口の入江にのぼる千鳥かな 丈草「猿蓑」
【参考】「虎が雨」=「虎が雨(とらがあめ)/ 仲夏」(陰暦の五月二十八日に降る雨のこと。曾我兄弟の兄、十郎が新田忠常に切り殺されことを、愛人の虎御前が悲しみ、その涙が雨になったという言伝えに由来する。)の季語だが、この句では、「虎が裾模様」で、季語としての働きはしていない。さらに、この「袖(すそ)模様」は、「前々句」(4-23)からの「誰が袖」の「袖(そで)模様」の変奏なのである。
(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html
「白繻子地紅梅文様描絵小袖 酒井抱一画」(「国立歴史民俗博物館」蔵)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/136247
≪酒井抱一(ほういつ)(1761~1828)の筆による描絵小袖である。文様は独特な濃淡で紅梅を描き、梅樹の根元には蒲公英(たんぽぽ)や菫(すみれ)など春の情景が表される。「抱一」の朱印がある。本小袖は、紅梅を全面に見事に描いた小袖意匠としても秀逸であり、絵師が直接小袖に図様を描く描絵小袖の数少ない遺例の一つである。≫
句意(その周辺)=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の『句兄弟』に収載されている「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(もと)」(参考)の「本句取り」の一句なのである。
句意=「重陽」の「菊」(「誰が袖」の菊模様の「匂袋」)の句から、「時雨」(「誰が袖図屏風」の「畫から紙」)の句となり、そして、「今」、それらが、「袖」でなく「裾」の、その「虎が雨」の、その「白繻子地紅梅(「虎が雨」の見立て)文様描絵小袖(その「袖」と「裾」絵)の、「虎が雨(「梅」して、「菊」・「千鳥」)」と化している。
(参考)「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(其角)」周辺
https://yahantei.blogspot.com/2007/05/blog-post_23.html
(句合せ四)
※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html
※(謎解き・五十五)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html
四番
兄 粛山
祐成が袖引(き)のばせむら千鳥
弟 (其角)
むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許
(兄句の句意)群千鳥が鳴いている。群千鳥よ、どうか、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けていこうとしているが、その袖を強く引いて引き留めて欲しい。
(弟句の句意)群千鳥が鳴いている。曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けて行った日も、虎御前とともにあって、その夜は厳しい寒さであったことだろう。
(判詞の要点)両句とも、曽我十郎祐成と祐成と契った遊女の虎御前のことについて詠んだものである。「是は各句合意の躰也。兄の句に寒しといふ字のふくみて聞え侍れば、こなたの句、弟なるべし」。判詞中の「冬の夜の川風寒みのうたにて追反せし也」は、紀貫之の「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒みちどり鳴くなり」(『拾遺集』)を踏まえている。
(参考)「粛山(しゅくざん)」については、この其角の『句兄弟』の、「上巻が三十九番の発句合(わせ)、判詞、其角。中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める。下巻は元禄七年秋から冬にかけて東海道・畿内の旅をした其角・岩翁・亀翁らの紀行句、諸家発句を健・新・清など六格に分類したものを収める」(『俳文学大辞典』)の、「中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める」の「粛山」であろう。『句兄弟(上)』の其角の判詞には、「さすか(が)に高名の士なりけれハ(ば)」とあり、この粛山とは、松平隠岐守の重臣・久松粛山のことであろう。
第四 椎の木かげ(4-12~4-20) [第四 椎の木かげ]
4-12 仙薬を魚もなめてや雲の峰
季語=「雲の峰」=雲の峰(くものみね)三夏
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2036
【子季語】 積乱雲、入道雲、峰雲
【解説】 盛夏、聳え立つ山並みのようにわき立つ雲。積乱雲。夏といえば入道雲であり、夏の代名詞である。強い日差しを受けて発生する激しい上昇気流により、巨大な積雲に成長して行く。地方により坂東太郎・丹波太郎・信濃太郎・石見太郎・安達太郎・比古太郎などとよばれる。
【例句】
雲の峰幾つ崩れて月の山 芭蕉「奥の細道」
ひらひらとあぐる扇や雲の峰 芭蕉「笈日記」
湖やあつさををしむ雲のみね 芭蕉「笈日記」
雲の峰きのふに似たるけふもあり 白雄「白雄句集」
しづかさや湖水の底の雲のみね 一茶「寛政句帖」
仙薬=① 飲むと仙人になるという薬。不老不死の薬。仙丹。
※霊異記(810‐824)上「『逕ること八日、夜、銛き鋒に逢はむ。願はくは仙薬を服せ』といひて」 〔史記‐始皇本紀〕
② 非常によくきく不思議な薬。霊薬。
※今昔(1120頃か)五「国王、此は仙薬を服せるに依て也と知て」
(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=この句には「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」との前書がある。この前書からすると、一茶の「しづかさや湖水の底の雲のみね」に近い、「緑樹の影と入道雲のが水底に沈んで、その入道雲を、魚が、あたかも、仙薬(不老不死の薬)のように舐めている」というような句意となる。
(参考)『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』で紹介されている句意周辺
この句は、『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』(p77~p78)で、其角の「香薷散(かうじゆさん)犬がねぶつて雲の峯」(『五元集』)の句を変奏しているとの謎解きをしている。
それによると、この前書は、謡曲(「竹生島(ちくぶじま)」)の「緑樹影沈(しづ)みて、魚木に上る気配あり」を摘まんだものと指摘している。そして、其角の句は、「夏雲が水たまりに影を落とす。犬が水たまりの茶色い水をなめるので、さながら犬が雲のなかにいるかのようである」として、その「茶色い水(液体)」は、「暑気払い」の「茶色い・香薷散」の見立てと喝破している。
この其角の「香薷散」の句は、下記のアドレスで紹介している。
ttps://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false
【〇 香薷(じゆ)散犬がねぶつて雲の峰 (其角『五元集』)
〇 まとふどな犬ふみつけて猫の恋 (芭蕉『菊の道』)
四十一 掲出の一句目の其角の句は、「雲の峰が立つ真夏の余りの暑さに、犬までが暑気払いの『香薷(じゆ)散』を舐(なぶ)っている」という意であろう。この句の背後には、『事文類聚』(「列仙全伝」)の故事(准南王が仙とし去った後、仙薬が鼎中に残っていたのを鶏と犬とが舐めて昇天し、雲中に鳴いたとある)を踏まえているという。さらに、この句の真意は、「将軍綱吉の生類憐れみの令による犬保護の世相を背景とし、犬の増長ぶりを諷している」という(今泉・前掲書)。と解すると、これまた、其角の時の幕政への痛烈な風刺の句ということになる。それに比して、其角の師匠の芭蕉の二句目の犬の句は、「恋に切なく身を焦がす猫が、おっとり寝そべっている犬を踏みつけてうろつきまわっている」と、主題は「猫の恋」で実にのんびりとした穏やかな光景である。この「まとふど」は、「全人(またいびと)」の「純朴で正直な人」から転じての「とんま・偶直な」という意とのことである(井本農一他注解『松尾芭蕉集』)。いずれにしろ、ここには、其角のような、時の幕政への痛烈な風刺の句というニュアンスは感知されない。芭蕉もまた、反権力・反権威ということにおいては、人後に落ちない「隠棲の大宗匠」という雰囲気だが、どちらかというと、「おくのほそ道」に関わる「芭蕉隠密説」も流布されるように、「親幕府」という趣だが、こと、その蕉門第一の高弟・其角は、「反幕府」という趣なのが、何とも好対照なのである。ちなみに、芭蕉もまた、其角と同様に、綱吉の「生類憐れみの令」の御時世の元禄の俳人であったことは、付言する必要もなかろう。】
ここまで来ると、其角の句も、抱一の句も、それこそ、正岡子規の、「抱一の画、濃艶愛すべしといえども、俳句に至っては拙劣見るに堪えず」と、「チンプンカンプン」ということで、敬遠されることになる。
しかし、抱一の、その句の周辺を探るには、その作意の本筋の「其角」の句は手に負えないとしても、より、定石的な、より、理解し易い、例えば、上記の、「季語」の解説の「例句」などを補助線にすると、何かが見えてくるような、そして、そういう、「抱一の発句、濃艶愛すべし」という見方もあるように思える。
4-13 秋旣(すでニ)ちかづきふへて蛍がり
季語=「秋」と「蛍」=「秋の蛍」=秋の蛍(あきのほたる) 初秋
https://kigosai.sub.jp/?s=%E7%A7%8B%E3%81%AE%E8%9B%8D&x=0&y=0
【子季語】 秋蛍/残る蛍/病蛍
【解説】 秋風が吹く頃の蛍である。弱々しく放つ光や季節を外れた侘しさが本意。
【例句】
世の秋の蛍はその日おくりかな 信徳「口真似草」
死ぬるとも居るとも秋を飛ぶ蛍 乙州「西の雲」
牛の尾にうたるる秋のほたるかな 成美「成美家集」
蛍減る秋を浅香の橋作り 乙二「をののえ草稿」
「ほたるがり」=夏の夜、水辺などに光る蛍を捕えて遊ぶこと。ほたるおい。《季・夏》
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
※浮世草子・好色産毛(1695頃)三「上鴨の蛍狩(ホタルガリ)、宇治瀬田は更也、北野平野に勝て、市原二の瀬の柴口鼻(しばかか)が帰る夜道をかがやかし」 (「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=この句も難解句の一つである。まず、前句(4-12)の前書(「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」)が掛かる一群(「4-12」~「4-20」)の句の、二番目の句と解したい。その上で、この句の「秋旣(既の「異字体」)ちかづきふへて蛍がり」の詠みは、「秋既(すで)ニ/ちかづき・ふへて/蛍がり」(五・七・五)の詠みとして置きたい。
句意=緑樹の影も沈んで、既に、夏から秋へとの気配を漂わせている。その忍び寄る初秋の夜に蛍の数は増えて、その最後の蛍狩りに興じている。
(参考) 其角の蛍の句(「此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉(『五元集』)」)周辺
https://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false
【(謎解き・二十一)
〇 鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分 (其角『五元集』)
〇 夕顔にあはれをかけよ売名号 (其角『五元集』)
〇 此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉 (其角『五元集』)
四十 この掲出の三句は、『五元集』では、一句目が「春」、二句・三句目が「夏」と分かれて掲載されているが、その『五元集』のもとになっている『焦尾琴』の「早船の記」では、次のように掲載されているうちの三句である。
http://kikaku.boo.jp/haibun.html
其引 所の産を寄て
※行水や何にとゝまる海苔の味 其角
朝皃の下紐ひちて蜆とり 午寂
雨雲や簀に干海苔の片明り 文士
幕洗ふ川辺の比や郭公 序令
椎の木に衣たゝむや村時雨 同
浮島の親仁組也余情川 景口(けいれん)
すまふ取ゆかしき顔や松浦潟 同
建坪の願ひにみせつ小萩はら 白獅
※幸清か霧のまかきや昔松 其角
※鯉に義は山吹の瀬やしらぬ分 同
さなきたに鯉も浮出て十三夜 秋航
雷の撥のうはさや花八手 百里
夕月や女中に薄き川屋敷 同
村雨や川をへたてゝつくつくし 甫盛
後からくらう成けり土筆 堤亭
揚麩には祐天もなし昏の鴫 朝叟
※夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号 其角
河上に音楽あり
笙の肱是も帆に張夏木立 午寂
お手かけの菫屋敷は栄螺哉 同
こまかたに舟をよせて
※此碑ては江を哀(カナシ)まぬ蛍哉 其角
若手共もぬけの舟や更る月 楓子
さて、この掲出の一句目の、「鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分」は、「綾瀬の御留川(漁獲禁止の川)の名物の山吹鯉を獲るのに、見張りの役人に少々山吹色の小判を与えれば、見て見ぬふりをしてくれる」という世相風刺(当時の幕政の腐敗の風刺)の句のようなのである(今泉・前掲書)。
二句目の「夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号」は、『五元集』では、「裕天和尚に申す」との前書きがあり、この裕天和尚は、当時の五代将軍綱吉の母桂昌院の尊信を受け、隅田川東岸の牛島を去って、一躍高位の僧となられた方で、その「裕天和尚に申す」という形での、「売名号」(仏あるいは菩薩の名号を書いた札で、書き手によって御利益がある)の御利益のように、民衆に「哀れをかけよ」としての、これまた、当時の幕政への不満に基づく風刺の句のようなのである。
この「夕顔」は、『源氏物語』の「夕顔」の「山がつが垣穂荒るともをりをりはあはれをかけよ撫子のつゆ」を踏まえているとのことである(今泉・前掲書)。そして、三句目の「此碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉」は、「この殺生禁断の碑のお蔭で何となく不景気で、川の流れを眺めながら哀れに感じないのは蛍だけ」という意の、当時の五代将軍綱吉の「生類憐れみの令」への嘆きの句であるという(半藤・前掲書)。其角の謎句には、このような当時の幕政への痛烈な風刺の句があり、その意味では、其角は、終始一貫して、反権力・反権威の反骨の俳人という姿勢を貫いている。
こういう句の背後にあるものを、当時の人でも察知できる者と、察知できない者と、完全に二分されていたのであろう。そして、その背後にあるものを察知できない者は、其角の句を「奇想・奇抜・意味不明」の世界のものとして排斥していったということは、容易に想像のできるところのものである。】
4-14 きぬぎぬの橋に成(なり)たかあの鴉
季語=「きぬぎぬの橋」=「後朝の橋」=「鵲の橋(かささぎのはし)」 初秋
https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%B5%B2%E3%81%AE%E6%A9%8B&x=0&y=0
【子季語】 星の橋/行合の橋/寄羽の橋/天の小夜橋/紅葉の橋/烏鵲の橋
【解説】 七夕の夜、天の川を渡る織姫のため、かささぎが羽を連ねて橋となること。
【例句】
かささぎやけふ久かたのあまの川 守武「飛梅千句」
鵲の橋や銀河のよこ曇り 来山「続今宮草」
かささぎや石を重りの橋も有り 其角「浮世の北」
【参考】 鵲=鵲(かささぎ)三秋=七夕伝説に登場する鳥。天の川を渡る織姫のために羽を連ねて橋を作るという。カラスに似ているが腹部が白いのでカラスと見分けられる。
「鴉・烏」だけでは、季語の働きはしない。「春= 鴉の巣/夏= 鴉の子/冬= 寒烏/新年 =初烏」。
この抱一の句では、「きぬぎぬの橋」(「鵲の橋」)と「鴉」との取り合わせで、「初秋」の句ということになろう。そして、この句は、「吉原」の「きぬぎぬの別れ」の「あの鴉(男)」=「吉原帰りの男」の見立てということになる。
句意(その周辺)=緑樹の影も沈んで、七夕の季節、あの吉原帰りの「鴉(からす)野郎」は、昨夜は、「鵲の橋」を渡って、「彦星と織女と逢瀬」を成就したのであろうか? あの橋を渡っている顔つきを見ると、頭上で鳴いている鴉の「「カーカー」と、どこか淋し気であるわい(蛇足)。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「風流三ッのはじめ」(Theree Elegant Beginnings) (「慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション/Digital Collections of Keio University Libraries」)
https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/ukiyoe/0008
【「横雲やきふうのかわる日の出かな」 青楼の店先での後朝の別れの一齣。遊女の方はいまだ名残尽きせぬ様子で上目遣いに客を見やるが、一方の遊客は上半身は振り返っているものの足はすでに帰途に踏み出している。遊里のはかないかりそめの恋愛風景といえようか。朝陽の中に活動を始め、飛び交う鴉たちの鳴き声も白々しく聞こえてくるようである。 礒田湖龍斎は、世間が春信美人のブームに湧く頃浮世絵界に登場した。本図に見られるごとく、初期の画風は春信風に近似しているが、次第に独自の美人画様式を確立した。(樋口一貴)
作者/磯田湖龍斎/作者英名koryusai/画題 風流三ッのはじめ/請求記号200X@59/制作年代
18世紀後期/版元 なし/極印 なし/版型 中判錦絵/寸法 26.3×19.2/署名 湖龍斎画 】
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「後朝きぬぎぬの図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)
(「早稲田大学図書館」蔵)
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0008.jpg
4-15 寝やと言ふ禿またねずけふの月
季語=「けふの月」(仲秋)
【解説】 旧暦八月十五日の月のこと。「名月をとつてくれろと泣く子かな」と一茶の句にもあるように、手を伸ばせば届きそうな大きな月である。団子、栗、芋などを三方に盛り、薄の穂を活けてこの月を祭る。
【例句】
名月や池をめぐりて夜もすがら 芭蕉「孤松」
たんだすめ住めば都ぞけふの月 芭蕉「続山の井」
木をきりて本口みるやけふの月 芭蕉「江戸通り町」
蒼海の浪酒臭しけふの月 芭蕉「坂東太郎」
【参考】
十五から酒をのみ出てけふの月 其角「五元集」
闇の夜は吉原はかり月夜哉 其角「五元集」
「禿(かぶろ)」=遊女に使われる少女。太夫(たゆう)、天神など上位の遊女に仕えて、その見習いをする六、七歳から一三、四歳ぐらいまでの少女。かぶろっこ。かむろ。(「精選版 日本国語大辞典」)
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
※仮名草子・浮世物語(1665頃)一「禿(カブロ)、遣手(やりて)も空(そら)知らぬ風情なり」
(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=これも「吉原」の句であろう。其角の「吉原」の「闇の夜は吉原はかり月夜哉」(『五元集』)などが背景にあるような雰囲気である。
句意=「緑樹影沈(ん)では」、今日は、陰暦八月十五日の「仲秋の名月」である。この吉原の妓楼の遊女に仕えている「禿」(少女)の名は「寝(ねれ・ね)や」と、面白い名なのだが、「また(まだ)」一睡もしないで、「不寝番(ねずのばん)をしている。
(参考) 「吉原」の「遊女(「花魁」など)周辺
「忘八(ぼうはち)」=遊女屋の当主。仁・義・礼・智・信・孝・悌・忠の8つの「徳」を忘れたものとされていた。
「禿(かむろ)」=花魁の身の回りの雑用をする10歳前後の少女。彼女達の教育は姉貴分に当たる遊女が行った。禿(はげ)と書くのは毛が生えそろわない少女であることからの当て字である。
「番頭新造(ばんとうしんぞう)」=器量が悪く遊女として売り出せない者や、年季を勤め上げた遊女が務め、マネージャー的な役割を担った。花魁につく。ひそかに客を取ることもあった。「新造」とは武家や町人の妻を指す言葉であったが、後に未婚の女性も指すようになった。
「振袖新造(ふりそでしんぞう)」=15-16歳の遊女見習い。禿はこの年頃になると姉貴分の遊女の働きかけで振袖新造になる。多忙な花魁の名代として客のもとに呼ばれても床入りはしない。しかし、稀にはひそかに客を取るものもいた。その代金は「つきだし」(花魁としてデビューし、水揚げを迎える日)の際の費用の足しとされた。振袖新造となるものは格の高い花魁となる将来が約束されたものである。
「留袖新造(とめそでしんぞう)」=振袖新造とほぼ同年代であるが、禿から上級遊女になれない妓、10代で吉原に売られ禿の時代を経なかった妓がなる。振袖新造は客を取らないが、留袖新造は客を取る。しかし、まだ独り立ちできる身分でないので花魁につき、世話を受けている。
「太鼓新造(たいこしんぞう)」=遊女でありながら人気がなく、しかし芸はたつので主に宴会での芸の披露を担当した。後の吉原芸者の前身のひとつ。
「遣手(やりて)」=遊女屋全体の遊女を管理・教育し、客や当主、遊女との間の仲介役。誤解されがちだが当主の妻(内儀)とは別であり、あくまでも従業員。難しい役どころのため年季を勤め上げた遊女や、番頭新造のなかから優秀な者が選ばれた。店にひとりとは限らなかった。
(「ウィキペディア」)
「妓夫」=遊里で客を引く男。遣手婆について,二階の駆引き,客の応待などもした。私娼や夜の字をあてたのは明治以降のことであるといわれる。この言葉の源は,承応の頃 (1652~55) ,江戸,葺屋町の「泉風呂」で遊女を引回し,客を扱っていた久助という男にあり,『洞房語園』によると,その男の煙草 (たばこ) を吸うさまが「及 (きゅう) 」の字に似ていたので,人々が彼をして「きゅう」というようになり,それがいつしか「ぎゅう」となり,やがて,かかる男たちの惣名になった,とある(「精選版 日本国語大辞典」)。
4-16 花方に団子喰せつ今日の月
季語=「今日の月」=「けふの月」(仲秋)
「花方」=「花形」=花形(はながた):はなやかで人気のある人や物のこと。(「ウィキペディア」) ここは、「吉原」の「花形」である「花魁(おいらん)」と、その取り巻きを指しているものと解したい。
「花魁(おいらん)」=江戸・吉原における上級遊女の別称。語源としては、遊女に従属する新造(しんぞう)や禿(かむろ)が姉女郎を「おいらがの(私の)」とよんだのがなまったとする説などがあるが、明らかではない。いずれにしても口語体から発生したらしく、漢字は当て字である。洒落本(しゃれぼん)には、姉妓、姉娼、全盛、妹妓など多数の当て字が使われている。そのなかで、ものいう花(美女)の魁(かしら)という意味をもつ花魁が、広く使用されて代表的文字となった。語源の伝承にもあるように、花魁は尊称的美称であって職名でないため、どの階級の遊女がこれに相当するかは一定していない。花魁の称が一般化した明和(めいわ)(1764~72)ごろは、吉原では太夫(たゆう)が衰滅して散茶(さんちゃ)がこれにかわった時代であるが、散茶のなかの最上格である呼出しを、初めは花魁とよんだという。呼出しは張り見世をしない別格であったが、のちには次位の昼三(ちゅうさん)や、その下の座敷持(ざしきもち)なども花魁とよぶようになった。ただし、いずれも2部屋以上の座敷を与えられ、新造2~3人、禿2~3人を従え、座敷には各種の調度をそろえ、寝具は重ねふとんであった。[原島陽一](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)
句意(その周辺)=「吉原」での「月見」には、とんと金がかかる。その「花方」の「花魁」と、その取り巻き連中に、「団子」(料理)を振舞いつつ、豪奢に「良夜」を楽しんでいる。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「良夜之図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)
(「早稲田大学図書館」蔵)
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0004.jpg
4-17 名月やもと塩窰(塩釜)の人通り
季語=名月(仲秋)
(参考句)
沾徳岩城に逗留して、餞別の句なき恨むるよし聞え侍りしに
松島や嶋かすむとも此序 其角「五元集」
南村千調仙臺へかへるに
行春や猪口を雄嶋の忘貝 其角「五元集」
「塩窰(塩釜)」=この「塩窰(塩釜)」は、謡曲「融」の、次のような一節を踏まえているように解したい。
https://japanese.hix05.com/Noh/4/yokyoku402.tooru.html
【シテ一セイ「月も早。出汐になりて塩釜の。うらさび渡る。気色かな。
サシ「陸奥はいづくはあれど塩釜の。うらみて渡る老が身の。よるべもいさや定なき。心も澄める水の面に。照る月並を数ふれば。今宵ぞ秋の最中なる。実にや移せば塩釜の。月も都の最中かな。
下歌「秋は半身は既に。老いかさなりてもろ白髪。
上歌「雪とのみ。積りぞ来ぬる年月の。積りぞ来ぬる年月の。春を迎へ秋を添へ。時雨るゝ松の。風までも我が身の上と汲みて知る。汐馴衣袖寒き。浦わの秋の夕かな浦わの。秋の夕かな。】
句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」は、謡曲「融(とおる)」の名調子である。今宵の「名月」、その世阿弥の「融」の背景となっている「伊勢物語第八十一段」の、「塩竈にいつか来にけむ朝なぎに釣する舟はこゝに寄らなん」などが、脳裏を去来している。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
謡曲「融」の舞台図と「京名所案内」
http://insite-r.co.jp/Noh/shunkoukai/2019/tooru/tooru_notice.html
4-18 印籠の一つ下(れ)るやからす瓜
季語=からす瓜=烏瓜(からすうり)/晩秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/3484
【子季語】 王瓜、王章
【解説】 ウリ科の多年草。山野に自生する蔓草。夏に白いレースのような 花を咲かせ秋に実をつける。実は卵形で、縞のある緑色から熟し て赤や黄に色づく。
【例句】
竹藪に人音しけり烏瓜 惟然「惟然坊句集」
まだき冬をもとつ葉もなしからす瓜 蕪村「夜半叟句集」
くれなゐもかくてはさびし烏瓜 蓼太「蓼太句集初編」
溝川や水に引かるる烏瓜 一茶「文政九年句帖
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「蒔絵烏瓜図印籠 萬麟齊」
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k533664600
「印籠」=腰に下げる三重または五重の長円筒形の小箱。箱には蒔絵(まきえ)、堆朱(ついしゅ)、螺鈿(らでん)などの細工が施され、緒には緒締め、根付けがある。もと印判を入れたところからいい、室町頃から薬を入れるようになった。主として武士の礼装の装飾品。薬籠。印籠巾着。〔東京教育大本下学集(室町中)〕
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
※浮世草子・好色一代男(1682)七「田舎大じん印籠(ヰンラウ)あけて、いく薬かあたえけるを」(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」の、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」の、その謡曲「融(とおる)」の名調子などを吟じながら、腰に差している「蒔絵烏瓜図印籠烏瓜」を、お相手してくれる相方に、「これ、烏瓜」と、「これを見たら思い出してくれ」と、手渡すような、そんな、雰囲気の句である。
4-19 貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤
季語=蛤=蛤(はまぐり)/三春
https://kigosai.sub.jp/001/archives/849#:~:text=%E8%9B%A4%E3%81%AF%E6%98%A5%E3%80%81%E8%BA%AB%E3%81%8C,%E8%9B%A4%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E9%A3%9F%E5%8D%93%E3%81%AB%E4%B8%8A%E3%82%8B%E3%80%82
【子季語】 蛤鍋、蒸蛤、焼蛤、蛤つゆ
【解説】 蛤は春、身がふっくらと肥え、旬を迎える。二枚の貝は他のものとは決して合わないことから末永い夫婦の縁の象徴とされ、婚礼や雛の節句などの細工、貝合せなどに用いられ、平安時代には、薬入れとしても使われた。吸物、蒸し物、蛤鍋、焼蛤として食卓に上る。桑名の焼蛤、大阪の住吉神社の洲崎の洲蛤が有名。
【例句】
尻ふりて蛤ふむや南風 涼菟「喪の名残」
蛤の芥を吐かする月夜かな 一茶「七番日記」
【参考】
この句(「貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤」)は、『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』(p124~p128)で、次のとおり紹介されている。(一部抜粋)
≪『句藻』「椎の木陰」に「送笠堂主人文(りゅうどうしゅじんにおくるふみ)」という俳文に見られる。寛政八年(一七九六)秋、川越(埼玉県川越市)の瓢坊が其貝(きばい)と改名するのを祝ったのである。
「抑(そもそも)、元禄十五年長月十六日のうら遊びに、晋子(其角)が見し、雀の足をはさみし貝ならんか。此(この)貝、必(かならずしも)中に明珠(めいしゅ)を含(ふくむ)るか。此珠(このたま)、彫琢を頼ずして、光、晋流のくらきを照らすべしと祝ひ、藻に住(すむ)虫の我等迄も、五七五の一章句を申送り侍る。
貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤 (『句藻』「椎の木陰」) ≫
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇
句意(その周辺)=この句は、其角の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」(『類柑子』「浦あそび」)の本句取りの一句である。抱一は、文化三年(一八〇六)、四十六歳の時に、「其角百回忌」として、その「肖像百幅」(其角肖像画と其角の句の賛)を制作する(上記の図は、その内の一つで「夜光る画賛」のものである。これらについては、下記のアドレスの「参考」で紹介している)。
句意=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の元祖ともいうべ其角宗匠の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」を変奏して、その「必ず中に明珠を含む」縁起が良い「夜蛤」の句を、次のような一句として、それに唱和することにする。
「貝の班(ふ)の」(この貝の模様は)、「雀に似たり」(其角宗匠が目にした「雀の足を咥えた蛤」の、その「雀に似たり)、「夜蛤」(彫琢(てうたく)を頼(たよら)ずして、光(ひかり)、晋流(しんりう=其角俳諧)のくらきを照らすべし)
(参考) 「其角肖像百幅」(抱一筆・賛=其角句)周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-09-30
【(再掲)
https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22
(画像)→上記のとおり
酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇
「晋子とは其角のこと。抱一が文化三年の其角百回忌に描いた百幅のうちの一幅。新出作品。『夜光るうめのつぼみや貝の玉』(『類柑子』『五元集』)という其角の句に、略画体で其角の肖像を記した。左下には『晋子肖像百幅之弐』という印章が捺されている。書風はこの時期の抱一の書風と比較すると若干異なり、『光』など其角の奔放な書風に似せた気味がある。其角は先行する俳人肖像集で十徳という羽織や如意とともに表現されてきたが、本作はそれに倣いつつ、ユーモアを漂わせる。」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「抱一の俳諧(井田太郎稿)」)
この著者(井田太郎)が、『酒井抱一---俳諧と絵画の織りなす抒情』(岩波新書一七九八)を刊行した(以下、『井田・岩波新書』)。
この『井田・岩波新書』では、この「其角肖像百幅」について、現在知られている四幅について紹介している。
一 「仏とはさくらの花の月夜かな」が書かれたもの(伊藤松宇旧蔵。所在不明)
二 「お汁粉を還城楽(げんじょうらく)のたもとかな」同上(所在不明)
三 「夜光るうめのつぼみや貝の玉」同上(上記の図)
四 「乙鳥の塵をうごかす柳かな」同上(『井田・岩波新書』執筆中の新出)(以下略) 】
4-20 降り年や初茸売りが声の錆
季語=初茸=初茸(はつたけ)/三秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/5680#:~:text=%E8%8C%B8%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%80,%E3%81%A7%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%8C%E8%96%84%E8%8C%B6%E8%89%B2%E3%80%82
【解説】 茸のなかでも一番早く生えるのでこの名がついた。傘は扁平で全体が薄茶色。傷みやすく、傷になった部分は青く変色する。
【例句】
初茸やまだ日数経ぬ秋の露 芭蕉「小文庫」
【参考】 「初茸」周辺(「ウィキペディア」)
(歴史)
特に関東地方で親しまれ、守貞漫稿(食類-後巻之一)には「初茸売り。山のきこりや八百屋がハツタケを売る。京阪にはハツタケは無い。江戸だけで売られる。」とあり、当時の関西ではあまり人気がなかったのに対し、マツタケがほとんど産出しない江戸近辺では、食用としてよく利用されたようである。千葉県では特に珍重されたといい、旧佐倉堀田藩鹿渡村(現在の千葉県四街道市鹿渡)においては、嘉永3(1850)年庚戌年(かのえいぬ)九月十日(旧暦)付の回状として「初茸 七十ケ 右ハ御用ニテ不足無ク 来ル十三日 四ツ時迄ニ 上納致ス可シ 尤モ軸切下致シ 相納メル可ク候 此廻状 早々順達致ス可ク候 以上」の文面が発行された記録がある。(中略)
さらに、続江戸砂子(菊岡光行著:享保20年=1735年)には、「江府(=江戸)名産並近在近国」として「小金初茸・下総国葛飾郡小金之辺、所々出而発:在江府隔六里内外:在相州藤沢戸塚辺産、早産比下総:相州之産存微砂而食味下品。下総之産解砂而有風味佳品(小金初茸、下総国葛飾郡小金の辺、所々より出る。江戸より六里程。相州藤沢戸塚辺より出る初茸は、下総より早い。しかし相州産のものは微砂をふくみ、歯にさわってよくない。下総産のものは砂がなく、風味ももっとも佳い)。」との記事 がみえる。おそらくは、相模湾岸に広がるクロマツ林に産するハツタケと、内陸のアカマツ林に生えるハツタケとを比較したものではないかと思われる。
(生態・生理)
日本では、夏から秋(時に梅雨期)、アカマツ・クロマツ・リュウキュウマツ などの二針葉マツ類の樹下に発生し、これらの樹木の生きた細根に典型的な外生菌根(フォーク状に二叉分岐し、白色 または赤紫色を呈するを形成して生活する。(中略)
(ハツタケと文学)
秋の季語の一つとして知られることからも、日本人とハツタケとの関わりが深いものであることが推察される。
(例句)=一部抜粋
初茸やまだ日数 へぬ秋の露 芭蕉
初茸の無疵に出るや袂から 一茶
初茸のさび声門に秋の風 柳樽七五・8
青錆に成る初茸の旅労(つか)レ 柳樽八三・75
句意(その周辺)=「初茸」は、「初」の字がついているのだが、「新年」の季語ではなく、「古年」の「秋」の季語で、「雨の降る梅雨」明けの、特に、江戸近郊で食用される「江戸前(江戸風)の茸(きのこ)」である。その「初茸(たけ)売り」の声が、「初茸のさび声門に秋の風」(柳樽七五・8)で、夏から秋の「江戸前の風物詩」の一つとなっている。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
河東節/助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)
https://www.youtube.com/watch?v=Znm06U_7WEk
「春霞 立てるやいずこ三芳野の 山口三浦うらうらと
うら若草や初花に 和らぐ土手を誰がいうて 日本めでたき国の名の
豊芦原や吉原に 根こじて植えし江戸桜
匂う夕べの風に連れ 鐘は上野か浅草か」
季語=「雲の峰」=雲の峰(くものみね)三夏
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2036
【子季語】 積乱雲、入道雲、峰雲
【解説】 盛夏、聳え立つ山並みのようにわき立つ雲。積乱雲。夏といえば入道雲であり、夏の代名詞である。強い日差しを受けて発生する激しい上昇気流により、巨大な積雲に成長して行く。地方により坂東太郎・丹波太郎・信濃太郎・石見太郎・安達太郎・比古太郎などとよばれる。
【例句】
雲の峰幾つ崩れて月の山 芭蕉「奥の細道」
ひらひらとあぐる扇や雲の峰 芭蕉「笈日記」
湖やあつさををしむ雲のみね 芭蕉「笈日記」
雲の峰きのふに似たるけふもあり 白雄「白雄句集」
しづかさや湖水の底の雲のみね 一茶「寛政句帖」
仙薬=① 飲むと仙人になるという薬。不老不死の薬。仙丹。
※霊異記(810‐824)上「『逕ること八日、夜、銛き鋒に逢はむ。願はくは仙薬を服せ』といひて」 〔史記‐始皇本紀〕
② 非常によくきく不思議な薬。霊薬。
※今昔(1120頃か)五「国王、此は仙薬を服せるに依て也と知て」
(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=この句には「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」との前書がある。この前書からすると、一茶の「しづかさや湖水の底の雲のみね」に近い、「緑樹の影と入道雲のが水底に沈んで、その入道雲を、魚が、あたかも、仙薬(不老不死の薬)のように舐めている」というような句意となる。
(参考)『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』で紹介されている句意周辺
この句は、『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』(p77~p78)で、其角の「香薷散(かうじゆさん)犬がねぶつて雲の峯」(『五元集』)の句を変奏しているとの謎解きをしている。
それによると、この前書は、謡曲(「竹生島(ちくぶじま)」)の「緑樹影沈(しづ)みて、魚木に上る気配あり」を摘まんだものと指摘している。そして、其角の句は、「夏雲が水たまりに影を落とす。犬が水たまりの茶色い水をなめるので、さながら犬が雲のなかにいるかのようである」として、その「茶色い水(液体)」は、「暑気払い」の「茶色い・香薷散」の見立てと喝破している。
この其角の「香薷散」の句は、下記のアドレスで紹介している。
ttps://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false
【〇 香薷(じゆ)散犬がねぶつて雲の峰 (其角『五元集』)
〇 まとふどな犬ふみつけて猫の恋 (芭蕉『菊の道』)
四十一 掲出の一句目の其角の句は、「雲の峰が立つ真夏の余りの暑さに、犬までが暑気払いの『香薷(じゆ)散』を舐(なぶ)っている」という意であろう。この句の背後には、『事文類聚』(「列仙全伝」)の故事(准南王が仙とし去った後、仙薬が鼎中に残っていたのを鶏と犬とが舐めて昇天し、雲中に鳴いたとある)を踏まえているという。さらに、この句の真意は、「将軍綱吉の生類憐れみの令による犬保護の世相を背景とし、犬の増長ぶりを諷している」という(今泉・前掲書)。と解すると、これまた、其角の時の幕政への痛烈な風刺の句ということになる。それに比して、其角の師匠の芭蕉の二句目の犬の句は、「恋に切なく身を焦がす猫が、おっとり寝そべっている犬を踏みつけてうろつきまわっている」と、主題は「猫の恋」で実にのんびりとした穏やかな光景である。この「まとふど」は、「全人(またいびと)」の「純朴で正直な人」から転じての「とんま・偶直な」という意とのことである(井本農一他注解『松尾芭蕉集』)。いずれにしろ、ここには、其角のような、時の幕政への痛烈な風刺の句というニュアンスは感知されない。芭蕉もまた、反権力・反権威ということにおいては、人後に落ちない「隠棲の大宗匠」という雰囲気だが、どちらかというと、「おくのほそ道」に関わる「芭蕉隠密説」も流布されるように、「親幕府」という趣だが、こと、その蕉門第一の高弟・其角は、「反幕府」という趣なのが、何とも好対照なのである。ちなみに、芭蕉もまた、其角と同様に、綱吉の「生類憐れみの令」の御時世の元禄の俳人であったことは、付言する必要もなかろう。】
ここまで来ると、其角の句も、抱一の句も、それこそ、正岡子規の、「抱一の画、濃艶愛すべしといえども、俳句に至っては拙劣見るに堪えず」と、「チンプンカンプン」ということで、敬遠されることになる。
しかし、抱一の、その句の周辺を探るには、その作意の本筋の「其角」の句は手に負えないとしても、より、定石的な、より、理解し易い、例えば、上記の、「季語」の解説の「例句」などを補助線にすると、何かが見えてくるような、そして、そういう、「抱一の発句、濃艶愛すべし」という見方もあるように思える。
4-13 秋旣(すでニ)ちかづきふへて蛍がり
季語=「秋」と「蛍」=「秋の蛍」=秋の蛍(あきのほたる) 初秋
https://kigosai.sub.jp/?s=%E7%A7%8B%E3%81%AE%E8%9B%8D&x=0&y=0
【子季語】 秋蛍/残る蛍/病蛍
【解説】 秋風が吹く頃の蛍である。弱々しく放つ光や季節を外れた侘しさが本意。
【例句】
世の秋の蛍はその日おくりかな 信徳「口真似草」
死ぬるとも居るとも秋を飛ぶ蛍 乙州「西の雲」
牛の尾にうたるる秋のほたるかな 成美「成美家集」
蛍減る秋を浅香の橋作り 乙二「をののえ草稿」
「ほたるがり」=夏の夜、水辺などに光る蛍を捕えて遊ぶこと。ほたるおい。《季・夏》
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
※浮世草子・好色産毛(1695頃)三「上鴨の蛍狩(ホタルガリ)、宇治瀬田は更也、北野平野に勝て、市原二の瀬の柴口鼻(しばかか)が帰る夜道をかがやかし」 (「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=この句も難解句の一つである。まず、前句(4-12)の前書(「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」)が掛かる一群(「4-12」~「4-20」)の句の、二番目の句と解したい。その上で、この句の「秋旣(既の「異字体」)ちかづきふへて蛍がり」の詠みは、「秋既(すで)ニ/ちかづき・ふへて/蛍がり」(五・七・五)の詠みとして置きたい。
句意=緑樹の影も沈んで、既に、夏から秋へとの気配を漂わせている。その忍び寄る初秋の夜に蛍の数は増えて、その最後の蛍狩りに興じている。
(参考) 其角の蛍の句(「此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉(『五元集』)」)周辺
https://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false
【(謎解き・二十一)
〇 鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分 (其角『五元集』)
〇 夕顔にあはれをかけよ売名号 (其角『五元集』)
〇 此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉 (其角『五元集』)
四十 この掲出の三句は、『五元集』では、一句目が「春」、二句・三句目が「夏」と分かれて掲載されているが、その『五元集』のもとになっている『焦尾琴』の「早船の記」では、次のように掲載されているうちの三句である。
http://kikaku.boo.jp/haibun.html
其引 所の産を寄て
※行水や何にとゝまる海苔の味 其角
朝皃の下紐ひちて蜆とり 午寂
雨雲や簀に干海苔の片明り 文士
幕洗ふ川辺の比や郭公 序令
椎の木に衣たゝむや村時雨 同
浮島の親仁組也余情川 景口(けいれん)
すまふ取ゆかしき顔や松浦潟 同
建坪の願ひにみせつ小萩はら 白獅
※幸清か霧のまかきや昔松 其角
※鯉に義は山吹の瀬やしらぬ分 同
さなきたに鯉も浮出て十三夜 秋航
雷の撥のうはさや花八手 百里
夕月や女中に薄き川屋敷 同
村雨や川をへたてゝつくつくし 甫盛
後からくらう成けり土筆 堤亭
揚麩には祐天もなし昏の鴫 朝叟
※夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号 其角
河上に音楽あり
笙の肱是も帆に張夏木立 午寂
お手かけの菫屋敷は栄螺哉 同
こまかたに舟をよせて
※此碑ては江を哀(カナシ)まぬ蛍哉 其角
若手共もぬけの舟や更る月 楓子
さて、この掲出の一句目の、「鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分」は、「綾瀬の御留川(漁獲禁止の川)の名物の山吹鯉を獲るのに、見張りの役人に少々山吹色の小判を与えれば、見て見ぬふりをしてくれる」という世相風刺(当時の幕政の腐敗の風刺)の句のようなのである(今泉・前掲書)。
二句目の「夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号」は、『五元集』では、「裕天和尚に申す」との前書きがあり、この裕天和尚は、当時の五代将軍綱吉の母桂昌院の尊信を受け、隅田川東岸の牛島を去って、一躍高位の僧となられた方で、その「裕天和尚に申す」という形での、「売名号」(仏あるいは菩薩の名号を書いた札で、書き手によって御利益がある)の御利益のように、民衆に「哀れをかけよ」としての、これまた、当時の幕政への不満に基づく風刺の句のようなのである。
この「夕顔」は、『源氏物語』の「夕顔」の「山がつが垣穂荒るともをりをりはあはれをかけよ撫子のつゆ」を踏まえているとのことである(今泉・前掲書)。そして、三句目の「此碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉」は、「この殺生禁断の碑のお蔭で何となく不景気で、川の流れを眺めながら哀れに感じないのは蛍だけ」という意の、当時の五代将軍綱吉の「生類憐れみの令」への嘆きの句であるという(半藤・前掲書)。其角の謎句には、このような当時の幕政への痛烈な風刺の句があり、その意味では、其角は、終始一貫して、反権力・反権威の反骨の俳人という姿勢を貫いている。
こういう句の背後にあるものを、当時の人でも察知できる者と、察知できない者と、完全に二分されていたのであろう。そして、その背後にあるものを察知できない者は、其角の句を「奇想・奇抜・意味不明」の世界のものとして排斥していったということは、容易に想像のできるところのものである。】
4-14 きぬぎぬの橋に成(なり)たかあの鴉
季語=「きぬぎぬの橋」=「後朝の橋」=「鵲の橋(かささぎのはし)」 初秋
https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%B5%B2%E3%81%AE%E6%A9%8B&x=0&y=0
【子季語】 星の橋/行合の橋/寄羽の橋/天の小夜橋/紅葉の橋/烏鵲の橋
【解説】 七夕の夜、天の川を渡る織姫のため、かささぎが羽を連ねて橋となること。
【例句】
かささぎやけふ久かたのあまの川 守武「飛梅千句」
鵲の橋や銀河のよこ曇り 来山「続今宮草」
かささぎや石を重りの橋も有り 其角「浮世の北」
【参考】 鵲=鵲(かささぎ)三秋=七夕伝説に登場する鳥。天の川を渡る織姫のために羽を連ねて橋を作るという。カラスに似ているが腹部が白いのでカラスと見分けられる。
「鴉・烏」だけでは、季語の働きはしない。「春= 鴉の巣/夏= 鴉の子/冬= 寒烏/新年 =初烏」。
この抱一の句では、「きぬぎぬの橋」(「鵲の橋」)と「鴉」との取り合わせで、「初秋」の句ということになろう。そして、この句は、「吉原」の「きぬぎぬの別れ」の「あの鴉(男)」=「吉原帰りの男」の見立てということになる。
句意(その周辺)=緑樹の影も沈んで、七夕の季節、あの吉原帰りの「鴉(からす)野郎」は、昨夜は、「鵲の橋」を渡って、「彦星と織女と逢瀬」を成就したのであろうか? あの橋を渡っている顔つきを見ると、頭上で鳴いている鴉の「「カーカー」と、どこか淋し気であるわい(蛇足)。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「風流三ッのはじめ」(Theree Elegant Beginnings) (「慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション/Digital Collections of Keio University Libraries」)
https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/ukiyoe/0008
【「横雲やきふうのかわる日の出かな」 青楼の店先での後朝の別れの一齣。遊女の方はいまだ名残尽きせぬ様子で上目遣いに客を見やるが、一方の遊客は上半身は振り返っているものの足はすでに帰途に踏み出している。遊里のはかないかりそめの恋愛風景といえようか。朝陽の中に活動を始め、飛び交う鴉たちの鳴き声も白々しく聞こえてくるようである。 礒田湖龍斎は、世間が春信美人のブームに湧く頃浮世絵界に登場した。本図に見られるごとく、初期の画風は春信風に近似しているが、次第に独自の美人画様式を確立した。(樋口一貴)
作者/磯田湖龍斎/作者英名koryusai/画題 風流三ッのはじめ/請求記号200X@59/制作年代
18世紀後期/版元 なし/極印 なし/版型 中判錦絵/寸法 26.3×19.2/署名 湖龍斎画 】
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「後朝きぬぎぬの図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)
(「早稲田大学図書館」蔵)
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0008.jpg
4-15 寝やと言ふ禿またねずけふの月
季語=「けふの月」(仲秋)
【解説】 旧暦八月十五日の月のこと。「名月をとつてくれろと泣く子かな」と一茶の句にもあるように、手を伸ばせば届きそうな大きな月である。団子、栗、芋などを三方に盛り、薄の穂を活けてこの月を祭る。
【例句】
名月や池をめぐりて夜もすがら 芭蕉「孤松」
たんだすめ住めば都ぞけふの月 芭蕉「続山の井」
木をきりて本口みるやけふの月 芭蕉「江戸通り町」
蒼海の浪酒臭しけふの月 芭蕉「坂東太郎」
【参考】
十五から酒をのみ出てけふの月 其角「五元集」
闇の夜は吉原はかり月夜哉 其角「五元集」
「禿(かぶろ)」=遊女に使われる少女。太夫(たゆう)、天神など上位の遊女に仕えて、その見習いをする六、七歳から一三、四歳ぐらいまでの少女。かぶろっこ。かむろ。(「精選版 日本国語大辞典」)
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
※仮名草子・浮世物語(1665頃)一「禿(カブロ)、遣手(やりて)も空(そら)知らぬ風情なり」
(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=これも「吉原」の句であろう。其角の「吉原」の「闇の夜は吉原はかり月夜哉」(『五元集』)などが背景にあるような雰囲気である。
句意=「緑樹影沈(ん)では」、今日は、陰暦八月十五日の「仲秋の名月」である。この吉原の妓楼の遊女に仕えている「禿」(少女)の名は「寝(ねれ・ね)や」と、面白い名なのだが、「また(まだ)」一睡もしないで、「不寝番(ねずのばん)をしている。
(参考) 「吉原」の「遊女(「花魁」など)周辺
「忘八(ぼうはち)」=遊女屋の当主。仁・義・礼・智・信・孝・悌・忠の8つの「徳」を忘れたものとされていた。
「禿(かむろ)」=花魁の身の回りの雑用をする10歳前後の少女。彼女達の教育は姉貴分に当たる遊女が行った。禿(はげ)と書くのは毛が生えそろわない少女であることからの当て字である。
「番頭新造(ばんとうしんぞう)」=器量が悪く遊女として売り出せない者や、年季を勤め上げた遊女が務め、マネージャー的な役割を担った。花魁につく。ひそかに客を取ることもあった。「新造」とは武家や町人の妻を指す言葉であったが、後に未婚の女性も指すようになった。
「振袖新造(ふりそでしんぞう)」=15-16歳の遊女見習い。禿はこの年頃になると姉貴分の遊女の働きかけで振袖新造になる。多忙な花魁の名代として客のもとに呼ばれても床入りはしない。しかし、稀にはひそかに客を取るものもいた。その代金は「つきだし」(花魁としてデビューし、水揚げを迎える日)の際の費用の足しとされた。振袖新造となるものは格の高い花魁となる将来が約束されたものである。
「留袖新造(とめそでしんぞう)」=振袖新造とほぼ同年代であるが、禿から上級遊女になれない妓、10代で吉原に売られ禿の時代を経なかった妓がなる。振袖新造は客を取らないが、留袖新造は客を取る。しかし、まだ独り立ちできる身分でないので花魁につき、世話を受けている。
「太鼓新造(たいこしんぞう)」=遊女でありながら人気がなく、しかし芸はたつので主に宴会での芸の披露を担当した。後の吉原芸者の前身のひとつ。
「遣手(やりて)」=遊女屋全体の遊女を管理・教育し、客や当主、遊女との間の仲介役。誤解されがちだが当主の妻(内儀)とは別であり、あくまでも従業員。難しい役どころのため年季を勤め上げた遊女や、番頭新造のなかから優秀な者が選ばれた。店にひとりとは限らなかった。
(「ウィキペディア」)
「妓夫」=遊里で客を引く男。遣手婆について,二階の駆引き,客の応待などもした。私娼や夜の字をあてたのは明治以降のことであるといわれる。この言葉の源は,承応の頃 (1652~55) ,江戸,葺屋町の「泉風呂」で遊女を引回し,客を扱っていた久助という男にあり,『洞房語園』によると,その男の煙草 (たばこ) を吸うさまが「及 (きゅう) 」の字に似ていたので,人々が彼をして「きゅう」というようになり,それがいつしか「ぎゅう」となり,やがて,かかる男たちの惣名になった,とある(「精選版 日本国語大辞典」)。
4-16 花方に団子喰せつ今日の月
季語=「今日の月」=「けふの月」(仲秋)
「花方」=「花形」=花形(はながた):はなやかで人気のある人や物のこと。(「ウィキペディア」) ここは、「吉原」の「花形」である「花魁(おいらん)」と、その取り巻きを指しているものと解したい。
「花魁(おいらん)」=江戸・吉原における上級遊女の別称。語源としては、遊女に従属する新造(しんぞう)や禿(かむろ)が姉女郎を「おいらがの(私の)」とよんだのがなまったとする説などがあるが、明らかではない。いずれにしても口語体から発生したらしく、漢字は当て字である。洒落本(しゃれぼん)には、姉妓、姉娼、全盛、妹妓など多数の当て字が使われている。そのなかで、ものいう花(美女)の魁(かしら)という意味をもつ花魁が、広く使用されて代表的文字となった。語源の伝承にもあるように、花魁は尊称的美称であって職名でないため、どの階級の遊女がこれに相当するかは一定していない。花魁の称が一般化した明和(めいわ)(1764~72)ごろは、吉原では太夫(たゆう)が衰滅して散茶(さんちゃ)がこれにかわった時代であるが、散茶のなかの最上格である呼出しを、初めは花魁とよんだという。呼出しは張り見世をしない別格であったが、のちには次位の昼三(ちゅうさん)や、その下の座敷持(ざしきもち)なども花魁とよぶようになった。ただし、いずれも2部屋以上の座敷を与えられ、新造2~3人、禿2~3人を従え、座敷には各種の調度をそろえ、寝具は重ねふとんであった。[原島陽一](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)
句意(その周辺)=「吉原」での「月見」には、とんと金がかかる。その「花方」の「花魁」と、その取り巻き連中に、「団子」(料理)を振舞いつつ、豪奢に「良夜」を楽しんでいる。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「良夜之図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)
(「早稲田大学図書館」蔵)
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0004.jpg
4-17 名月やもと塩窰(塩釜)の人通り
季語=名月(仲秋)
(参考句)
沾徳岩城に逗留して、餞別の句なき恨むるよし聞え侍りしに
松島や嶋かすむとも此序 其角「五元集」
南村千調仙臺へかへるに
行春や猪口を雄嶋の忘貝 其角「五元集」
「塩窰(塩釜)」=この「塩窰(塩釜)」は、謡曲「融」の、次のような一節を踏まえているように解したい。
https://japanese.hix05.com/Noh/4/yokyoku402.tooru.html
【シテ一セイ「月も早。出汐になりて塩釜の。うらさび渡る。気色かな。
サシ「陸奥はいづくはあれど塩釜の。うらみて渡る老が身の。よるべもいさや定なき。心も澄める水の面に。照る月並を数ふれば。今宵ぞ秋の最中なる。実にや移せば塩釜の。月も都の最中かな。
下歌「秋は半身は既に。老いかさなりてもろ白髪。
上歌「雪とのみ。積りぞ来ぬる年月の。積りぞ来ぬる年月の。春を迎へ秋を添へ。時雨るゝ松の。風までも我が身の上と汲みて知る。汐馴衣袖寒き。浦わの秋の夕かな浦わの。秋の夕かな。】
句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」は、謡曲「融(とおる)」の名調子である。今宵の「名月」、その世阿弥の「融」の背景となっている「伊勢物語第八十一段」の、「塩竈にいつか来にけむ朝なぎに釣する舟はこゝに寄らなん」などが、脳裏を去来している。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
謡曲「融」の舞台図と「京名所案内」
http://insite-r.co.jp/Noh/shunkoukai/2019/tooru/tooru_notice.html
4-18 印籠の一つ下(れ)るやからす瓜
季語=からす瓜=烏瓜(からすうり)/晩秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/3484
【子季語】 王瓜、王章
【解説】 ウリ科の多年草。山野に自生する蔓草。夏に白いレースのような 花を咲かせ秋に実をつける。実は卵形で、縞のある緑色から熟し て赤や黄に色づく。
【例句】
竹藪に人音しけり烏瓜 惟然「惟然坊句集」
まだき冬をもとつ葉もなしからす瓜 蕪村「夜半叟句集」
くれなゐもかくてはさびし烏瓜 蓼太「蓼太句集初編」
溝川や水に引かるる烏瓜 一茶「文政九年句帖
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
「蒔絵烏瓜図印籠 萬麟齊」
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k533664600
「印籠」=腰に下げる三重または五重の長円筒形の小箱。箱には蒔絵(まきえ)、堆朱(ついしゅ)、螺鈿(らでん)などの細工が施され、緒には緒締め、根付けがある。もと印判を入れたところからいい、室町頃から薬を入れるようになった。主として武士の礼装の装飾品。薬籠。印籠巾着。〔東京教育大本下学集(室町中)〕
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
※浮世草子・好色一代男(1682)七「田舎大じん印籠(ヰンラウ)あけて、いく薬かあたえけるを」(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」の、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」の、その謡曲「融(とおる)」の名調子などを吟じながら、腰に差している「蒔絵烏瓜図印籠烏瓜」を、お相手してくれる相方に、「これ、烏瓜」と、「これを見たら思い出してくれ」と、手渡すような、そんな、雰囲気の句である。
4-19 貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤
季語=蛤=蛤(はまぐり)/三春
https://kigosai.sub.jp/001/archives/849#:~:text=%E8%9B%A4%E3%81%AF%E6%98%A5%E3%80%81%E8%BA%AB%E3%81%8C,%E8%9B%A4%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E9%A3%9F%E5%8D%93%E3%81%AB%E4%B8%8A%E3%82%8B%E3%80%82
【子季語】 蛤鍋、蒸蛤、焼蛤、蛤つゆ
【解説】 蛤は春、身がふっくらと肥え、旬を迎える。二枚の貝は他のものとは決して合わないことから末永い夫婦の縁の象徴とされ、婚礼や雛の節句などの細工、貝合せなどに用いられ、平安時代には、薬入れとしても使われた。吸物、蒸し物、蛤鍋、焼蛤として食卓に上る。桑名の焼蛤、大阪の住吉神社の洲崎の洲蛤が有名。
【例句】
尻ふりて蛤ふむや南風 涼菟「喪の名残」
蛤の芥を吐かする月夜かな 一茶「七番日記」
【参考】
この句(「貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤」)は、『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』(p124~p128)で、次のとおり紹介されている。(一部抜粋)
≪『句藻』「椎の木陰」に「送笠堂主人文(りゅうどうしゅじんにおくるふみ)」という俳文に見られる。寛政八年(一七九六)秋、川越(埼玉県川越市)の瓢坊が其貝(きばい)と改名するのを祝ったのである。
「抑(そもそも)、元禄十五年長月十六日のうら遊びに、晋子(其角)が見し、雀の足をはさみし貝ならんか。此(この)貝、必(かならずしも)中に明珠(めいしゅ)を含(ふくむ)るか。此珠(このたま)、彫琢を頼ずして、光、晋流のくらきを照らすべしと祝ひ、藻に住(すむ)虫の我等迄も、五七五の一章句を申送り侍る。
貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤 (『句藻』「椎の木陰」) ≫
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇
句意(その周辺)=この句は、其角の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」(『類柑子』「浦あそび」)の本句取りの一句である。抱一は、文化三年(一八〇六)、四十六歳の時に、「其角百回忌」として、その「肖像百幅」(其角肖像画と其角の句の賛)を制作する(上記の図は、その内の一つで「夜光る画賛」のものである。これらについては、下記のアドレスの「参考」で紹介している)。
句意=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の元祖ともいうべ其角宗匠の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」を変奏して、その「必ず中に明珠を含む」縁起が良い「夜蛤」の句を、次のような一句として、それに唱和することにする。
「貝の班(ふ)の」(この貝の模様は)、「雀に似たり」(其角宗匠が目にした「雀の足を咥えた蛤」の、その「雀に似たり)、「夜蛤」(彫琢(てうたく)を頼(たよら)ずして、光(ひかり)、晋流(しんりう=其角俳諧)のくらきを照らすべし)
(参考) 「其角肖像百幅」(抱一筆・賛=其角句)周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-09-30
【(再掲)
https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22
(画像)→上記のとおり
酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇
「晋子とは其角のこと。抱一が文化三年の其角百回忌に描いた百幅のうちの一幅。新出作品。『夜光るうめのつぼみや貝の玉』(『類柑子』『五元集』)という其角の句に、略画体で其角の肖像を記した。左下には『晋子肖像百幅之弐』という印章が捺されている。書風はこの時期の抱一の書風と比較すると若干異なり、『光』など其角の奔放な書風に似せた気味がある。其角は先行する俳人肖像集で十徳という羽織や如意とともに表現されてきたが、本作はそれに倣いつつ、ユーモアを漂わせる。」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「抱一の俳諧(井田太郎稿)」)
この著者(井田太郎)が、『酒井抱一---俳諧と絵画の織りなす抒情』(岩波新書一七九八)を刊行した(以下、『井田・岩波新書』)。
この『井田・岩波新書』では、この「其角肖像百幅」について、現在知られている四幅について紹介している。
一 「仏とはさくらの花の月夜かな」が書かれたもの(伊藤松宇旧蔵。所在不明)
二 「お汁粉を還城楽(げんじょうらく)のたもとかな」同上(所在不明)
三 「夜光るうめのつぼみや貝の玉」同上(上記の図)
四 「乙鳥の塵をうごかす柳かな」同上(『井田・岩波新書』執筆中の新出)(以下略) 】
4-20 降り年や初茸売りが声の錆
季語=初茸=初茸(はつたけ)/三秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/5680#:~:text=%E8%8C%B8%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%80,%E3%81%A7%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%8C%E8%96%84%E8%8C%B6%E8%89%B2%E3%80%82
【解説】 茸のなかでも一番早く生えるのでこの名がついた。傘は扁平で全体が薄茶色。傷みやすく、傷になった部分は青く変色する。
【例句】
初茸やまだ日数経ぬ秋の露 芭蕉「小文庫」
【参考】 「初茸」周辺(「ウィキペディア」)
(歴史)
特に関東地方で親しまれ、守貞漫稿(食類-後巻之一)には「初茸売り。山のきこりや八百屋がハツタケを売る。京阪にはハツタケは無い。江戸だけで売られる。」とあり、当時の関西ではあまり人気がなかったのに対し、マツタケがほとんど産出しない江戸近辺では、食用としてよく利用されたようである。千葉県では特に珍重されたといい、旧佐倉堀田藩鹿渡村(現在の千葉県四街道市鹿渡)においては、嘉永3(1850)年庚戌年(かのえいぬ)九月十日(旧暦)付の回状として「初茸 七十ケ 右ハ御用ニテ不足無ク 来ル十三日 四ツ時迄ニ 上納致ス可シ 尤モ軸切下致シ 相納メル可ク候 此廻状 早々順達致ス可ク候 以上」の文面が発行された記録がある。(中略)
さらに、続江戸砂子(菊岡光行著:享保20年=1735年)には、「江府(=江戸)名産並近在近国」として「小金初茸・下総国葛飾郡小金之辺、所々出而発:在江府隔六里内外:在相州藤沢戸塚辺産、早産比下総:相州之産存微砂而食味下品。下総之産解砂而有風味佳品(小金初茸、下総国葛飾郡小金の辺、所々より出る。江戸より六里程。相州藤沢戸塚辺より出る初茸は、下総より早い。しかし相州産のものは微砂をふくみ、歯にさわってよくない。下総産のものは砂がなく、風味ももっとも佳い)。」との記事 がみえる。おそらくは、相模湾岸に広がるクロマツ林に産するハツタケと、内陸のアカマツ林に生えるハツタケとを比較したものではないかと思われる。
(生態・生理)
日本では、夏から秋(時に梅雨期)、アカマツ・クロマツ・リュウキュウマツ などの二針葉マツ類の樹下に発生し、これらの樹木の生きた細根に典型的な外生菌根(フォーク状に二叉分岐し、白色 または赤紫色を呈するを形成して生活する。(中略)
(ハツタケと文学)
秋の季語の一つとして知られることからも、日本人とハツタケとの関わりが深いものであることが推察される。
(例句)=一部抜粋
初茸やまだ日数 へぬ秋の露 芭蕉
初茸の無疵に出るや袂から 一茶
初茸のさび声門に秋の風 柳樽七五・8
青錆に成る初茸の旅労(つか)レ 柳樽八三・75
句意(その周辺)=「初茸」は、「初」の字がついているのだが、「新年」の季語ではなく、「古年」の「秋」の季語で、「雨の降る梅雨」明けの、特に、江戸近郊で食用される「江戸前(江戸風)の茸(きのこ)」である。その「初茸(たけ)売り」の声が、「初茸のさび声門に秋の風」(柳樽七五・8)で、夏から秋の「江戸前の風物詩」の一つとなっている。
(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html
河東節/助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)
https://www.youtube.com/watch?v=Znm06U_7WEk
「春霞 立てるやいずこ三芳野の 山口三浦うらうらと
うら若草や初花に 和らぐ土手を誰がいうて 日本めでたき国の名の
豊芦原や吉原に 根こじて植えし江戸桜
匂う夕べの風に連れ 鐘は上野か浅草か」
第九 うめの立枝(9-1~9-3) [第九 うめの立枝]
9-1 客船に入日残して時雨かな
季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2773
【子季語】 朝時雨、夕時雨、小夜時雨、村時雨、北時雨、片時雨、時雨雲、時雨傘、時雨心地、時雨の色、月時雨、松風の時雨
【解説】 冬の初め、降ったかと思うと晴れ、また降りだし、短時間で目まぐるしく変わる通り雨。この雨が徐々に自然界の色を消して行く。先人達は、さびれゆくものの中に、美しさと無常の心を養ってきた。
【例句】(芭蕉の「時雨」の句→「時雨忌」=松尾芭蕉の忌日。陰暦10月12日。時雨の多い季節であること、また芭蕉が時雨を好んで句作に用いたことにちなむ。翁忌。桃青忌。芭蕉忌)
http://chukonen.com/oboegaki/haiku/bashou052.html
旅人と我が名呼ばれん初しぐれ 笈の小文 貞享4年(1687)
初しぐれ猿も子蓑をほしげなり 猿蓑 元禄2年(1689)
けふばかり人も年よれ初時雨 真蹟短冊 元禄5年(1692)
初時雨初の字を我が時雨かな 粟津原 元禄6年(1693)
時雨をやもどかしがりて松の雪 続山井 寛文6年(1666)
一時雨礫(つぶて)や降つて小石川 俳諧江戸広小路 延宝5年(1677)
いづく霽(しぐれ)傘を手にさげて帰る僧 東日記 延宝8年(1680)
この海に草鞋(わらんじ)捨てん笠時雨 皺筥物語 天和4・貞享元年(1684)
山城へ井手の駕籠借るしぐれかな 蕉尾琴 元禄2年(1689)
作りなす庭をいさむるいさむる時雨かな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)
宿借りて名を名乗らするしぐれかな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)
馬方は知らじしぐれの大井川 泊船集 元禄4年(1691)
行く雲や犬の駆尿(かけばり)むらしぐれ 六百番俳諧発句会 延宝5年(1677)
茸狩りやあぶなきことに夕時雨 真蹟画賛 元禄2年(1689)
笠もなき我をしぐるるかこは何と あつめ句 天和4・貞享元年(1684)
草枕犬も時雨るか夜の声 野ざらし紀行 天和4・貞享元年(1684)
一尾根はしぐるる雲か富士の雪 泊船集 貞享4年(1687)
しぐるるや田の新株(あらかぶ)の黒む程 泊船集 貞享4年(1687)
「句意」(その周辺)
「第九 うめの立枝」は、『屠龍之技』の最後を飾る章(編)で、『軽挙館句藻』では、文化八年(一八一一)、抱一、五十一歳時を、そのスタートとしている。その翌年の「文化九年(一八一二)」の一月に、「杉田村へ観梅」(参考一)とあり(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)』、この「9-1 客船に入日残して時雨かな」は、この上五の「客船」の措辞から、その「杉田村観梅」時の作と思われる。
そして、この下五の「時雨」(季語)と結びつくと、『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)に、「珍らしき作意に出る師(芭蕉)の心の出所を味べし」(参考二)と評されている「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(『笈の小文』ほか)を念頭にあっての一句のように思われる。
さらに、この芭蕉の時雨の句は、『三冊子(赤冊子)』の「『よばれん初しぐれ』とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして」との「謡のはしを前書にして」の「謡」は、謡曲の「「梅枝(うめがえ)」(参考三)の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(「越天楽今様」の歌詞にある「梅枝」)を踏まえてのもののようである(『松尾芭蕉集①全発句・小学館』)。
このように解していくと、「第九 うめの立枝(たちえ)」は、「うめの立枝(たちえ)」の措辞からすると、『更科日記』の「梅の立ち枝」(参考四)などに由来があるようなのだが、その背後には、芭蕉の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」などを踏まえての、当時の、抱一の自信作の一句のように思われる。
句意は、「久しぶりに、新居の根岸の里の『鶯村(邨)亭(庵)=後の「雨華庵』から、金沢八景の北の「杉田村」(横浜市磯子区)の『観梅(梅見)』に出かけた。折から『時雨』で、その入り江の『客船』は入り日が射したり止んだりしている。それを見ていると、芭蕉の『笈の小文』の名吟、『旅人と我が名呼ばれん初しぐれ』が思い浮かんでくる。その名吟は、謡曲「梅枝(うめがえ)」の一節「越天楽今様」の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(鶯=抱一?)、「梅が枝」=小鸞女史?)を踏まえているという。その声曲が、しみじみと、今、旅心の胸中に伝わってくる。」
(参考一)「文化九年(一八一二)の抱一の『杉田村」(横浜市磯子区)観梅記』周辺
【金沢八景の北に「杉田村」(横浜市磯子区)という梅の名所があった。金沢道から杉田道に分岐する地点には、今なお其爪の「程ヶ谷(ほどがや)の枝道曲れ梅の花」という句碑を兼ねた道しるべ(文化十一年=一八一四)が建ち、抱一周辺が好んで遊覧したことをひそかに伝える。さて、文化九年(一八一二)、抱一が杉田村に観梅に赴いた一連の記事があさらにる。
む月十七日、杉田のうめ見にゆきて、森中原などゆふ村を過(すぎ)、杉田の荒井源左衛門の宅に夕餉す
解き船の橋を境や梅の花
人々、うた詠めとむ有ける時
浜風はちりくる梅を空に吹てくものひまより雪のふるなり
などし侍る。隠居善悪坊に対して、
此景色両輪の如し海と浪
八幡宮それより祇園社にまゐり、此処梅樹ことに多し
これはこれは爰をやううめのよしの山 (『軽挙館句藻』所収「梅のたち枝」) 】(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)
(参考二)『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(芭蕉『笈の小文』)周辺
http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/3zousi.html
旅人と我名呼れん初しぐれ
此句は、師、武江に旅出の日の吟也。心のいさましきを句のふりにふり出して、「よばれん初しぐれ」とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして、書のごとく章さして門人に送られし也。一風情あるもの也。この珍らしき作意に出る師の心の出所を味べし。
(参考三)「第九 うめの立枝」と謡曲「梅枝(うめがえ)」周辺
http://soxis.blog112.fc2.com/blog-category-93.html
謡曲「梅枝(うめがえ)」は、謡曲「富士太鼓」の後日談です。 富士太鼓は、伶人(雅楽演奏者)の「富士」が、ライバル「浅間」に殺害され、富士の妻が太鼓に恨みを晴らすという話。梅枝では、妻は亡霊となって登場します。
「摂津の国・住吉の里」。旅僧一行が、女(亡霊)の草庵を訪れ宿を借ります。 部屋にある太鼓と衣装に不審を抱いた僧に、女は昔を物語り、回向を頼んで消え去ります。
夜、僧の読経に、舞衣裳をつけた亡霊が現れ、夫の形見を着て太鼓を打って心を慰めたと語り、成仏を願って舞う「懺悔の舞」、そして「越天楽今様」。
しかし暁闇(あけぐれ)には、亡霊の姿も執心も消え、「面影ばかりや残るらん」。
道行はあっさりと、廻国行脚の僧が「摂津の国・住吉」に到着。「女人成仏」が主題ですから法華の僧でなくてはなりません。
これは甲斐の国身延山より出でたる僧にて候・・
いづくにも
住みは果つべき雲水(くもみず)の 住みは果つべき雲水の
身は果て知らぬ旅の空 月日ほどなく移り来て
所を問へば世を厭ふ わが衣手やすみのえ(墨・住江)の
里にも早く着きにけり 里にも早く着きにけり
「村雨」に降られ宿を求める僧を、はじめは拒んだ女ですが、受け入れれば優しい。
はやこなたへといふつゆ(言・夕露)の むぐらの宿はうれたくとも
袖を片敷きて お泊りあれや旅人(たびびと)
西北に雲起こりて 西北に雲起こりて
東南に来たる雨の足 早くに降り晴れて 月にならん嬉しや
所はすみよし(住吉・住良)の 松吹く風も心して
旅人(りょじん)の夢を覚ますなよ 旅人の夢を覚ますなよ
雨が止み、空気も澄みわたる月夜。主人公の心象風景でもある「秋」の風情がすばらしい。でもタイトルがどうして「梅枝」? 「越天楽今様」の歌詞に「梅枝」があります。今様通りに歌うのがこの曲のハイライトなのだとか。
いざさらば妄執の 雲霧を払ふ夜の 月も半ばなり
「夜半楽(やはんらく)」を奏でん・・
波もて結(ゆ)へる淡路潟 沖も静に青海(あおうみ)の
「青海波(せいがいは)」の波返し
返すや袖の折りを得て 軒端の梅に鶯の
来(き)鳴くや花の「えてんらく(枝・越天楽)」
梅が枝にこそ 鶯は巣をくへ
風吹かばいかにせん 花に宿る鶯
(梅の枝に鶯は巣を作るが、風が吹いたらどうするのだろう、鶯は)
(参考四)「第九 うめの立枝」の「うめの立枝(たちえ)」周辺
「うめの立枝(たちえ)」は、『更科日記』の「梅の立ち枝」などに由来しているのであろう。
https://shikinobi.com/sarashina-mamahaha
【 梅の立ち枝
継母なりし人は、宮仕へせしがくだりしなれば、思ひしにあらぬことどもなどありて、世の中うらめしげにて、ほかにわたるとて、五つばかりなる児どもなどして、
「あはれなりつる心のほどなむ、忘れむ世あるまじき」
などいひて、梅の木の、つま近くていと大きなるを、
「これが花の咲かむ折は来むよ」
といひおきてわたりぬるを、心の内に、恋しくあはれなりと思ひつつ、しのびねをのみ泣きて、その年もかへりぬ。いつしか梅咲かなむ、来むとありしを、さやあると、目をかけてまちわたるに、花もみな咲きぬれど、音もせず、思ひわびて、花を折りてやる。
たのめしをなほや待つべき霜がれし 梅をも春は忘れざりけり
といひやりたれば、あはれなることども書きて、
なほたのめ梅の立ち枝はちぎりおかぬ 思ひのほかの人もとふなり
もうすこしお待ちください、梅の立ち枝を見て思いがけない人がくるかもしれませんよ
(平兼盛 わがやどの梅のたちえや見えつらむ思ひのほかに君の来ませる がベース) 】
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kanemori.html
【 冷泉院御屏風の絵に、梅の花ある家にまらうど来たる所
わが宿の梅の立ち枝や見えつらむ思ひのほかに君が来ませる(平兼盛「拾遺15)」
(通釈)我が家の高く伸びた梅の枝が見えたのだろうか。思いもかけず、あなたが来てくれた。
(語釈)◇梅の立ち枝(え) 空に向かって伸びた梅の枝。「たち」には「花の香りがたつ」意が掛かる。
(補記)冷泉院(天皇在位967~969年)の御所の屏風絵。
(他出)拾遺抄、三十人撰、三十六人撰、新撰朗詠集、梁塵秘抄 】
(参考五)「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2021-07-08
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html
「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/589419
(「日野資勝」書の「詞」)
花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ
とあれば、「いと屈したりや」と笑ひたまふ。御車かくるほどに追ひて
めづらしと故里人も待ちぞ見む 花の錦を着て帰る君
(第一章 光る源氏の物語 薫物合せ 第四段 薫物合せ後の饗宴)
1.4.18 花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ
(この花の香りを素晴らしい袖に移して帰ったら、女と過ちを犯したのではないかと妻が咎
めるでしょう。)
1.4.19 とあれば、(と言うので、)
1.4.20 「 いと屈したりや」(「たいそう弱気ですな」)
1.4.21 と笑ひたまふ。 御車かくるほどに、 追ひて、(と言ってお笑いになる。お車に牛を
繋ぐところに、追いついて、)
1.4.22 めづらしと故里人も待ちぞ見む花の錦を着て帰る君 (珍しいと家の人も待ち受け
て見ましょう。この花の錦を着て帰るあなたを、)
1.4.23 またなきことと思さるらむ (めったにないこととお思いになるでしょう。)
9-2 傘はまだ時雨るゝ音や星月夜
季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬
※星月夜(ほしづきよ)=① 星の明るい晩。月が出ていないで、星だけが輝いている夜。星明りの夜。《季・秋》
※狭衣物語(1069‐77頃か)四「ほし月夜のたどたどしきに烏帽子のきと見えたるに心惑ひし給ひて」
※永久百首(1116)雑「我ひとりかまくら山を越行は星月夜こそうれしかりけれ〈肥後〉」
② 「暗」と同音の「倉」を含む「鎌倉」にかかる修飾語。主として謡曲で枕詞ふうに用い
られた。
※謡曲・調伏曾我(1480頃)「箱根詣でのおんために、明くるを待つや星月夜、鎌倉山を朝立ちて」
③ 地名「鎌倉」、あるいはそれに縁のある「鎌倉将軍」(源頼朝)、「松ガ岡」(東慶寺)などを暗示的に表わす。
※北国紀行(1487)「今もなほ星月夜こそ残るらめ寺なき谷の闇のともしび」
④ 植物「ゆうがぎく(柚香菊)」の異名。
[語誌]歌語としての初出は①の挙例「永久百首」の肥後の作で、これは意図的に珍しい語を用いたもの。しかし、「夫木和歌抄」にも採られたこの歌の影響は大きく、連歌では付合(つけあい)で「鎌倉山」に縁のあることば(寄合)となり(一条兼良「連玉合璧集」)、謡曲では②のように「鎌倉」の飾り詞として用いられるようになる。これは、平安期には珍しい歌枕のひとつにすぎなかった「鎌倉」が、頼朝登場以降は重要地名となり、寄合・飾り詞の需要が増したためでもある。(「精選版 日本国語大辞典」)
「句意」(その周辺)=謡曲「調伏曾我(ちようぶくそが)」などを背景としている一句の雰囲気もするが、ここでは、前句(9-2)の『時雨』の句と同一時の作として、「月時雨」(月の出ている時に時雨が通りすぎて行くこと。また、その時雨。《季・冬》)などの景と解したい。
句意=梅林で時雨に遭い、雨宿りをして傘の来るのを待っていたが、まだ、外は降ったり止んだりの時雨の音がしている。しかし、月までは出ていないが、闇夜に星が出てきたような気配である。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html
歌川広重「東都名所 日本橋之白雨」
https://mag.japaaan.com/archives/57976
9-3 からからと日本堤の落葉かな
季語=落葉=落葉(おちば)三冬
https://kigosai.sub.jp/?s=%E8%90%BD%E8%91%89&x=0&y=0
【子季語】 名の木落葉、落葉の雨、落葉の時雨、落葉時、落葉掃く、落葉掻く、落葉籠、落葉焚く
【解説】 晩秋から冬にかけて、落葉樹はすべて葉を落とす。散った木の葉ばかりでなく、木の葉の散る様子も地面や水面に散り敷いたようすも表わす。堆肥にしたり、焚き火にしたりする。
【例句】
宮人よ我名をちらせ落葉川 芭蕉「笈日記」
留守のまにあれたる神の落葉哉 芭蕉「芭蕉庵小文集」
百歳(ももとせ)の気色を庭の落葉哉 芭蕉「真蹟画賛」
岨(そば)行けば音空を行く落葉かな 太祗「太祗句選」
落葉して遠く成(なり)けり臼の音 蕪村「蕪村自筆句帳」
西吹けば東にたまる落ば哉 蕪村「蕪村自筆句帳」
句意(その周辺)=この句も、前々句(9-1)・前句(9-2)と同一時の作と解したい。
句意=久しぶりに遠出をして、その帰路の、新居近くの「日本堤」は、「時雨」ならず「落ち葉」が「からから」と、「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。さながら、芭蕉翁の「留守のまにあれたる神の落葉哉」の、その「神の落葉哉」の風情である。
(参考)「留守のまに荒れたる神の落葉哉」周辺
https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/rusunoma.htm
留守のまに荒れたる神の落葉哉
元禄4年10月29日、江戸に到着。元禄2年彌生も末の7日に江戸を立ってから、実に2年7ヶ月の大旅行であった。「住めるかたも人に譲り、杉風が別墅に」引っ越して旅に出たのだから、この日旧芭蕉庵には入れず、橘町の彦右衛門方借家に旅の荷を下ろす。ここが江戸最後の居となり、翌元禄7年5月11日上方に下るまでここに住むこととなった。
句意=2年7ヶ月も不在にしていた江戸で、ちょうど神無月の神が出雲から帰ってきたときのように、神社でもある自分の住まいも荒れ果てていることよ。
この「荒れたる神の落葉哉」は、抱一にとっては、≪「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。≫と、上記の「芭蕉の句」(句意)を「反転」しての一句ということになる。
季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2773
【子季語】 朝時雨、夕時雨、小夜時雨、村時雨、北時雨、片時雨、時雨雲、時雨傘、時雨心地、時雨の色、月時雨、松風の時雨
【解説】 冬の初め、降ったかと思うと晴れ、また降りだし、短時間で目まぐるしく変わる通り雨。この雨が徐々に自然界の色を消して行く。先人達は、さびれゆくものの中に、美しさと無常の心を養ってきた。
【例句】(芭蕉の「時雨」の句→「時雨忌」=松尾芭蕉の忌日。陰暦10月12日。時雨の多い季節であること、また芭蕉が時雨を好んで句作に用いたことにちなむ。翁忌。桃青忌。芭蕉忌)
http://chukonen.com/oboegaki/haiku/bashou052.html
旅人と我が名呼ばれん初しぐれ 笈の小文 貞享4年(1687)
初しぐれ猿も子蓑をほしげなり 猿蓑 元禄2年(1689)
けふばかり人も年よれ初時雨 真蹟短冊 元禄5年(1692)
初時雨初の字を我が時雨かな 粟津原 元禄6年(1693)
時雨をやもどかしがりて松の雪 続山井 寛文6年(1666)
一時雨礫(つぶて)や降つて小石川 俳諧江戸広小路 延宝5年(1677)
いづく霽(しぐれ)傘を手にさげて帰る僧 東日記 延宝8年(1680)
この海に草鞋(わらんじ)捨てん笠時雨 皺筥物語 天和4・貞享元年(1684)
山城へ井手の駕籠借るしぐれかな 蕉尾琴 元禄2年(1689)
作りなす庭をいさむるいさむる時雨かな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)
宿借りて名を名乗らするしぐれかな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)
馬方は知らじしぐれの大井川 泊船集 元禄4年(1691)
行く雲や犬の駆尿(かけばり)むらしぐれ 六百番俳諧発句会 延宝5年(1677)
茸狩りやあぶなきことに夕時雨 真蹟画賛 元禄2年(1689)
笠もなき我をしぐるるかこは何と あつめ句 天和4・貞享元年(1684)
草枕犬も時雨るか夜の声 野ざらし紀行 天和4・貞享元年(1684)
一尾根はしぐるる雲か富士の雪 泊船集 貞享4年(1687)
しぐるるや田の新株(あらかぶ)の黒む程 泊船集 貞享4年(1687)
「句意」(その周辺)
「第九 うめの立枝」は、『屠龍之技』の最後を飾る章(編)で、『軽挙館句藻』では、文化八年(一八一一)、抱一、五十一歳時を、そのスタートとしている。その翌年の「文化九年(一八一二)」の一月に、「杉田村へ観梅」(参考一)とあり(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)』、この「9-1 客船に入日残して時雨かな」は、この上五の「客船」の措辞から、その「杉田村観梅」時の作と思われる。
そして、この下五の「時雨」(季語)と結びつくと、『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)に、「珍らしき作意に出る師(芭蕉)の心の出所を味べし」(参考二)と評されている「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(『笈の小文』ほか)を念頭にあっての一句のように思われる。
さらに、この芭蕉の時雨の句は、『三冊子(赤冊子)』の「『よばれん初しぐれ』とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして」との「謡のはしを前書にして」の「謡」は、謡曲の「「梅枝(うめがえ)」(参考三)の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(「越天楽今様」の歌詞にある「梅枝」)を踏まえてのもののようである(『松尾芭蕉集①全発句・小学館』)。
このように解していくと、「第九 うめの立枝(たちえ)」は、「うめの立枝(たちえ)」の措辞からすると、『更科日記』の「梅の立ち枝」(参考四)などに由来があるようなのだが、その背後には、芭蕉の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」などを踏まえての、当時の、抱一の自信作の一句のように思われる。
句意は、「久しぶりに、新居の根岸の里の『鶯村(邨)亭(庵)=後の「雨華庵』から、金沢八景の北の「杉田村」(横浜市磯子区)の『観梅(梅見)』に出かけた。折から『時雨』で、その入り江の『客船』は入り日が射したり止んだりしている。それを見ていると、芭蕉の『笈の小文』の名吟、『旅人と我が名呼ばれん初しぐれ』が思い浮かんでくる。その名吟は、謡曲「梅枝(うめがえ)」の一節「越天楽今様」の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(鶯=抱一?)、「梅が枝」=小鸞女史?)を踏まえているという。その声曲が、しみじみと、今、旅心の胸中に伝わってくる。」
(参考一)「文化九年(一八一二)の抱一の『杉田村」(横浜市磯子区)観梅記』周辺
【金沢八景の北に「杉田村」(横浜市磯子区)という梅の名所があった。金沢道から杉田道に分岐する地点には、今なお其爪の「程ヶ谷(ほどがや)の枝道曲れ梅の花」という句碑を兼ねた道しるべ(文化十一年=一八一四)が建ち、抱一周辺が好んで遊覧したことをひそかに伝える。さて、文化九年(一八一二)、抱一が杉田村に観梅に赴いた一連の記事があさらにる。
む月十七日、杉田のうめ見にゆきて、森中原などゆふ村を過(すぎ)、杉田の荒井源左衛門の宅に夕餉す
解き船の橋を境や梅の花
人々、うた詠めとむ有ける時
浜風はちりくる梅を空に吹てくものひまより雪のふるなり
などし侍る。隠居善悪坊に対して、
此景色両輪の如し海と浪
八幡宮それより祇園社にまゐり、此処梅樹ことに多し
これはこれは爰をやううめのよしの山 (『軽挙館句藻』所収「梅のたち枝」) 】(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)
(参考二)『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(芭蕉『笈の小文』)周辺
http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/3zousi.html
旅人と我名呼れん初しぐれ
此句は、師、武江に旅出の日の吟也。心のいさましきを句のふりにふり出して、「よばれん初しぐれ」とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして、書のごとく章さして門人に送られし也。一風情あるもの也。この珍らしき作意に出る師の心の出所を味べし。
(参考三)「第九 うめの立枝」と謡曲「梅枝(うめがえ)」周辺
http://soxis.blog112.fc2.com/blog-category-93.html
謡曲「梅枝(うめがえ)」は、謡曲「富士太鼓」の後日談です。 富士太鼓は、伶人(雅楽演奏者)の「富士」が、ライバル「浅間」に殺害され、富士の妻が太鼓に恨みを晴らすという話。梅枝では、妻は亡霊となって登場します。
「摂津の国・住吉の里」。旅僧一行が、女(亡霊)の草庵を訪れ宿を借ります。 部屋にある太鼓と衣装に不審を抱いた僧に、女は昔を物語り、回向を頼んで消え去ります。
夜、僧の読経に、舞衣裳をつけた亡霊が現れ、夫の形見を着て太鼓を打って心を慰めたと語り、成仏を願って舞う「懺悔の舞」、そして「越天楽今様」。
しかし暁闇(あけぐれ)には、亡霊の姿も執心も消え、「面影ばかりや残るらん」。
道行はあっさりと、廻国行脚の僧が「摂津の国・住吉」に到着。「女人成仏」が主題ですから法華の僧でなくてはなりません。
これは甲斐の国身延山より出でたる僧にて候・・
いづくにも
住みは果つべき雲水(くもみず)の 住みは果つべき雲水の
身は果て知らぬ旅の空 月日ほどなく移り来て
所を問へば世を厭ふ わが衣手やすみのえ(墨・住江)の
里にも早く着きにけり 里にも早く着きにけり
「村雨」に降られ宿を求める僧を、はじめは拒んだ女ですが、受け入れれば優しい。
はやこなたへといふつゆ(言・夕露)の むぐらの宿はうれたくとも
袖を片敷きて お泊りあれや旅人(たびびと)
西北に雲起こりて 西北に雲起こりて
東南に来たる雨の足 早くに降り晴れて 月にならん嬉しや
所はすみよし(住吉・住良)の 松吹く風も心して
旅人(りょじん)の夢を覚ますなよ 旅人の夢を覚ますなよ
雨が止み、空気も澄みわたる月夜。主人公の心象風景でもある「秋」の風情がすばらしい。でもタイトルがどうして「梅枝」? 「越天楽今様」の歌詞に「梅枝」があります。今様通りに歌うのがこの曲のハイライトなのだとか。
いざさらば妄執の 雲霧を払ふ夜の 月も半ばなり
「夜半楽(やはんらく)」を奏でん・・
波もて結(ゆ)へる淡路潟 沖も静に青海(あおうみ)の
「青海波(せいがいは)」の波返し
返すや袖の折りを得て 軒端の梅に鶯の
来(き)鳴くや花の「えてんらく(枝・越天楽)」
梅が枝にこそ 鶯は巣をくへ
風吹かばいかにせん 花に宿る鶯
(梅の枝に鶯は巣を作るが、風が吹いたらどうするのだろう、鶯は)
(参考四)「第九 うめの立枝」の「うめの立枝(たちえ)」周辺
「うめの立枝(たちえ)」は、『更科日記』の「梅の立ち枝」などに由来しているのであろう。
https://shikinobi.com/sarashina-mamahaha
【 梅の立ち枝
継母なりし人は、宮仕へせしがくだりしなれば、思ひしにあらぬことどもなどありて、世の中うらめしげにて、ほかにわたるとて、五つばかりなる児どもなどして、
「あはれなりつる心のほどなむ、忘れむ世あるまじき」
などいひて、梅の木の、つま近くていと大きなるを、
「これが花の咲かむ折は来むよ」
といひおきてわたりぬるを、心の内に、恋しくあはれなりと思ひつつ、しのびねをのみ泣きて、その年もかへりぬ。いつしか梅咲かなむ、来むとありしを、さやあると、目をかけてまちわたるに、花もみな咲きぬれど、音もせず、思ひわびて、花を折りてやる。
たのめしをなほや待つべき霜がれし 梅をも春は忘れざりけり
といひやりたれば、あはれなることども書きて、
なほたのめ梅の立ち枝はちぎりおかぬ 思ひのほかの人もとふなり
もうすこしお待ちください、梅の立ち枝を見て思いがけない人がくるかもしれませんよ
(平兼盛 わがやどの梅のたちえや見えつらむ思ひのほかに君の来ませる がベース) 】
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kanemori.html
【 冷泉院御屏風の絵に、梅の花ある家にまらうど来たる所
わが宿の梅の立ち枝や見えつらむ思ひのほかに君が来ませる(平兼盛「拾遺15)」
(通釈)我が家の高く伸びた梅の枝が見えたのだろうか。思いもかけず、あなたが来てくれた。
(語釈)◇梅の立ち枝(え) 空に向かって伸びた梅の枝。「たち」には「花の香りがたつ」意が掛かる。
(補記)冷泉院(天皇在位967~969年)の御所の屏風絵。
(他出)拾遺抄、三十人撰、三十六人撰、新撰朗詠集、梁塵秘抄 】
(参考五)「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2021-07-08
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html
「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/589419
(「日野資勝」書の「詞」)
花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ
とあれば、「いと屈したりや」と笑ひたまふ。御車かくるほどに追ひて
めづらしと故里人も待ちぞ見む 花の錦を着て帰る君
(第一章 光る源氏の物語 薫物合せ 第四段 薫物合せ後の饗宴)
1.4.18 花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ
(この花の香りを素晴らしい袖に移して帰ったら、女と過ちを犯したのではないかと妻が咎
めるでしょう。)
1.4.19 とあれば、(と言うので、)
1.4.20 「 いと屈したりや」(「たいそう弱気ですな」)
1.4.21 と笑ひたまふ。 御車かくるほどに、 追ひて、(と言ってお笑いになる。お車に牛を
繋ぐところに、追いついて、)
1.4.22 めづらしと故里人も待ちぞ見む花の錦を着て帰る君 (珍しいと家の人も待ち受け
て見ましょう。この花の錦を着て帰るあなたを、)
1.4.23 またなきことと思さるらむ (めったにないこととお思いになるでしょう。)
9-2 傘はまだ時雨るゝ音や星月夜
季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬
※星月夜(ほしづきよ)=① 星の明るい晩。月が出ていないで、星だけが輝いている夜。星明りの夜。《季・秋》
※狭衣物語(1069‐77頃か)四「ほし月夜のたどたどしきに烏帽子のきと見えたるに心惑ひし給ひて」
※永久百首(1116)雑「我ひとりかまくら山を越行は星月夜こそうれしかりけれ〈肥後〉」
② 「暗」と同音の「倉」を含む「鎌倉」にかかる修飾語。主として謡曲で枕詞ふうに用い
られた。
※謡曲・調伏曾我(1480頃)「箱根詣でのおんために、明くるを待つや星月夜、鎌倉山を朝立ちて」
③ 地名「鎌倉」、あるいはそれに縁のある「鎌倉将軍」(源頼朝)、「松ガ岡」(東慶寺)などを暗示的に表わす。
※北国紀行(1487)「今もなほ星月夜こそ残るらめ寺なき谷の闇のともしび」
④ 植物「ゆうがぎく(柚香菊)」の異名。
[語誌]歌語としての初出は①の挙例「永久百首」の肥後の作で、これは意図的に珍しい語を用いたもの。しかし、「夫木和歌抄」にも採られたこの歌の影響は大きく、連歌では付合(つけあい)で「鎌倉山」に縁のあることば(寄合)となり(一条兼良「連玉合璧集」)、謡曲では②のように「鎌倉」の飾り詞として用いられるようになる。これは、平安期には珍しい歌枕のひとつにすぎなかった「鎌倉」が、頼朝登場以降は重要地名となり、寄合・飾り詞の需要が増したためでもある。(「精選版 日本国語大辞典」)
「句意」(その周辺)=謡曲「調伏曾我(ちようぶくそが)」などを背景としている一句の雰囲気もするが、ここでは、前句(9-2)の『時雨』の句と同一時の作として、「月時雨」(月の出ている時に時雨が通りすぎて行くこと。また、その時雨。《季・冬》)などの景と解したい。
句意=梅林で時雨に遭い、雨宿りをして傘の来るのを待っていたが、まだ、外は降ったり止んだりの時雨の音がしている。しかし、月までは出ていないが、闇夜に星が出てきたような気配である。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html
歌川広重「東都名所 日本橋之白雨」
https://mag.japaaan.com/archives/57976
9-3 からからと日本堤の落葉かな
季語=落葉=落葉(おちば)三冬
https://kigosai.sub.jp/?s=%E8%90%BD%E8%91%89&x=0&y=0
【子季語】 名の木落葉、落葉の雨、落葉の時雨、落葉時、落葉掃く、落葉掻く、落葉籠、落葉焚く
【解説】 晩秋から冬にかけて、落葉樹はすべて葉を落とす。散った木の葉ばかりでなく、木の葉の散る様子も地面や水面に散り敷いたようすも表わす。堆肥にしたり、焚き火にしたりする。
【例句】
宮人よ我名をちらせ落葉川 芭蕉「笈日記」
留守のまにあれたる神の落葉哉 芭蕉「芭蕉庵小文集」
百歳(ももとせ)の気色を庭の落葉哉 芭蕉「真蹟画賛」
岨(そば)行けば音空を行く落葉かな 太祗「太祗句選」
落葉して遠く成(なり)けり臼の音 蕪村「蕪村自筆句帳」
西吹けば東にたまる落ば哉 蕪村「蕪村自筆句帳」
句意(その周辺)=この句も、前々句(9-1)・前句(9-2)と同一時の作と解したい。
句意=久しぶりに遠出をして、その帰路の、新居近くの「日本堤」は、「時雨」ならず「落ち葉」が「からから」と、「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。さながら、芭蕉翁の「留守のまにあれたる神の落葉哉」の、その「神の落葉哉」の風情である。
(参考)「留守のまに荒れたる神の落葉哉」周辺
https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/rusunoma.htm
留守のまに荒れたる神の落葉哉
元禄4年10月29日、江戸に到着。元禄2年彌生も末の7日に江戸を立ってから、実に2年7ヶ月の大旅行であった。「住めるかたも人に譲り、杉風が別墅に」引っ越して旅に出たのだから、この日旧芭蕉庵には入れず、橘町の彦右衛門方借家に旅の荷を下ろす。ここが江戸最後の居となり、翌元禄7年5月11日上方に下るまでここに住むこととなった。
句意=2年7ヶ月も不在にしていた江戸で、ちょうど神無月の神が出雲から帰ってきたときのように、神社でもある自分の住まいも荒れ果てていることよ。
この「荒れたる神の落葉哉」は、抱一にとっては、≪「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。≫と、上記の「芭蕉の句」(句意)を「反転」しての一句ということになる。
第八 花ぬふとり(8-1~8-7) [第八 花ぬふとり]
8-1 取遣りもおかしき村の歳暮かな
季語=歳暮=歳暮(せいぼ) 暮(仲冬)
ps://kigosai.sub.jp/001/archives/17533
【子季語】 お歳暮/歳暮祝ひ/歳暮の礼/歳暮返し
【解説】 もともとは歳暮周りといって、お世話になった人にあいさつ回りをしたことに始まる。そのときの贈り物が、現在の歳暮につながるとされる。お世話になった人、会社の上司、習い事の師などに贈る。夏のお中元と同様、日本人の大切な習慣である。
【例句】
宵過の一村歩く歳暮哉 一茶(『八番日記』)
※「取遣(とりやり)」=① 取り除くこと。かたづけること。
※枕(10C終)一八四「殿まゐらせ給ふなりとて、散りたるものとりやりなどするに」
② 受け取ったり、与えたりすること。やりとり。贈答。授受。
※応永本論語抄(1420)堯曰第二〇「先王は是を乱らずして同斗量にてとりやりするなり」
③ 交際。つきあい。
※滑稽本・浮世風呂(1809‐13)前「仲間の取遣(トリヤリ)はあがったり大明神」
(「精選版 日本国語大辞典」)
「句意」(その周辺)
前書に、「己巳(きし・つちのとみ)の冬、居を藤塚といふところにうつして」とある。「己巳)」は、文化六年(一八〇九)、抱一、四十九歳の時で、「根岸の金杉村に転居、以後、定住」(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)と、この「藤塚」は、「根岸の金杉村」の地名のようである。
明けて文化七年(一八一〇)の正月に、この根岸の里の転居先に、吉原・大文字屋の遊女といわれる「小鸞(しょうらん)」女史を身請けして、二人の新居生活がスタートとする。その二人の合作が、下記のアドレスで紹介した「紅梅図(墨梅図)」(抱一画・小鸞書)である。
小鸞女史は、「遊女名=香川、書を中井董堂に習い、茶の湯、俳諧、河東節の三味線を嗜み、文化十四年(一八一七)に剃髪し、妙華(みょうけ)尼と名乗る」(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。
句意は、「長い遷住(放浪)生活に見切りをつけて、ここ『根岸の郷(里)』で、小鸞女史と、二人の新居生活をスタートする、その暮れの『歳暮』(歳暮周り・歳暮受け)の、この『根岸金杉村』の『取遣り』(しきたり)は、これがまた、まことに『お(を)かしき』(風変わりで、風情がある)ことであるよ。」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-09-01
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝
【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。
小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(1837)に没するまで、抱一亡き後の雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。
本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。
抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。
「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。
梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。
「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。
(賛)
「竹斎」(朱文楕円印)
行過野逕渡渓橋
踏雪相求不憚労
何處蔵春々不見惟
聞風裡暗香瓢
小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】
(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)
(参考)「第八 花ぬふとり」の「花ぬふとり」周辺
「花に明(あ)かぬ嘆きや我が歌袋」(いが上野松尾宗房=芭蕉『続山の井』)
寛文七年(一六六七)、芭蕉、二十七歳時の作である。この句は、『伊勢物語29段:花の賀』の「花に飽かぬ嘆きはいつもせしかどもけふの今宵に似る時はなし」(在原業平)をパロディー化したものである。
句意は、「在原業平は、『花に飽かぬ』と嘆いたが、私は花があっても、私の歌袋が「明かない=開かない」ばかりで、歌が一首も出てきません」というよう意であろう。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
伊勢物語絵巻廿九段(花の賀)
https://ise-monogatari.hix05.com/2/ise-029.html
【 むかし、春宮の女御の御方の花の賀に、召しあづけられたりけるに、
花にあかぬ嘆きはいつもせしかども今日のこよひに似る時はなし
(文の現代語訳)
昔、春宮の(母上の)女御の御殿で催された花の賀に、御呼び出しにあずかったある男が読んだ歌、
花を見るたびに見飽きることのないという嘆きを覚えますが、今日の今宵は格別です
(文の解説)
春宮の女御:皇太子の母上、ここでは、後に陽成天皇になった皇太子貞明親王の母である藤原高子をさす、春宮は「とうぐう」とよみ、皇太子のこと、●召しあづけられ:お召しにあずかり、●花の賀:桜の花を見ながら行われる長寿の祝、●あかぬ:飽きない
(絵の解説)
御殿の中では大勢の人々が集まり、庭には桜の花が咲き誇っている様子が描かれている。
(付記)
この段では、誰が歌を歌ったかは明示していないが、若い頃の藤原高子と業平との間を知っている者には、これが業平であることは明らかだ。かつて、愛した人とともに眺める桜はひとしおです、といっているわけである。 】
8-2 節季候(せきぞろ)は百轉(囀=てん・でん・さえずり)のはじめかな
季語=節季候=節季候(せきぞろ) 暮(仲冬)
https://kigosai.sub.jp/001/archives/17531
【子季語】 せつきぞろ/胸叩/姥等
【解説】 年が押しつまったころにくる門付け芸人。笠の上に羊歯の葉をさし、赤い布で顔を覆って「せきぞろ、めでたい」などとと叫びながら年越しの銭を乞うた。割竹で胸をたたいたので胸叩とも呼ばれた。乞食のようなもので、凶作の時代に多く出たという。
【例句】
おどろけや念仏衆生節季候 宗因「釈教百韻]
節季候や臼こかし来て間がぬける 鬼貫「荒小田」
気にむかぬ時もあるらん節季候 来山「難波の枝折」
節季候の来れば風雅も師走かな 芭蕉「勧進牒」
節気候を雀の笑ふ出立かな 芭蕉「深川」
気候や顔つつましき小風ろ敷 蕪村「落日庵句集」
小藪から小藪蔭がくれやせつき候 一茶「九番目記」
https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E4%B8%89%E5%86%8A%E5%AD%90-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%95%E3%81%86%E3%81%97/
【「節季候のくれバ風雅も師走哉
此句、風雅も師走哉、と俗とひとつに侍る。是先師の心也。人の句に、藏やけて、と云句有。とぶ蝶の羽音やかまし、といふ句あり。高くいひて甚心俗也。味べし。」(『去来抄・三冊子・旅寝論』潁原退蔵校訂、一九三九、岩波文庫p.108)
句は元禄四年刊路通編の『俳諧勧進牒』で、
果ての朔日の朝から
節季候の来れば風雅も師走哉 芭蕉
元禄三年十二月一日の句と思われる。
節季候(せきぞろ)はコトバンクの「精選版 日本国語大辞典の解説」に、
「〘名〙 江戸時代、歳末の門付けの一種。一二月の初めから二七、八日ごろまで、羊歯(しだ)の葉を挿した笠をかぶり、赤い布で顔をおおって目だけを出し、割り竹をたたきながら二、三人で組になって町家にはいり、「ああ節季候節季候、めでたいめでたい」と唱えて囃(はや)して歩き、米銭をもらってまわったもの。せっきぞろ。《季・冬》 〔俳諧・誹諧初学抄(1641)〕」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
「節句候」(「精選版 日本国語大辞典の解説」) 】
「句意」(その周辺)
前句の「8-1 取遣りもおかしき村の歳暮かな」と同時の作であろう。
句意=歳末・年始の風物詩の「節句候」が我が新居にもやってきた。芭蕉翁は、「節季候の来れば風雅も師走哉」と何やら皮肉めいた句を遺しているが、これは、これ、「節季候は百轉(囀)のはじめかな」で、新しい年に一斉に鳴く小鳥たちの百囀(てん=さえずり)の始めの、まさに、風雅の師走(終わり)ではなく、年始(始め)を告げるお囃子であることよ。
8-3 元日の朝寝起すや小田の鶴
季語=元日=元日(がんじつ、ぐわんじつ) 新年
https://kigosai.sub.jp/001/
【子季語】 お元日、元旦、元朝、大旦、日の始、初旦、鶏旦、朔旦、歳旦、元三、三の始、年の朝
【関連季語】 初春、若水、門松、鏡餅、雑煮、屠蘇
【解説】 一月一日。一年の始めの日である。門松や鏡餅を飾り、屠蘇を酌み、雑煮を食べてこの日を祝う。旧暦では立春の前後にめぐってきたが、新暦では冬のさなか。元旦は元日の朝のこと。
【来歴】 『俳諧初学抄』(寛永18年、1641年)に所出。
【文学での言及】
あら玉の年たちかへるあしたより待たるゝものは鶯の声 素性法師『拾遺集』
【例句】
元日やおもへばさびし秋の暮 芭蕉「真蹟短冊」
元日は田ごとの日こそ恋しけれ 芭蕉「橋守」
元日や晴れてすゞめのものがたり 嵐雪「其袋」
元日や何やら人のしたり皃 春来「俳諧新選」
※小田(おだ・をだ)=〘名〙 (「お」は接頭語) 田。たんぼ。
※万葉(8C後)七・一一一〇「斉種(ゆたね)蒔く新墾(あらき)の小田(をだ)を求めむと足結(あゆひ)出で濡れぬこの川の瀬に」(「精選版 日本国語大辞典」)
句意=新しい年の「元日」の朝に、その寝覚めを起こすかのように、この根岸の新居を取り巻く「小田」(田んぼ)」には、新年の鶴がたむろして鳴いている。我らの「東風流(あずまぶり)」(「都市=江戸」風の蕉門俳諧)の、その源流の芭蕉翁は、「元日は田ごとの日こそ恋しけれ」と、「更科紀行」での「田ごとの月」を、「田ごとの日(新年の初日と日々)」と反転しているが、ここは、「東風流」の祖(先々師「(馬場)存義)」の師)の「(前田)春来」の「元日や何やら人のしたり皃(かお)」に倣い、「したりがお(顔)」の一句を吟ずることにする。
(参考)「江戸座俳諧」の「東風流(あずまぶり)」(「都会=江戸」風の蕉門俳諧)の系譜
松尾芭蕉→宝井(榎本)其角=服部嵐雪
↓
(「江戸座俳諧」の「東風流(あずまぶり)」
前田春来(二世青峨)→馬場存義(有無庵)→柳沢米翁(大名俳人・抱一の師)→佐藤晩得(米翁の知己・抱一の師)→酒井抱一
悼米翁老君
聡き人耳なし山や呼子鳥 (第一 こがねのこま)
船頭も象と成けり夏まつり (同上)
存義先師七七回忌
ふるふると鳴て千鳥の磯めぐり (第五 千づかのいね)
雪おれの雀ありけり園の竹 (同上)
雪の夜や雪車に引せん三布団 (同上)
【 柳沢 信鴻(やなぎさわ のぶとき)は、江戸時代中期の大名。大和国郡山藩第2代藩主。郡山藩柳沢家3代。初代藩主柳沢吉里の四男。
時代 江戸時代中期
生誕 享保9年10月29日(1724年12月14日)
死没 寛政4年3月3日(1792年4月23日)
別名 久菊、義稠、信卿、伊信
諡号 米翁、春来、香山、月村、蘇明山、紫子庵、伯鸞
戒名 即仏心院無誉祐阿香山大居士
墓所 東京都新宿区 正覚山月桂寺
幕府 江戸幕府
藩 郡山藩主
氏族 柳沢氏
父母 父:柳沢吉里、母:森氏
兄弟 信睦、時英、信鴻、信昌、伊奈忠敬、坪内定規
妻 正室:伊達村年の娘 継室:真田信弘の娘
子 保光、信復(次男)、武田信明、六角広寿(四男)、里之、
娘(米倉昌賢正室)、娘(阿部正倫正室) 】(「ウィキペディア」)
【 前田春来(二世青峨) 1698-1759 江戸時代中期の俳人。
元禄(げんろく)11年生まれ。江戸の人。鴛田(おしだ)青峨の門人で2代青峨をつぐ。宝暦6年江戸俳諧(はいかい)の伝統の誇示と古風の復活をはかって「東風流(あずまぶり)」を編集,刊行した。宝暦9年4月16日死去。62歳。別号に春来,紫子庵。 】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
【 馬場存義(ばば ぞんぎ) 1703-1782 江戸時代中期の俳人。
元禄(げんろく)16年3月15日生まれ。2代前田青峨にまなぶ。享保(きょうほう)19年俳諧(はいかい)宗匠となり,存義側をひきいて江戸座の代表的点者として活躍した。与謝蕪村(よさ-ぶそん)とも交友があった。天明2年10月30日死去。80歳。江戸出身。別号に泰里(たいり),李井庵,有無庵,古来庵。編著に「遠つくば」「古来庵句集」など。】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
【 佐藤晩得 (さとう-ばんとく) 1731-1792 江戸時代中期-後期の俳人。
享保(きょうほう)16年生まれ。出羽(でわ)久保田藩(秋田県)の江戸留守居役。馬場存義(そんぎ)の門人で酒井抱一としたしく,西山宗因風をこのんだ。遺句集に「哲阿弥(てつあみ)句藻」,随筆に「古事記布倶路(ぶくろ)」。寛政4年10月18日死去。62歳。名は祐英。通称は又兵衛。別号に哲阿弥,木雁,北斎,朝四など。 】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
8-4 うめ守に硯借れば筆もなし
季語=うめ守=梅(初春)
※参考季語:花守=花守(はなもり) 晩春
https://kigosai.sub.jp/001/archives/9920
【子季語】 花の主/花のあるじ/桜守
【解説】 寺や庭園、山野等の桜の木の手入れをしたり、番をしたりする人。和歌から派生した季語である。
【例句】
一里はみな花守の子孫かや 芭蕉「猿蓑」
花守や白きかしらをつき合はせ 去来「薦獅子」
花守の身は弓矢なきかがしかな 蕪村「続一夜松後集」
花守のあづかり船や岸の月 太祇「太祇句選」
句意=「花守」ならず「梅守」に、一句を書き留めようと、硯を借りて、さて「一筆」と思ったら、肝心要の「筆」もない。蛇足=「うめ守」は、「梅守」(梅・梅林の管理)に没頭していて、「硯・筆」(「風雅」=俳諧など)には、とんと、気がまわらない。
上記の例句の「花守の身は弓矢なきかがしかな(蕪村)」の、「花守」(花の番人=風雅の道の護持者=「花咲翁」=松永貞徳)と関連させる句意もあろう。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
抱一筆『集外三十六歌仙図画帖』所収「三十六 松永貞徳」(姫路市立美術館蔵)
https://jmapps.ne.jp/hmgsbj/det.html?data_id=1506
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-20
【松永貞徳(まつながていとく) [生]元亀2(1571).京都 [没]承応2(1653).11.15. 京都
江戸時代前期の俳人,歌人,歌学者。名,勝熊。別号,逍遊軒,長頭丸,延陀丸,花咲の翁など。連歌師の子として生れ,九条稙通 (たねみち) ,細川幽斎らから和歌,歌学などを,里村紹巴から連歌を学び,一時豊臣秀吉の祐筆となった。貞門俳諧の指導者として,俳諧を全国的に普及させた功績は大きく,松江重頼,野々口立圃,安原貞室,山本西武 (さいむ) ,鶏冠井 (かえでい) 令徳,高瀬梅盛,北村季吟のいわゆる七俳仙をはじめ多数の門人を全国に擁した。
歌人としては木下長嘯子とともに地下 (じげ) 歌壇の双璧をなし,門下に北村季吟,加藤磐斎,和田以悦,望月長好,深草元政,山本春正らがいる。狂歌作者としても一流であった。俳書に『新増犬筑波集』 (1643) ,『御傘 (ごさん) 』,『紅梅千句』 (55) ,歌集に『逍遊愚抄』 (77) ,歌学書に『九六古新注』 (70) ,『堀川百首肝要抄』 (84) ,狂歌書に『貞徳百首狂歌』 (36成立) などがある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について】
8-5 山陰の梅まだ寒し活大根(いけだいこ)
季語=梅(初春)
※「活大根」=いけ‐だいこん(生大根・埋大根)
【〘名〙 (「いけ」は生かす、埋める意の「いける」から)
① 畑から引き抜いたままの大根を地中に深くうずめて、翌年の春まで貯蔵し、食用とするもの。いけだいこ。《季・冬》
※俳諧・笈日記(1695)中「寒菊の隣もありやいけ大根〈許六〉」
② 大根の栽培品種で、根が地上に出ないで、深く地中に隠れているもの。二、三月頃に収穫する。かつて京都付近で多く栽培された。《季・春》
※俳諧・骨書(1787)下「かくれ家や花咲かかるいけ大根〈鶴市〉」】(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=この句は、「梅」の句なのか、それとも「活大根(いけだいこ)」の句なのか? この「活大根」は、「いけ(活け)だいこ」(春)なのか、それとも、「いけ(埋け)だいこ」(冬)なのか?
この疑問には、この句が、「第八 花ぬふとり」の、冒頭(8-1)から五番目で掲載されていて、これに続く七番目(8-7)の句まで、冒頭(8-1)の前書の「己巳(きし・つちのとみ)の冬、居を藤塚といふところにうつして」が掛かる一群の、新居を構えた「根岸の郷(里)」の「歳暮・元日・梅」の句で、これは、「8-4から8-7」の三句続きの「梅」(初春)の句と解したい。同様に、この「活大根」は、「いけ(活け)だいこ」の「春採り大根」(初春)ということになる。
句意=「山陰(やまかげ)」の「梅」の花は、「まだ、寒さ」で、その傍らの、春採りの「「活大根(いけだいこ)」のように、間もなく来る「春の暖かさ」を待っている。
8-6 うぐゐすや梅に氷れる枝もなし
季語=「うぐゐす=鶯」(三春)と「梅」(初春)
https://fukusaisin.com/3842.html
立春の期間は2月4日頃~次の雨水に至る前日2月18日頃までを指します。
□ 初候 2月 4日頃 ~ 8日頃 … 東風解凍 … はるかぜこほりをとく
□ 次候 2月 9日頃 ~13日頃 … 黄鶯睍睆 … うぐひすなく
□ 末候 2月14日頃 ~18日頃 … 魚上氷 … うをこほりをいづる
句意(その周辺)=この「根岸の郷(里)」の「梅林」にも「鶯」が一斉に鳴いている。「東風解凍(はるかぜこほりをとく)」、そして、「黄鶯睍睆(うぐひすなく)」、さらに、「魚上氷(うをこほりをいづる)」と、見事な梅の季節となった。
8-7 梅を縫ふ糸ならなくに春の雨
季語=「梅」(初春)、そして、「春の雨(春雨))(三春)。
句意(その周辺)=「梅を縫ふ糸」とは、「第八 花(梅)ぬふ(縫う)とり(鶯)」のイメージ(雰囲気)の、その「鶯」)に解したい。そして、「糸(鶯)ならなくに春の雨」のイメージは、その「鶯」ではなく、「春の雨(春雨)」こそ、「梅を縫ふ(梅の花を開く)糸(その源)」なのである。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-06-18
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
酒井抱一筆「四季花鳥図屏風(右隻)」六曲一双 陽明文庫蔵 文化十三年(一八一六)
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
酒井抱一筆「四季花鳥図屏風(左隻)」六曲一双 陽明文庫蔵 文化十三年(一八一六)
【 右隻の右から平坦な土坡に、春草のさまざま、蕨や菫や蒲公英、土筆、桜草、蓮華層などをちりばめ、雌雄の雲雀が上下に呼応する。続いて夏の花、牡丹、鬼百合、紫陽花、立葵、撫子、下の方には河骨、沢瀉、燕子花に、やはり白鷺が二羽向き合い、水鶏も隠れている。左隻には、秋の竜胆、桔梗、薄、女郎花、漆、葛、篠竹に、雉と鴫がいる。冬は水仙、白梅に鶯、榛(はん)の木、藪柑子である。
モチーフはそれぞれ明確に輪郭をとり厚く平たく塗り分け、ここで完璧な型づくりが為されたといっていいだろう。光琳百回忌から一年、濃彩で豪華な大作としては絵馬や仏画などを除いて早い一例となる。淡い彩色や墨を多用してきた抱一としては大変な飛躍であり、後の作画に内外に大きな影響を及ぼしたことが想像される。
本図は、昭和二年の抱一百年忌の展観に出品され、当時は、金融界の風雲児といわれた実業家で、浮世絵風俗画の収集でも知られる神田鐳蔵の所蔵であった。その前後、大正から昭和初めにかけて、さまざまな所蔵家のもとを変転したことが入札目録よりわかるが、それ以前の情報として、新出の田中抱二資料の嘉永元年(一八四八)の「写真」に、本図の縮図が見出されたことを報告しておく。 】
(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍社)』所収「作品解説(松尾知子稿))
季語=歳暮=歳暮(せいぼ) 暮(仲冬)
ps://kigosai.sub.jp/001/archives/17533
【子季語】 お歳暮/歳暮祝ひ/歳暮の礼/歳暮返し
【解説】 もともとは歳暮周りといって、お世話になった人にあいさつ回りをしたことに始まる。そのときの贈り物が、現在の歳暮につながるとされる。お世話になった人、会社の上司、習い事の師などに贈る。夏のお中元と同様、日本人の大切な習慣である。
【例句】
宵過の一村歩く歳暮哉 一茶(『八番日記』)
※「取遣(とりやり)」=① 取り除くこと。かたづけること。
※枕(10C終)一八四「殿まゐらせ給ふなりとて、散りたるものとりやりなどするに」
② 受け取ったり、与えたりすること。やりとり。贈答。授受。
※応永本論語抄(1420)堯曰第二〇「先王は是を乱らずして同斗量にてとりやりするなり」
③ 交際。つきあい。
※滑稽本・浮世風呂(1809‐13)前「仲間の取遣(トリヤリ)はあがったり大明神」
(「精選版 日本国語大辞典」)
「句意」(その周辺)
前書に、「己巳(きし・つちのとみ)の冬、居を藤塚といふところにうつして」とある。「己巳)」は、文化六年(一八〇九)、抱一、四十九歳の時で、「根岸の金杉村に転居、以後、定住」(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)と、この「藤塚」は、「根岸の金杉村」の地名のようである。
明けて文化七年(一八一〇)の正月に、この根岸の里の転居先に、吉原・大文字屋の遊女といわれる「小鸞(しょうらん)」女史を身請けして、二人の新居生活がスタートとする。その二人の合作が、下記のアドレスで紹介した「紅梅図(墨梅図)」(抱一画・小鸞書)である。
小鸞女史は、「遊女名=香川、書を中井董堂に習い、茶の湯、俳諧、河東節の三味線を嗜み、文化十四年(一八一七)に剃髪し、妙華(みょうけ)尼と名乗る」(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。
句意は、「長い遷住(放浪)生活に見切りをつけて、ここ『根岸の郷(里)』で、小鸞女史と、二人の新居生活をスタートする、その暮れの『歳暮』(歳暮周り・歳暮受け)の、この『根岸金杉村』の『取遣り』(しきたり)は、これがまた、まことに『お(を)かしき』(風変わりで、風情がある)ことであるよ。」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-09-01
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝
【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。
小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(1837)に没するまで、抱一亡き後の雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。
本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。
抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。
「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。
梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。
「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。
(賛)
「竹斎」(朱文楕円印)
行過野逕渡渓橋
踏雪相求不憚労
何處蔵春々不見惟
聞風裡暗香瓢
小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】
(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)
(参考)「第八 花ぬふとり」の「花ぬふとり」周辺
「花に明(あ)かぬ嘆きや我が歌袋」(いが上野松尾宗房=芭蕉『続山の井』)
寛文七年(一六六七)、芭蕉、二十七歳時の作である。この句は、『伊勢物語29段:花の賀』の「花に飽かぬ嘆きはいつもせしかどもけふの今宵に似る時はなし」(在原業平)をパロディー化したものである。
句意は、「在原業平は、『花に飽かぬ』と嘆いたが、私は花があっても、私の歌袋が「明かない=開かない」ばかりで、歌が一首も出てきません」というよう意であろう。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
伊勢物語絵巻廿九段(花の賀)
https://ise-monogatari.hix05.com/2/ise-029.html
【 むかし、春宮の女御の御方の花の賀に、召しあづけられたりけるに、
花にあかぬ嘆きはいつもせしかども今日のこよひに似る時はなし
(文の現代語訳)
昔、春宮の(母上の)女御の御殿で催された花の賀に、御呼び出しにあずかったある男が読んだ歌、
花を見るたびに見飽きることのないという嘆きを覚えますが、今日の今宵は格別です
(文の解説)
春宮の女御:皇太子の母上、ここでは、後に陽成天皇になった皇太子貞明親王の母である藤原高子をさす、春宮は「とうぐう」とよみ、皇太子のこと、●召しあづけられ:お召しにあずかり、●花の賀:桜の花を見ながら行われる長寿の祝、●あかぬ:飽きない
(絵の解説)
御殿の中では大勢の人々が集まり、庭には桜の花が咲き誇っている様子が描かれている。
(付記)
この段では、誰が歌を歌ったかは明示していないが、若い頃の藤原高子と業平との間を知っている者には、これが業平であることは明らかだ。かつて、愛した人とともに眺める桜はひとしおです、といっているわけである。 】
8-2 節季候(せきぞろ)は百轉(囀=てん・でん・さえずり)のはじめかな
季語=節季候=節季候(せきぞろ) 暮(仲冬)
https://kigosai.sub.jp/001/archives/17531
【子季語】 せつきぞろ/胸叩/姥等
【解説】 年が押しつまったころにくる門付け芸人。笠の上に羊歯の葉をさし、赤い布で顔を覆って「せきぞろ、めでたい」などとと叫びながら年越しの銭を乞うた。割竹で胸をたたいたので胸叩とも呼ばれた。乞食のようなもので、凶作の時代に多く出たという。
【例句】
おどろけや念仏衆生節季候 宗因「釈教百韻]
節季候や臼こかし来て間がぬける 鬼貫「荒小田」
気にむかぬ時もあるらん節季候 来山「難波の枝折」
節季候の来れば風雅も師走かな 芭蕉「勧進牒」
節気候を雀の笑ふ出立かな 芭蕉「深川」
気候や顔つつましき小風ろ敷 蕪村「落日庵句集」
小藪から小藪蔭がくれやせつき候 一茶「九番目記」
https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E4%B8%89%E5%86%8A%E5%AD%90-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%95%E3%81%86%E3%81%97/
【「節季候のくれバ風雅も師走哉
此句、風雅も師走哉、と俗とひとつに侍る。是先師の心也。人の句に、藏やけて、と云句有。とぶ蝶の羽音やかまし、といふ句あり。高くいひて甚心俗也。味べし。」(『去来抄・三冊子・旅寝論』潁原退蔵校訂、一九三九、岩波文庫p.108)
句は元禄四年刊路通編の『俳諧勧進牒』で、
果ての朔日の朝から
節季候の来れば風雅も師走哉 芭蕉
元禄三年十二月一日の句と思われる。
節季候(せきぞろ)はコトバンクの「精選版 日本国語大辞典の解説」に、
「〘名〙 江戸時代、歳末の門付けの一種。一二月の初めから二七、八日ごろまで、羊歯(しだ)の葉を挿した笠をかぶり、赤い布で顔をおおって目だけを出し、割り竹をたたきながら二、三人で組になって町家にはいり、「ああ節季候節季候、めでたいめでたい」と唱えて囃(はや)して歩き、米銭をもらってまわったもの。せっきぞろ。《季・冬》 〔俳諧・誹諧初学抄(1641)〕」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
「節句候」(「精選版 日本国語大辞典の解説」) 】
「句意」(その周辺)
前句の「8-1 取遣りもおかしき村の歳暮かな」と同時の作であろう。
句意=歳末・年始の風物詩の「節句候」が我が新居にもやってきた。芭蕉翁は、「節季候の来れば風雅も師走哉」と何やら皮肉めいた句を遺しているが、これは、これ、「節季候は百轉(囀)のはじめかな」で、新しい年に一斉に鳴く小鳥たちの百囀(てん=さえずり)の始めの、まさに、風雅の師走(終わり)ではなく、年始(始め)を告げるお囃子であることよ。
8-3 元日の朝寝起すや小田の鶴
季語=元日=元日(がんじつ、ぐわんじつ) 新年
https://kigosai.sub.jp/001/
【子季語】 お元日、元旦、元朝、大旦、日の始、初旦、鶏旦、朔旦、歳旦、元三、三の始、年の朝
【関連季語】 初春、若水、門松、鏡餅、雑煮、屠蘇
【解説】 一月一日。一年の始めの日である。門松や鏡餅を飾り、屠蘇を酌み、雑煮を食べてこの日を祝う。旧暦では立春の前後にめぐってきたが、新暦では冬のさなか。元旦は元日の朝のこと。
【来歴】 『俳諧初学抄』(寛永18年、1641年)に所出。
【文学での言及】
あら玉の年たちかへるあしたより待たるゝものは鶯の声 素性法師『拾遺集』
【例句】
元日やおもへばさびし秋の暮 芭蕉「真蹟短冊」
元日は田ごとの日こそ恋しけれ 芭蕉「橋守」
元日や晴れてすゞめのものがたり 嵐雪「其袋」
元日や何やら人のしたり皃 春来「俳諧新選」
※小田(おだ・をだ)=〘名〙 (「お」は接頭語) 田。たんぼ。
※万葉(8C後)七・一一一〇「斉種(ゆたね)蒔く新墾(あらき)の小田(をだ)を求めむと足結(あゆひ)出で濡れぬこの川の瀬に」(「精選版 日本国語大辞典」)
句意=新しい年の「元日」の朝に、その寝覚めを起こすかのように、この根岸の新居を取り巻く「小田」(田んぼ)」には、新年の鶴がたむろして鳴いている。我らの「東風流(あずまぶり)」(「都市=江戸」風の蕉門俳諧)の、その源流の芭蕉翁は、「元日は田ごとの日こそ恋しけれ」と、「更科紀行」での「田ごとの月」を、「田ごとの日(新年の初日と日々)」と反転しているが、ここは、「東風流」の祖(先々師「(馬場)存義)」の師)の「(前田)春来」の「元日や何やら人のしたり皃(かお)」に倣い、「したりがお(顔)」の一句を吟ずることにする。
(参考)「江戸座俳諧」の「東風流(あずまぶり)」(「都会=江戸」風の蕉門俳諧)の系譜
松尾芭蕉→宝井(榎本)其角=服部嵐雪
↓
(「江戸座俳諧」の「東風流(あずまぶり)」
前田春来(二世青峨)→馬場存義(有無庵)→柳沢米翁(大名俳人・抱一の師)→佐藤晩得(米翁の知己・抱一の師)→酒井抱一
悼米翁老君
聡き人耳なし山や呼子鳥 (第一 こがねのこま)
船頭も象と成けり夏まつり (同上)
存義先師七七回忌
ふるふると鳴て千鳥の磯めぐり (第五 千づかのいね)
雪おれの雀ありけり園の竹 (同上)
雪の夜や雪車に引せん三布団 (同上)
【 柳沢 信鴻(やなぎさわ のぶとき)は、江戸時代中期の大名。大和国郡山藩第2代藩主。郡山藩柳沢家3代。初代藩主柳沢吉里の四男。
時代 江戸時代中期
生誕 享保9年10月29日(1724年12月14日)
死没 寛政4年3月3日(1792年4月23日)
別名 久菊、義稠、信卿、伊信
諡号 米翁、春来、香山、月村、蘇明山、紫子庵、伯鸞
戒名 即仏心院無誉祐阿香山大居士
墓所 東京都新宿区 正覚山月桂寺
幕府 江戸幕府
藩 郡山藩主
氏族 柳沢氏
父母 父:柳沢吉里、母:森氏
兄弟 信睦、時英、信鴻、信昌、伊奈忠敬、坪内定規
妻 正室:伊達村年の娘 継室:真田信弘の娘
子 保光、信復(次男)、武田信明、六角広寿(四男)、里之、
娘(米倉昌賢正室)、娘(阿部正倫正室) 】(「ウィキペディア」)
【 前田春来(二世青峨) 1698-1759 江戸時代中期の俳人。
元禄(げんろく)11年生まれ。江戸の人。鴛田(おしだ)青峨の門人で2代青峨をつぐ。宝暦6年江戸俳諧(はいかい)の伝統の誇示と古風の復活をはかって「東風流(あずまぶり)」を編集,刊行した。宝暦9年4月16日死去。62歳。別号に春来,紫子庵。 】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
【 馬場存義(ばば ぞんぎ) 1703-1782 江戸時代中期の俳人。
元禄(げんろく)16年3月15日生まれ。2代前田青峨にまなぶ。享保(きょうほう)19年俳諧(はいかい)宗匠となり,存義側をひきいて江戸座の代表的点者として活躍した。与謝蕪村(よさ-ぶそん)とも交友があった。天明2年10月30日死去。80歳。江戸出身。別号に泰里(たいり),李井庵,有無庵,古来庵。編著に「遠つくば」「古来庵句集」など。】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
【 佐藤晩得 (さとう-ばんとく) 1731-1792 江戸時代中期-後期の俳人。
享保(きょうほう)16年生まれ。出羽(でわ)久保田藩(秋田県)の江戸留守居役。馬場存義(そんぎ)の門人で酒井抱一としたしく,西山宗因風をこのんだ。遺句集に「哲阿弥(てつあみ)句藻」,随筆に「古事記布倶路(ぶくろ)」。寛政4年10月18日死去。62歳。名は祐英。通称は又兵衛。別号に哲阿弥,木雁,北斎,朝四など。 】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
8-4 うめ守に硯借れば筆もなし
季語=うめ守=梅(初春)
※参考季語:花守=花守(はなもり) 晩春
https://kigosai.sub.jp/001/archives/9920
【子季語】 花の主/花のあるじ/桜守
【解説】 寺や庭園、山野等の桜の木の手入れをしたり、番をしたりする人。和歌から派生した季語である。
【例句】
一里はみな花守の子孫かや 芭蕉「猿蓑」
花守や白きかしらをつき合はせ 去来「薦獅子」
花守の身は弓矢なきかがしかな 蕪村「続一夜松後集」
花守のあづかり船や岸の月 太祇「太祇句選」
句意=「花守」ならず「梅守」に、一句を書き留めようと、硯を借りて、さて「一筆」と思ったら、肝心要の「筆」もない。蛇足=「うめ守」は、「梅守」(梅・梅林の管理)に没頭していて、「硯・筆」(「風雅」=俳諧など)には、とんと、気がまわらない。
上記の例句の「花守の身は弓矢なきかがしかな(蕪村)」の、「花守」(花の番人=風雅の道の護持者=「花咲翁」=松永貞徳)と関連させる句意もあろう。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
抱一筆『集外三十六歌仙図画帖』所収「三十六 松永貞徳」(姫路市立美術館蔵)
https://jmapps.ne.jp/hmgsbj/det.html?data_id=1506
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-20
【松永貞徳(まつながていとく) [生]元亀2(1571).京都 [没]承応2(1653).11.15. 京都
江戸時代前期の俳人,歌人,歌学者。名,勝熊。別号,逍遊軒,長頭丸,延陀丸,花咲の翁など。連歌師の子として生れ,九条稙通 (たねみち) ,細川幽斎らから和歌,歌学などを,里村紹巴から連歌を学び,一時豊臣秀吉の祐筆となった。貞門俳諧の指導者として,俳諧を全国的に普及させた功績は大きく,松江重頼,野々口立圃,安原貞室,山本西武 (さいむ) ,鶏冠井 (かえでい) 令徳,高瀬梅盛,北村季吟のいわゆる七俳仙をはじめ多数の門人を全国に擁した。
歌人としては木下長嘯子とともに地下 (じげ) 歌壇の双璧をなし,門下に北村季吟,加藤磐斎,和田以悦,望月長好,深草元政,山本春正らがいる。狂歌作者としても一流であった。俳書に『新増犬筑波集』 (1643) ,『御傘 (ごさん) 』,『紅梅千句』 (55) ,歌集に『逍遊愚抄』 (77) ,歌学書に『九六古新注』 (70) ,『堀川百首肝要抄』 (84) ,狂歌書に『貞徳百首狂歌』 (36成立) などがある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について】
8-5 山陰の梅まだ寒し活大根(いけだいこ)
季語=梅(初春)
※「活大根」=いけ‐だいこん(生大根・埋大根)
【〘名〙 (「いけ」は生かす、埋める意の「いける」から)
① 畑から引き抜いたままの大根を地中に深くうずめて、翌年の春まで貯蔵し、食用とするもの。いけだいこ。《季・冬》
※俳諧・笈日記(1695)中「寒菊の隣もありやいけ大根〈許六〉」
② 大根の栽培品種で、根が地上に出ないで、深く地中に隠れているもの。二、三月頃に収穫する。かつて京都付近で多く栽培された。《季・春》
※俳諧・骨書(1787)下「かくれ家や花咲かかるいけ大根〈鶴市〉」】(「精選版 日本国語大辞典」)
句意(その周辺)=この句は、「梅」の句なのか、それとも「活大根(いけだいこ)」の句なのか? この「活大根」は、「いけ(活け)だいこ」(春)なのか、それとも、「いけ(埋け)だいこ」(冬)なのか?
この疑問には、この句が、「第八 花ぬふとり」の、冒頭(8-1)から五番目で掲載されていて、これに続く七番目(8-7)の句まで、冒頭(8-1)の前書の「己巳(きし・つちのとみ)の冬、居を藤塚といふところにうつして」が掛かる一群の、新居を構えた「根岸の郷(里)」の「歳暮・元日・梅」の句で、これは、「8-4から8-7」の三句続きの「梅」(初春)の句と解したい。同様に、この「活大根」は、「いけ(活け)だいこ」の「春採り大根」(初春)ということになる。
句意=「山陰(やまかげ)」の「梅」の花は、「まだ、寒さ」で、その傍らの、春採りの「「活大根(いけだいこ)」のように、間もなく来る「春の暖かさ」を待っている。
8-6 うぐゐすや梅に氷れる枝もなし
季語=「うぐゐす=鶯」(三春)と「梅」(初春)
https://fukusaisin.com/3842.html
立春の期間は2月4日頃~次の雨水に至る前日2月18日頃までを指します。
□ 初候 2月 4日頃 ~ 8日頃 … 東風解凍 … はるかぜこほりをとく
□ 次候 2月 9日頃 ~13日頃 … 黄鶯睍睆 … うぐひすなく
□ 末候 2月14日頃 ~18日頃 … 魚上氷 … うをこほりをいづる
句意(その周辺)=この「根岸の郷(里)」の「梅林」にも「鶯」が一斉に鳴いている。「東風解凍(はるかぜこほりをとく)」、そして、「黄鶯睍睆(うぐひすなく)」、さらに、「魚上氷(うをこほりをいづる)」と、見事な梅の季節となった。
8-7 梅を縫ふ糸ならなくに春の雨
季語=「梅」(初春)、そして、「春の雨(春雨))(三春)。
句意(その周辺)=「梅を縫ふ糸」とは、「第八 花(梅)ぬふ(縫う)とり(鶯)」のイメージ(雰囲気)の、その「鶯」)に解したい。そして、「糸(鶯)ならなくに春の雨」のイメージは、その「鶯」ではなく、「春の雨(春雨)」こそ、「梅を縫ふ(梅の花を開く)糸(その源)」なのである。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-06-18
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
酒井抱一筆「四季花鳥図屏風(右隻)」六曲一双 陽明文庫蔵 文化十三年(一八一六)
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html
酒井抱一筆「四季花鳥図屏風(左隻)」六曲一双 陽明文庫蔵 文化十三年(一八一六)
【 右隻の右から平坦な土坡に、春草のさまざま、蕨や菫や蒲公英、土筆、桜草、蓮華層などをちりばめ、雌雄の雲雀が上下に呼応する。続いて夏の花、牡丹、鬼百合、紫陽花、立葵、撫子、下の方には河骨、沢瀉、燕子花に、やはり白鷺が二羽向き合い、水鶏も隠れている。左隻には、秋の竜胆、桔梗、薄、女郎花、漆、葛、篠竹に、雉と鴫がいる。冬は水仙、白梅に鶯、榛(はん)の木、藪柑子である。
モチーフはそれぞれ明確に輪郭をとり厚く平たく塗り分け、ここで完璧な型づくりが為されたといっていいだろう。光琳百回忌から一年、濃彩で豪華な大作としては絵馬や仏画などを除いて早い一例となる。淡い彩色や墨を多用してきた抱一としては大変な飛躍であり、後の作画に内外に大きな影響を及ぼしたことが想像される。
本図は、昭和二年の抱一百年忌の展観に出品され、当時は、金融界の風雲児といわれた実業家で、浮世絵風俗画の収集でも知られる神田鐳蔵の所蔵であった。その前後、大正から昭和初めにかけて、さまざまな所蔵家のもとを変転したことが入札目録よりわかるが、それ以前の情報として、新出の田中抱二資料の嘉永元年(一八四八)の「写真」に、本図の縮図が見出されたことを報告しておく。 】
(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍社)』所収「作品解説(松尾知子稿))
第七 かみきぬた [第七 かみきぬた]
7-1 百舌のなく木末は昏て十三夜
季語=百舌=鵙(もず)・三秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2229#:~:text=%E9%B5%99%E3%81%AF%E7%A7%8B%E3%80%81%E6%9C%A8%E3%81%AE,%E6%99%B4%E3%80%8D%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%A8%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82
【子季語】 百舌鳥、伯労鳥、鵙日和、鵙の晴、鵙猛る、鵙の声、鵙の高音
【解説】 鵙は秋、木のてっぺんなどでキーイッ、キーイッと鋭い声で鳴く。小鳥ながら肉
食。その声が澄んだ秋の大気と通ずるので「鵙日和」「鵙の晴」などと用いられる。
【来歴】 『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。
【文学での言及】
秋の野の尾花が末に鳴く百舌鳥の声聞くらむか片侍つ吾妹 作者不詳『万葉集』
春されば百舌鳥草潜き見えずとも吾は見遣らむ君が辺りをば 作者不詳『万葉集』
頼めこし野辺の道芝夏深しいづくなるらむ鵙の草ぐき 藤原俊成『千載集』
【例句】
百舌鳥なくや入日さし込む女松原 凡兆「猿蓑」
鵙啼て一霜をまつ晩田哉 浪化「柿表紙」
草茎を失ふ百舌鳥の高音かな 蕪村「新五子稿」
漆掻くあたまのうへや鵙のこゑ 白雄「白雄句集」
鵙の来て一荒れ見ゆる野山かな 蓼太「蓼太句集」
日のさして鵙の贄見る葉裏かな 闌更「半化坊発句集」
鵙の声かんにん袋破れたか 一茶「七番日記」
※十三夜=後の月(晩秋)
https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%A4%9C&x=0&y=0
【子季語】 十三夜、名残の月、月の名残、二夜の月、豆名月、栗名月、女名月、後の今宵
【関連季語】 名月
【解説】 旧暦九月十三夜の月。八月十五夜は望月を愛でるが、秋もいよいよ深まったこの夜は、満月の二夜前の欠けた月を愛でる。この秋最後の月であることから名残の月、また豆や栗を供物とすることから豆名月、栗名月ともいう。
【来歴】 『俳諧初学抄』(寛永18年、1641年)に所出。
【文学での言及】
九月十三日夜、閑かに月見るといへることをよめる
すみのぼる心やそらをはらふらむ雲の塵ゐぬ秋の夜の月 源俊頼『金葉集」
【例句】
木曾の痩せもまだなほらぬに後の月 芭蕉「笈日記」
三井寺に緞子の夜着や後の月 蕪村「夜半叟句集」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html
「日本堤・隅田堤による狭窄部と遊水池」(国交省荒川下流河川事務所発行『都市を往く・荒川下流』より)
https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html
【◎[山谷堀]
東京都小平市に源を発し、練馬区・板橋区を東へ流れて北区堀船で隅田川に合流する石神井川の現・北区飛鳥山の麓には「王子の大堰」と云われる石堰が明暦二年(1656)以前に造られ、北区・荒川区・台東区の水田への灌漑用水を得ていた。灌漑用水の一つに「下郷二十三か村用水」があり、田端・西ケ原・中里を経て荒川・台東区に流れた。水路の最終部では三ノ輪・龍泉寺・千束・橋場・山谷・今戸村を経て、隅田川に注いだ。吉原大門辺りからの下流部は「山谷堀」と呼ばれている。
三ノ輪と今戸の中間辺りに吉原があったため、水路を利用する吉原への遊客は隅田川から今戸を経て猪牙舟で堀を上った。堀には今戸橋、聖天橋、吉野橋、正法寺橋、山谷堀橋、紙洗橋、地方〔じかた〕橋、日本堤橋と9つの橋が架かっていた。
◎[日本堤]
『江戸名所図会』本文の「日本堤」の項には、「聖天町より箕輪に至る。その間凡そ拾三町程(凡そ1400m)の長堤なり。(俗に八町縄手と云ふ。-山谷橋ともいった吉野橋から吉原大門辺りまでが八丁であった。)(中略)
日本堤は、高さ10尺(3m)、馬踏4間(7.2m)程だった。明暦三年(1657)に、浅草聖天町~三ノ輪のほぼ中間に吉原が移転してきてからは、吉原への通い路として往来が盛んであった。隅田堤は十六世紀後期の築造といわれている。 】
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html
広重・『絵本江戸土産』「日本堤・山谷」/注記に「聖天町の末より千住にいたる長堤なり。所々見どころ多しといへども、なかんづく吉原大門入口の辺より見渡せば、茫々たる広野にして、遙かに小塚原の地蔵を見る。雪の日に絶景なり。」とある。
https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html
「句意」(その周辺)
抱一は、文化二年(一八〇五)、四十五歳時に、「浅草寺の弁天池」辺りに転居し、「第六
潮の音」をスタートとして、その年末に、「山谷の紙洗橋」付近に転居し、「第七 紙(かみ)きぬた」が開始されたと記されている(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。
この「第七 紙(かみ)きぬた」は、「かみきぬた」そして「帋(かみ)きぬた」と、その『軽挙館句藻』では、その微妙な「紙・かみ・帋」と用字の使い分けをしながら、文化五年(一八〇八)、四十八歳時頃までの句作を書き留めているようである(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。
そして、この「第七 かみきぬた・紙きぬた・帋(かみ)きぬた」の由来は、その頃の転居先の、「山谷(堀)の紙洗橋」(吉原に通ずる日本堤に沿って流れる山谷堀に架かる小さな橋))にあるだろうとされている(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。
この「紙洗橋近くの新鳥越」に、享和三年(一八〇三)、抱一、四十三年時頃に開店した「料亭八百善」(『江戸流行料理通』初編を文化五年に出版。太田南畝、亀田鵬斎が序、酒井抱一、葛飾北斎が挿図を寄せている)がある(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html
歌川広重『江戸高名会亭尽』「山谷 八百善」(「ウィキペディア」)
【 享保年間に浅草山谷で創業[1][2]して以来、栄枯盛衰を繰り返す。もともとは八百屋だったが、周囲に寺が多かったことから料理の仕出しを始め、次第に料理屋として評判を取るようになった。
文政期の四代目の当主栗山善四郎は、多才多趣味で当世一流の文人墨客との交流が深く、狂歌、絵師、戯作家の大田南畝(蜀山人)に「詩は五山 役者は杜若 傾はかの 芸者は小萬 料理八百善」と言わしめた。また、八百善が文政五年に刊行した『江戸流行料理通』は当時の料理テキストとも言うべきものだが、蜀山人・鵬斎(亀田鵬斎)が序文を寄せ、谷文晁、葛飾北斎らが挿画を描いて評判になり、江戸土産としても人気を博した。】(「ウィキペディア」)
句意は、「吉原の『大文字屋』(大文字屋市兵衛)、そして、その別邸近くの『千束の料亭・田川屋(駐春亭)』(駐春亭右衛門)、それに続く、この『紙洗橋の料亭・八百善』(八百善善四郎)と、折りから、この晩秋を告げるような『百舌(もず)』が鳴いている。その鳴いている『木末(梢)』は、夕闇が迫って、もう、真っ暗闇と化してきた。さて、今日は、『大文字屋市兵衛』のねぐらか、それとも、『駐春亭右衛門』、それよりも、『八百善善四郎』のところとかと、ついつい、「十六夜(いざよい)」していると、その真っ暗闇の天に、何と、この晩秋の最後の名月の『後の月』が姿を現したことよ。」
(参考)「酒井抱一と『八百善善四郎』周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-01-25
『江戸流行料理通大全』p29 「食卓を囲む文人たち」
【上記は、文政五年(一八二二)に刊行された『江戸流行料理通大全』(栗山善四郎編著)の中からの抜粋である。ここに出てくる人物は、右から、「大田南畝(蜀山人)・亀田鵬斎・酒井抱一(?)か鍬形蕙斎(?)・大窪詩仏」で、中央手前の坊主頭は、酒井抱一ともいわれていたが、その羽織の紋所(立三橘)から、この挿絵の作者の「鍬形蕙斎(くわがたけいさい)」のようである(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「江戸の文人交友録(武田庸二郎稿))。
この「グルメ紹介本」は、当時、山谷にあった高級料亭「八百善」の主人・栗山善四郎が刊行したものである。酒井抱一は、表紙見返し頁(P2)に「蛤図」と「茸・山葵図」(P45)などを描いている。「序」(p2・3・4・5)は、亀田鵬斎の漢文のもので、さらに、谷文晁が、「白菜図」(P5)などを描いている(補記一のとおり)。
ここに登場する「下谷の三幅対」と称された、年齢順にして、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」とは、これは、まさしく、「江戸の三幅対」の言葉を呈したい位の、まさしく、切っも切れない、「江戸時代(三百年)」の、その「江戸(東京)」を代表する、「三幅対」の、それを象徴する「交友関係」であったという思いを深くする。
その「江戸の三幅対」の、「江戸(江戸時代・江戸=東京)」の、その「江戸」に焦点を当てると、その中心に位置するのが、上記に掲げた「食卓を囲む文人たち」の、その長老格の「亀田鵬斎」ということに思い知るのである。
しかも、この「鵬斎」は、抱一にとっては、無二の「画・俳」友である、「建部巣兆」の義理の兄にも当たるのである。
上記の、『江戸流行料理通大全』の、上記の挿絵の、その中心に位置する「亀田鵬斎」とは、「鵬斎・抱一・文晃」の、いわゆる、「江戸」(東京)の「下谷」(「吉原」界隈の下谷)の、その「下谷の三幅対」と云われ、その三幅対の真ん中に位置する、その中心的な最長老の人物が、亀田鵬斎なのである。
そして、この三人(「下谷の三幅対」)は、それぞれ、「江戸の大儒者(学者)・亀田鵬斎」、「江戸南画の大成者・谷文晁」、そして、「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と、その頭に「江戸」の二字が冠するのに、最も相応しい人物のように思われるのである。
これらの、江戸の文人墨客を代表する「鵬斎・抱一・文晁」が活躍した時代というのは、それ以前の、ごく限られた階層(公家・武家など)の独占物であった「芸術」(詩・書・画など)を、四民(士農工商)が共用するようになった時代ということを意味しよう。
それはまた、「詩・書・画など」を「生業(なりわい)」とする職業的文人・墨客が出現したということを意味しよう。さらに、それらは、流れ者が吹き溜まりのように集中して来る、当時の「江戸」(東京)にあっては、能力があれば、誰でもが温かく受け入れられ、その才能を伸ばし、そして、惜しみない援助の手が差し伸べられた、そのような環境下が助成されていたと言っても過言ではなかろう。
さらに換言するならば、「士農工商」の身分に拘泥することもなく、いわゆる「農工商」の庶民層が、その時代の、それを象徴する「芸術・文化」の担い手として、その第一線に登場して来たということを意味しよう。
すなわち、「江戸(東京)時代」以前の、綿々と続いていた、京都を中心とする、「公家の芸術・文化」、それに拮抗しての全国各地で芽生えた「武家の芸術・文化」が、得体の知れない「江戸(東京)」の、得体の知れない「庶民(市民)の芸術・文化」に様変わりして行ったということを意味しょう。
抱一の「略年譜」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収)の「享和二年(一八〇二)四十二歳」に、「亀田鵬斎、谷文晁とともに、常陸の若芝金龍寺に出かけ、蘇東坡像を見る」とある。
この年譜の背後には大きな時代の変革の嵐が押し寄せていた。それは、遡って、天明七年(一七八七)、徳川家斉が第十一代将軍となり、松平定信が老中に就任し、いわゆる、「寛政の大改革」が始まり、幕府大名旗本に三年の倹約令が発せられると、大きな変革の流れであったのである。
寛政三年(一七九一)、抱一と同年齢の朋友、戯作者・山東京伝(浮世絵師・北尾政演)は、洒落本三作が禁令を犯したという理由で筆禍を受け、手鎖五十日の処分を受ける。この時に、山東京伝らの黄表紙・洒落本、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵などの出版で知られる。「蔦重」こと蔦屋重三郎も過料に処せられ、財産半分が没収され、寛政九年(一七九七)には、その四十八年の生涯を閉じている。
この蔦屋重三郎が没した寛政九年(一七九七)、抱一、三十七最の時が、抱一に取って、大きな節目の年であった。その十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家し、「等覚院文詮暉真」の法名を名乗り、以後、「抱一上人」と仰がれることになる。
しかし、この抱一の出家の背後には、抱一の甥の姫路藩主、酒井忠道が弟の忠光を養嗣子に迎えるという幕府の許可とセットになっており、抱一は、酒井家を実質的に切り捨てられるという、その「酒井家」離脱を意味するものなのであろう。
この時に、抱一は、柿本人麻呂の和歌「世の中をうしといひてもいづこにか身をばかくさん山なしの花」を踏まえての、「遯入(のがれい)る山ありの実の天窓(あたま)かな」(句稿『椎の木陰』)との、その出家を受け入れる諦めにも似た一句を詠んでいる。そして、この句は、抱一の自撰句集『屠龍之技』では、「遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな」と、自らの意思で出家をしたように、断定的な句形で所収され、それが最終稿となっている。これらのことを踏まえると、抱一の出家というのは、抱一に取っては、不本意な、鬱積した諸事情があったことを、この一句に託していねかのように思われる。
これらのことと、いわゆる、時の老中・松平定信の「寛政の改革」とを直接的に結びつけることは極めて危険なことであるが、亀田鵬斎の場合は、幕府正学となった朱子学以外の学問を排斥するところの、いわゆる「寛政異学の禁」の発布により、「異学の五鬼」(亀田鵬斎・山本北山・冢田大峯・豊島豊洲・市川鶴鳴)の一人として目され、その門下生が殆ど離散するという、その現実的な一面を見逃すことも出来ないであろう。
この亀田鵬斎、そして、その義弟の建部巣兆と酒井抱一との交友関係は、この三人の生涯にわたって密なるものがあった。抱一の「画」に、漢詩・漢文の「書」の賛は、鵬斎のものが圧倒的に多い。そして、抱一の「画」に、和歌・和文の「書」は、抱一が見出した、橘千蔭と、この二人の「賛」は、抱一の「画」の一つの特色ともなっている。
そして、この橘千蔭も、鵬斎と同じように、寛政の改革により、その賀茂真淵の国学との関係からか、不運な立場に追い込まれていて、抱一は、鵬斎と千蔭とを、自己の「画」の「賛」者としていることは、やはり、その根っ子には、「寛政の改革」への、反権力、反権威への、抱一ならでは、一つのメッセージが込められているようにも思われる。
しかし、抱一は、出家して酒井家を離脱しても、徳川家三河恩顧の重臣の譜代大名の酒井雅樂頭家に連なる一員であることは、いささかの変わりもない。その酒井雅樂頭家が、時の権力・権威の象徴である、老中首座に就いた松平定信の、いわゆる厳しい風俗統制の「寛政の改革」に、面と向かって異を唱えることは、決して許されることではなかったであろう。】
季語=百舌=鵙(もず)・三秋
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2229#:~:text=%E9%B5%99%E3%81%AF%E7%A7%8B%E3%80%81%E6%9C%A8%E3%81%AE,%E6%99%B4%E3%80%8D%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%A8%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82
【子季語】 百舌鳥、伯労鳥、鵙日和、鵙の晴、鵙猛る、鵙の声、鵙の高音
【解説】 鵙は秋、木のてっぺんなどでキーイッ、キーイッと鋭い声で鳴く。小鳥ながら肉
食。その声が澄んだ秋の大気と通ずるので「鵙日和」「鵙の晴」などと用いられる。
【来歴】 『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。
【文学での言及】
秋の野の尾花が末に鳴く百舌鳥の声聞くらむか片侍つ吾妹 作者不詳『万葉集』
春されば百舌鳥草潜き見えずとも吾は見遣らむ君が辺りをば 作者不詳『万葉集』
頼めこし野辺の道芝夏深しいづくなるらむ鵙の草ぐき 藤原俊成『千載集』
【例句】
百舌鳥なくや入日さし込む女松原 凡兆「猿蓑」
鵙啼て一霜をまつ晩田哉 浪化「柿表紙」
草茎を失ふ百舌鳥の高音かな 蕪村「新五子稿」
漆掻くあたまのうへや鵙のこゑ 白雄「白雄句集」
鵙の来て一荒れ見ゆる野山かな 蓼太「蓼太句集」
日のさして鵙の贄見る葉裏かな 闌更「半化坊発句集」
鵙の声かんにん袋破れたか 一茶「七番日記」
※十三夜=後の月(晩秋)
https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%A4%9C&x=0&y=0
【子季語】 十三夜、名残の月、月の名残、二夜の月、豆名月、栗名月、女名月、後の今宵
【関連季語】 名月
【解説】 旧暦九月十三夜の月。八月十五夜は望月を愛でるが、秋もいよいよ深まったこの夜は、満月の二夜前の欠けた月を愛でる。この秋最後の月であることから名残の月、また豆や栗を供物とすることから豆名月、栗名月ともいう。
【来歴】 『俳諧初学抄』(寛永18年、1641年)に所出。
【文学での言及】
九月十三日夜、閑かに月見るといへることをよめる
すみのぼる心やそらをはらふらむ雲の塵ゐぬ秋の夜の月 源俊頼『金葉集」
【例句】
木曾の痩せもまだなほらぬに後の月 芭蕉「笈日記」
三井寺に緞子の夜着や後の月 蕪村「夜半叟句集」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html
「日本堤・隅田堤による狭窄部と遊水池」(国交省荒川下流河川事務所発行『都市を往く・荒川下流』より)
https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html
【◎[山谷堀]
東京都小平市に源を発し、練馬区・板橋区を東へ流れて北区堀船で隅田川に合流する石神井川の現・北区飛鳥山の麓には「王子の大堰」と云われる石堰が明暦二年(1656)以前に造られ、北区・荒川区・台東区の水田への灌漑用水を得ていた。灌漑用水の一つに「下郷二十三か村用水」があり、田端・西ケ原・中里を経て荒川・台東区に流れた。水路の最終部では三ノ輪・龍泉寺・千束・橋場・山谷・今戸村を経て、隅田川に注いだ。吉原大門辺りからの下流部は「山谷堀」と呼ばれている。
三ノ輪と今戸の中間辺りに吉原があったため、水路を利用する吉原への遊客は隅田川から今戸を経て猪牙舟で堀を上った。堀には今戸橋、聖天橋、吉野橋、正法寺橋、山谷堀橋、紙洗橋、地方〔じかた〕橋、日本堤橋と9つの橋が架かっていた。
◎[日本堤]
『江戸名所図会』本文の「日本堤」の項には、「聖天町より箕輪に至る。その間凡そ拾三町程(凡そ1400m)の長堤なり。(俗に八町縄手と云ふ。-山谷橋ともいった吉野橋から吉原大門辺りまでが八丁であった。)(中略)
日本堤は、高さ10尺(3m)、馬踏4間(7.2m)程だった。明暦三年(1657)に、浅草聖天町~三ノ輪のほぼ中間に吉原が移転してきてからは、吉原への通い路として往来が盛んであった。隅田堤は十六世紀後期の築造といわれている。 】
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html
広重・『絵本江戸土産』「日本堤・山谷」/注記に「聖天町の末より千住にいたる長堤なり。所々見どころ多しといへども、なかんづく吉原大門入口の辺より見渡せば、茫々たる広野にして、遙かに小塚原の地蔵を見る。雪の日に絶景なり。」とある。
https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html
「句意」(その周辺)
抱一は、文化二年(一八〇五)、四十五歳時に、「浅草寺の弁天池」辺りに転居し、「第六
潮の音」をスタートとして、その年末に、「山谷の紙洗橋」付近に転居し、「第七 紙(かみ)きぬた」が開始されたと記されている(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。
この「第七 紙(かみ)きぬた」は、「かみきぬた」そして「帋(かみ)きぬた」と、その『軽挙館句藻』では、その微妙な「紙・かみ・帋」と用字の使い分けをしながら、文化五年(一八〇八)、四十八歳時頃までの句作を書き留めているようである(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。
そして、この「第七 かみきぬた・紙きぬた・帋(かみ)きぬた」の由来は、その頃の転居先の、「山谷(堀)の紙洗橋」(吉原に通ずる日本堤に沿って流れる山谷堀に架かる小さな橋))にあるだろうとされている(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。
この「紙洗橋近くの新鳥越」に、享和三年(一八〇三)、抱一、四十三年時頃に開店した「料亭八百善」(『江戸流行料理通』初編を文化五年に出版。太田南畝、亀田鵬斎が序、酒井抱一、葛飾北斎が挿図を寄せている)がある(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html
歌川広重『江戸高名会亭尽』「山谷 八百善」(「ウィキペディア」)
【 享保年間に浅草山谷で創業[1][2]して以来、栄枯盛衰を繰り返す。もともとは八百屋だったが、周囲に寺が多かったことから料理の仕出しを始め、次第に料理屋として評判を取るようになった。
文政期の四代目の当主栗山善四郎は、多才多趣味で当世一流の文人墨客との交流が深く、狂歌、絵師、戯作家の大田南畝(蜀山人)に「詩は五山 役者は杜若 傾はかの 芸者は小萬 料理八百善」と言わしめた。また、八百善が文政五年に刊行した『江戸流行料理通』は当時の料理テキストとも言うべきものだが、蜀山人・鵬斎(亀田鵬斎)が序文を寄せ、谷文晁、葛飾北斎らが挿画を描いて評判になり、江戸土産としても人気を博した。】(「ウィキペディア」)
句意は、「吉原の『大文字屋』(大文字屋市兵衛)、そして、その別邸近くの『千束の料亭・田川屋(駐春亭)』(駐春亭右衛門)、それに続く、この『紙洗橋の料亭・八百善』(八百善善四郎)と、折りから、この晩秋を告げるような『百舌(もず)』が鳴いている。その鳴いている『木末(梢)』は、夕闇が迫って、もう、真っ暗闇と化してきた。さて、今日は、『大文字屋市兵衛』のねぐらか、それとも、『駐春亭右衛門』、それよりも、『八百善善四郎』のところとかと、ついつい、「十六夜(いざよい)」していると、その真っ暗闇の天に、何と、この晩秋の最後の名月の『後の月』が姿を現したことよ。」
(参考)「酒井抱一と『八百善善四郎』周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-01-25
『江戸流行料理通大全』p29 「食卓を囲む文人たち」
【上記は、文政五年(一八二二)に刊行された『江戸流行料理通大全』(栗山善四郎編著)の中からの抜粋である。ここに出てくる人物は、右から、「大田南畝(蜀山人)・亀田鵬斎・酒井抱一(?)か鍬形蕙斎(?)・大窪詩仏」で、中央手前の坊主頭は、酒井抱一ともいわれていたが、その羽織の紋所(立三橘)から、この挿絵の作者の「鍬形蕙斎(くわがたけいさい)」のようである(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「江戸の文人交友録(武田庸二郎稿))。
この「グルメ紹介本」は、当時、山谷にあった高級料亭「八百善」の主人・栗山善四郎が刊行したものである。酒井抱一は、表紙見返し頁(P2)に「蛤図」と「茸・山葵図」(P45)などを描いている。「序」(p2・3・4・5)は、亀田鵬斎の漢文のもので、さらに、谷文晁が、「白菜図」(P5)などを描いている(補記一のとおり)。
ここに登場する「下谷の三幅対」と称された、年齢順にして、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」とは、これは、まさしく、「江戸の三幅対」の言葉を呈したい位の、まさしく、切っも切れない、「江戸時代(三百年)」の、その「江戸(東京)」を代表する、「三幅対」の、それを象徴する「交友関係」であったという思いを深くする。
その「江戸の三幅対」の、「江戸(江戸時代・江戸=東京)」の、その「江戸」に焦点を当てると、その中心に位置するのが、上記に掲げた「食卓を囲む文人たち」の、その長老格の「亀田鵬斎」ということに思い知るのである。
しかも、この「鵬斎」は、抱一にとっては、無二の「画・俳」友である、「建部巣兆」の義理の兄にも当たるのである。
上記の、『江戸流行料理通大全』の、上記の挿絵の、その中心に位置する「亀田鵬斎」とは、「鵬斎・抱一・文晃」の、いわゆる、「江戸」(東京)の「下谷」(「吉原」界隈の下谷)の、その「下谷の三幅対」と云われ、その三幅対の真ん中に位置する、その中心的な最長老の人物が、亀田鵬斎なのである。
そして、この三人(「下谷の三幅対」)は、それぞれ、「江戸の大儒者(学者)・亀田鵬斎」、「江戸南画の大成者・谷文晁」、そして、「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と、その頭に「江戸」の二字が冠するのに、最も相応しい人物のように思われるのである。
これらの、江戸の文人墨客を代表する「鵬斎・抱一・文晁」が活躍した時代というのは、それ以前の、ごく限られた階層(公家・武家など)の独占物であった「芸術」(詩・書・画など)を、四民(士農工商)が共用するようになった時代ということを意味しよう。
それはまた、「詩・書・画など」を「生業(なりわい)」とする職業的文人・墨客が出現したということを意味しよう。さらに、それらは、流れ者が吹き溜まりのように集中して来る、当時の「江戸」(東京)にあっては、能力があれば、誰でもが温かく受け入れられ、その才能を伸ばし、そして、惜しみない援助の手が差し伸べられた、そのような環境下が助成されていたと言っても過言ではなかろう。
さらに換言するならば、「士農工商」の身分に拘泥することもなく、いわゆる「農工商」の庶民層が、その時代の、それを象徴する「芸術・文化」の担い手として、その第一線に登場して来たということを意味しよう。
すなわち、「江戸(東京)時代」以前の、綿々と続いていた、京都を中心とする、「公家の芸術・文化」、それに拮抗しての全国各地で芽生えた「武家の芸術・文化」が、得体の知れない「江戸(東京)」の、得体の知れない「庶民(市民)の芸術・文化」に様変わりして行ったということを意味しょう。
抱一の「略年譜」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収)の「享和二年(一八〇二)四十二歳」に、「亀田鵬斎、谷文晁とともに、常陸の若芝金龍寺に出かけ、蘇東坡像を見る」とある。
この年譜の背後には大きな時代の変革の嵐が押し寄せていた。それは、遡って、天明七年(一七八七)、徳川家斉が第十一代将軍となり、松平定信が老中に就任し、いわゆる、「寛政の大改革」が始まり、幕府大名旗本に三年の倹約令が発せられると、大きな変革の流れであったのである。
寛政三年(一七九一)、抱一と同年齢の朋友、戯作者・山東京伝(浮世絵師・北尾政演)は、洒落本三作が禁令を犯したという理由で筆禍を受け、手鎖五十日の処分を受ける。この時に、山東京伝らの黄表紙・洒落本、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵などの出版で知られる。「蔦重」こと蔦屋重三郎も過料に処せられ、財産半分が没収され、寛政九年(一七九七)には、その四十八年の生涯を閉じている。
この蔦屋重三郎が没した寛政九年(一七九七)、抱一、三十七最の時が、抱一に取って、大きな節目の年であった。その十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家し、「等覚院文詮暉真」の法名を名乗り、以後、「抱一上人」と仰がれることになる。
しかし、この抱一の出家の背後には、抱一の甥の姫路藩主、酒井忠道が弟の忠光を養嗣子に迎えるという幕府の許可とセットになっており、抱一は、酒井家を実質的に切り捨てられるという、その「酒井家」離脱を意味するものなのであろう。
この時に、抱一は、柿本人麻呂の和歌「世の中をうしといひてもいづこにか身をばかくさん山なしの花」を踏まえての、「遯入(のがれい)る山ありの実の天窓(あたま)かな」(句稿『椎の木陰』)との、その出家を受け入れる諦めにも似た一句を詠んでいる。そして、この句は、抱一の自撰句集『屠龍之技』では、「遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな」と、自らの意思で出家をしたように、断定的な句形で所収され、それが最終稿となっている。これらのことを踏まえると、抱一の出家というのは、抱一に取っては、不本意な、鬱積した諸事情があったことを、この一句に託していねかのように思われる。
これらのことと、いわゆる、時の老中・松平定信の「寛政の改革」とを直接的に結びつけることは極めて危険なことであるが、亀田鵬斎の場合は、幕府正学となった朱子学以外の学問を排斥するところの、いわゆる「寛政異学の禁」の発布により、「異学の五鬼」(亀田鵬斎・山本北山・冢田大峯・豊島豊洲・市川鶴鳴)の一人として目され、その門下生が殆ど離散するという、その現実的な一面を見逃すことも出来ないであろう。
この亀田鵬斎、そして、その義弟の建部巣兆と酒井抱一との交友関係は、この三人の生涯にわたって密なるものがあった。抱一の「画」に、漢詩・漢文の「書」の賛は、鵬斎のものが圧倒的に多い。そして、抱一の「画」に、和歌・和文の「書」は、抱一が見出した、橘千蔭と、この二人の「賛」は、抱一の「画」の一つの特色ともなっている。
そして、この橘千蔭も、鵬斎と同じように、寛政の改革により、その賀茂真淵の国学との関係からか、不運な立場に追い込まれていて、抱一は、鵬斎と千蔭とを、自己の「画」の「賛」者としていることは、やはり、その根っ子には、「寛政の改革」への、反権力、反権威への、抱一ならでは、一つのメッセージが込められているようにも思われる。
しかし、抱一は、出家して酒井家を離脱しても、徳川家三河恩顧の重臣の譜代大名の酒井雅樂頭家に連なる一員であることは、いささかの変わりもない。その酒井雅樂頭家が、時の権力・権威の象徴である、老中首座に就いた松平定信の、いわゆる厳しい風俗統制の「寛政の改革」に、面と向かって異を唱えることは、決して許されることではなかったであろう。】
第六 潮のおと(6-1) [第六 潮のおと]
6-1 鳥さしが手際見せけり梅林
季語=梅林(うめばやし・ばいりん)=梅(初春)の林
※「鳥さし」周辺
≪[1] 〘名〙① 細い竹竿などの先端に鳥黐(とりもち)を塗りつけ、小鳥を捕えること。ま
た、その人。特に、小鳥を捕えてそれを売るのを業とした人。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
※三十二番職人歌合(1494頃)三番「右 とりさし 春は又ところも花の千本にみせをくた
なの鳥のいろいろ」
② 江戸幕府の御鷹の餌にする小鳥を請け負った者。また、その配下。
③ 江戸時代の遊戯の一つ。殿様・用人・鳥刺し各一枚、他に種々の鳥の絵を描いた札一三
枚、合計一六枚の札から成り、殿様の命により用人が鳥刺しに鳥を捕えさせる仕組みになっ
ている。
※歌舞伎・五十三駅扇宿附(岡崎の猫)(1887)五幕「是れから鳥(トリ)さしか、お茶坊主
をして遊ばうと」
④ 民俗芸能の一つ。①の動作をおもしろおかしく舞踊化したもの。また、万歳の一つ。大
夫が鳥を刺すまねをし、才蔵が鳥づくしの歌をうたうもの。鳥刺し舞。鳥刺し踊り。
⑤ 鳥肉の刺身。
[2] 歌舞伎所作事。清元。三升屋二三治作詞。初世清元斎兵衛作曲。天保二年(一八三一)
江戸市村座初演。本名題「祇園町一力の段」。二世関三十郎の太鼓持ち次郎左衛門が、鳥づ
くしの文句で、鳥刺しの振りを座興に踊る。≫(「精選版 日本国語大辞典」)
https://kuniedayu.com/library/torisashi/
≪「鳥さし」とも「鳥刺し」とも書きます。
1748年(寛延元年)初演の「仮名手本忠臣蔵」の爆発的人気を背景に1767年(明和4年)
に「太平記忠臣講釈」が歌舞伎で初演されました。その七段目「祇園町一力の段」で一力茶
屋で塩冶縫之助が遊興し、太鼓持ちの岸野次郎左衛門が劇中で鳥刺しの格好に扮して踊っ
たものが初演と伝わっています。
現在では一つの演目として上演されるのみとなりました。
鳥さしとは、細い竹の先端に鳥餅を付けて小鳥などを引っかけて捕らえる職業で大正頃
まで見かけた職業の事です。
曲冒頭の「さすぞぇさすは盃~」は
鳥さしの刺す→盃を注す→初会の客(遊郭などで初めてのお客に盃を交わすしきたり)
と、鳥さしと一力茶屋を関連付けた歌詞になっています。
その他各所に「鳥」との洒落を盛り込んだ文句に軽妙な曲付けになっております。
歌詞
さすぞぇさすは盃 初会の客よ
手にはとれども初心顔
さいてくりょ さいてくりょ
これ物にかんまえて まっこれ物にかんまえて
ちょっとさいてくりょうか さいたら子供に羽根やろな
ひわや小雀や四十雀 瑠璃は見事な錦鳥
こいつは妙々 奇妙鳥類何んでもござれ
念仏はそばで禁物と 目当違わぬ稲むらを
狙いの的とためつすがめつ
いでや手並を一と差しと 一散走りに向うを見て
きょろつき眼をあちこちと 鳥さし掉も其儘に
手足延して捕らんとすれば 鳥はどこへか随徳寺
思案途方に立ち止まり
したりところてんではなけども 突出されても自分もの
是じゃ行かぬと捨鉢に 跡はどうなれ弾く三味線の
気も二上りか三下り 浮いて来た来た来たさの
酒の酔い心
四条五条の夕涼み 芸妓たいこを引連れて
上から下へ幾度も ゆたかな客の朝帰り カァカァカァ
鴉鳴きさえェェ うまい奴めと
なぶりおかめから そこらの目白が
見つけたらさぞ 鶺鴒であろうのに
日がらひばりの約束は いつも葭切顔鳥見たさ
文にもくどう駒鳥の そのかえす書きかえり事
なぞと口説きで仕かけたら 堪った色ではないかいな
其時あいつが口癖に 都々逸文句も古めいた
晩に忍べと云うた故 紺の手拭で顔隠し
いつも合図の咳払い ハックサメ
噂されたを評判に 幸いありや有難き
実に御ひいきの時を得て 座敷の興も面白き
息せき楽屋へ走り行く ≫
「句意」(その周辺)
この「第六 潮のおと」のスタートの一句も、これまた、この一句の、その上五の「鳥さし」が、やはり、当時の、抱一の、趣向に趣向を凝らした、何かを仕掛けている雰囲気なのである。
句意は、「『鳥刺し』が、この『梅林』で、見事な『手際』を見せている。折から、声曲の『鳥さし』の『手際』よい調べが聞こえくる。『さいてくりょ さいてくりょ これ物にかんまえて まっこれ物にかんまえて ちょっとさいてくりょうか …… 』と、これまた、見事な『手際』であることよ。」
この「第六 潮のおと」は、文化二年(一八〇五)、抱一、四十五歳、「浅草寺の弁天池に転居」の頃に、スタートしており(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)、この前年の文化元年(一八〇四)に、抱一と親交の深い「佐原菊塢(さはらきくう)」が「向島百花園(別称「新梅屋敷」)」を開園している。その梅林での一句と解するのも一興であろう。
(参考一) 佐原菊塢(さはらきくう)の『新梅屋敷』」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
「東都三十六景 向しま花屋敷七草」(歌川広重筆)
https://www.ndl.go.jp/landmarks/sights/mukojimahyakkaen/
【文化元(1804)年、骨董商の佐原菊塢(さはらきくう)が梅やすすきなどの日本古来の草木を集め、幕臣の多賀家屋敷跡に造園した庭園。名称は江戸後期の画家酒井抱一が「梅は百花のさきがけ」の意から名付けたとされる。当初は360本の梅が主体で、亀戸梅屋敷に対して、新梅屋敷とも呼ばれた。現在は都営庭園となり、国の史跡・名勝に指定されている。】(国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」)
(参考二) 佐原鞠塢の「向島百花園」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306183697-1
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
佐原鞠塢肖像、「園のいしぶみ」より
↑
http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/siryou/kyoudobunka/tenzi/h16/kikakuten_hyakkaen.html
↓
【百花園の開園者、佐原鞠塢(きくう)
百花園を開いた佐原鞠塢は、奥州仙台の農民の出で、俗称を平八といった。明和元年(1764年)生まれという説があるが不詳。天明年間(1781年から1789年)に江戸に出てきて、中村座の芝居茶屋・和泉屋勘十郎のもとで奉公した。その後、財を蓄え、それを元手に寛政8年(1796年)頃、日本橋住吉町に骨董屋の店を開き、名を北野屋平兵衛(北平とも)と改めた。芝居茶屋での奉公、骨董商時代の幅広いつき合いがもとで、当代の文人たちとの人脈を形成し、その過程で自らも書画・和歌・漢詩などを修得した。鞠塢は、商才のある人であったらしく、文人たちを集めて古道具市をしばしば開催したが、値をあげるためのオークション的な商法が幕府の咎めを受けたという。
しばらくの間、本所中の郷(現向島1丁目付近)にいたが、文化元年(1804年)頃に剃髪して、「鞠塢菩薩」の号を名乗った。この頃、向島にあった旗本・多賀氏の屋敷跡を購入し、ここに展示で紹介する著名な文人達より梅樹の寄付や造園に協力を仰ぎ、風雅な草庭を造ったのが百花園の起こりである。園は梅の季節だけでなく、和漢の古典の知識を生かして「春の七草」「秋の七草」や「万葉集」に見える草花を植えたため、四季を通じて草花が見られるようになり、いつしか梅屋敷・秋芳園・百花園などと呼ばれるようになった。園の経営者としても鞠塢の才能はいかんなく発揮され、園内の茶店では、隅田川焼という焼き物や「寿星梅」という梅干しなどを名物として販売。また、園内で向島の名所を描きこんだ地図を刷り人々に頒布して、来園者の誘致を図り、次第にその評判が高まっていった。天保2年(1931年)8月29日に死没。編著書に漢詩集「盛音集」、句集「墨多川集」「花袋」のほか、
「秋野七草考」「春野七草考」「梅屋花品」「墨水遊覧誌」「都鳥考」などがある。】(「墨田区企画展『開園200年記念百花園』」)
(参考三)「名所江戸百景・亀戸梅屋舗」(歌川広重筆)
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
「名所江戸百景・亀戸梅屋舗」(歌川広重筆)奈良県立美術館蔵
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/112047
【 歌川広重 (1797~1858) 江戸時代/1857/竪大判錦絵/37.2×24.3㎝
(解説) 前景に当時有名であった「臥竜梅」を大きく描く構図は、新鮮で印象的な詩情を求めた『名所江戸百景』の新しい試みをよく示している。赤・紫・緑を背景に純白の梅が馥郁と薫っている。装飾的で象徴的な日本の伝統的表現法が生かされ、早春の気配が巧みに描き出されている。印象的で装飾的な表現を多用したこのシリーズは、『東海道五十三次』などに見られる繊細な写実を脱し、歌川広重の新しい詩境を示すものであった。判形もたて形を用い、緊張感と動性をよくあらわすものである。 】(「文化遺産オンライン」)
(参考四)「第六 潮のおと」の「潮(しお)のおと」の由来
【 浅草寺周辺に居た頃の句集名は「潮(しお)の音(おと)。浅草寺の祀る観音菩薩像にちなみ、「法華経観世音菩薩普門品偈(ぼんげ)」の「妙音観世音、梵音海潮(かいちょう)音」を出典とする。ごく短期間の移住だったようで、『軽挙館句藻』現存第四冊目の「千束のゐね」の後半に書き付けられている。居住場所は、「等覚院殿御一代」に「浅草観音の境内弁天池のほとり」とあることから、浅草寺境内東南の弁天社付近であったことが分かる。」】
(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
「江戸名所之内 浅草金竜山弁天山之図」(絵師:歌川広重/出版者:丸甚/収載資料名:東都名所/国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」)
https://www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail287.html?sights=sensoji;tokyo=taito
季語=梅林(うめばやし・ばいりん)=梅(初春)の林
※「鳥さし」周辺
≪[1] 〘名〙① 細い竹竿などの先端に鳥黐(とりもち)を塗りつけ、小鳥を捕えること。ま
た、その人。特に、小鳥を捕えてそれを売るのを業とした人。
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
※三十二番職人歌合(1494頃)三番「右 とりさし 春は又ところも花の千本にみせをくた
なの鳥のいろいろ」
② 江戸幕府の御鷹の餌にする小鳥を請け負った者。また、その配下。
③ 江戸時代の遊戯の一つ。殿様・用人・鳥刺し各一枚、他に種々の鳥の絵を描いた札一三
枚、合計一六枚の札から成り、殿様の命により用人が鳥刺しに鳥を捕えさせる仕組みになっ
ている。
※歌舞伎・五十三駅扇宿附(岡崎の猫)(1887)五幕「是れから鳥(トリ)さしか、お茶坊主
をして遊ばうと」
④ 民俗芸能の一つ。①の動作をおもしろおかしく舞踊化したもの。また、万歳の一つ。大
夫が鳥を刺すまねをし、才蔵が鳥づくしの歌をうたうもの。鳥刺し舞。鳥刺し踊り。
⑤ 鳥肉の刺身。
[2] 歌舞伎所作事。清元。三升屋二三治作詞。初世清元斎兵衛作曲。天保二年(一八三一)
江戸市村座初演。本名題「祇園町一力の段」。二世関三十郎の太鼓持ち次郎左衛門が、鳥づ
くしの文句で、鳥刺しの振りを座興に踊る。≫(「精選版 日本国語大辞典」)
https://kuniedayu.com/library/torisashi/
≪「鳥さし」とも「鳥刺し」とも書きます。
1748年(寛延元年)初演の「仮名手本忠臣蔵」の爆発的人気を背景に1767年(明和4年)
に「太平記忠臣講釈」が歌舞伎で初演されました。その七段目「祇園町一力の段」で一力茶
屋で塩冶縫之助が遊興し、太鼓持ちの岸野次郎左衛門が劇中で鳥刺しの格好に扮して踊っ
たものが初演と伝わっています。
現在では一つの演目として上演されるのみとなりました。
鳥さしとは、細い竹の先端に鳥餅を付けて小鳥などを引っかけて捕らえる職業で大正頃
まで見かけた職業の事です。
曲冒頭の「さすぞぇさすは盃~」は
鳥さしの刺す→盃を注す→初会の客(遊郭などで初めてのお客に盃を交わすしきたり)
と、鳥さしと一力茶屋を関連付けた歌詞になっています。
その他各所に「鳥」との洒落を盛り込んだ文句に軽妙な曲付けになっております。
歌詞
さすぞぇさすは盃 初会の客よ
手にはとれども初心顔
さいてくりょ さいてくりょ
これ物にかんまえて まっこれ物にかんまえて
ちょっとさいてくりょうか さいたら子供に羽根やろな
ひわや小雀や四十雀 瑠璃は見事な錦鳥
こいつは妙々 奇妙鳥類何んでもござれ
念仏はそばで禁物と 目当違わぬ稲むらを
狙いの的とためつすがめつ
いでや手並を一と差しと 一散走りに向うを見て
きょろつき眼をあちこちと 鳥さし掉も其儘に
手足延して捕らんとすれば 鳥はどこへか随徳寺
思案途方に立ち止まり
したりところてんではなけども 突出されても自分もの
是じゃ行かぬと捨鉢に 跡はどうなれ弾く三味線の
気も二上りか三下り 浮いて来た来た来たさの
酒の酔い心
四条五条の夕涼み 芸妓たいこを引連れて
上から下へ幾度も ゆたかな客の朝帰り カァカァカァ
鴉鳴きさえェェ うまい奴めと
なぶりおかめから そこらの目白が
見つけたらさぞ 鶺鴒であろうのに
日がらひばりの約束は いつも葭切顔鳥見たさ
文にもくどう駒鳥の そのかえす書きかえり事
なぞと口説きで仕かけたら 堪った色ではないかいな
其時あいつが口癖に 都々逸文句も古めいた
晩に忍べと云うた故 紺の手拭で顔隠し
いつも合図の咳払い ハックサメ
噂されたを評判に 幸いありや有難き
実に御ひいきの時を得て 座敷の興も面白き
息せき楽屋へ走り行く ≫
「句意」(その周辺)
この「第六 潮のおと」のスタートの一句も、これまた、この一句の、その上五の「鳥さし」が、やはり、当時の、抱一の、趣向に趣向を凝らした、何かを仕掛けている雰囲気なのである。
句意は、「『鳥刺し』が、この『梅林』で、見事な『手際』を見せている。折から、声曲の『鳥さし』の『手際』よい調べが聞こえくる。『さいてくりょ さいてくりょ これ物にかんまえて まっこれ物にかんまえて ちょっとさいてくりょうか …… 』と、これまた、見事な『手際』であることよ。」
この「第六 潮のおと」は、文化二年(一八〇五)、抱一、四十五歳、「浅草寺の弁天池に転居」の頃に、スタートしており(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)、この前年の文化元年(一八〇四)に、抱一と親交の深い「佐原菊塢(さはらきくう)」が「向島百花園(別称「新梅屋敷」)」を開園している。その梅林での一句と解するのも一興であろう。
(参考一) 佐原菊塢(さはらきくう)の『新梅屋敷』」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
「東都三十六景 向しま花屋敷七草」(歌川広重筆)
https://www.ndl.go.jp/landmarks/sights/mukojimahyakkaen/
【文化元(1804)年、骨董商の佐原菊塢(さはらきくう)が梅やすすきなどの日本古来の草木を集め、幕臣の多賀家屋敷跡に造園した庭園。名称は江戸後期の画家酒井抱一が「梅は百花のさきがけ」の意から名付けたとされる。当初は360本の梅が主体で、亀戸梅屋敷に対して、新梅屋敷とも呼ばれた。現在は都営庭園となり、国の史跡・名勝に指定されている。】(国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」)
(参考二) 佐原鞠塢の「向島百花園」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306183697-1
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
佐原鞠塢肖像、「園のいしぶみ」より
↑
http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/siryou/kyoudobunka/tenzi/h16/kikakuten_hyakkaen.html
↓
【百花園の開園者、佐原鞠塢(きくう)
百花園を開いた佐原鞠塢は、奥州仙台の農民の出で、俗称を平八といった。明和元年(1764年)生まれという説があるが不詳。天明年間(1781年から1789年)に江戸に出てきて、中村座の芝居茶屋・和泉屋勘十郎のもとで奉公した。その後、財を蓄え、それを元手に寛政8年(1796年)頃、日本橋住吉町に骨董屋の店を開き、名を北野屋平兵衛(北平とも)と改めた。芝居茶屋での奉公、骨董商時代の幅広いつき合いがもとで、当代の文人たちとの人脈を形成し、その過程で自らも書画・和歌・漢詩などを修得した。鞠塢は、商才のある人であったらしく、文人たちを集めて古道具市をしばしば開催したが、値をあげるためのオークション的な商法が幕府の咎めを受けたという。
しばらくの間、本所中の郷(現向島1丁目付近)にいたが、文化元年(1804年)頃に剃髪して、「鞠塢菩薩」の号を名乗った。この頃、向島にあった旗本・多賀氏の屋敷跡を購入し、ここに展示で紹介する著名な文人達より梅樹の寄付や造園に協力を仰ぎ、風雅な草庭を造ったのが百花園の起こりである。園は梅の季節だけでなく、和漢の古典の知識を生かして「春の七草」「秋の七草」や「万葉集」に見える草花を植えたため、四季を通じて草花が見られるようになり、いつしか梅屋敷・秋芳園・百花園などと呼ばれるようになった。園の経営者としても鞠塢の才能はいかんなく発揮され、園内の茶店では、隅田川焼という焼き物や「寿星梅」という梅干しなどを名物として販売。また、園内で向島の名所を描きこんだ地図を刷り人々に頒布して、来園者の誘致を図り、次第にその評判が高まっていった。天保2年(1931年)8月29日に死没。編著書に漢詩集「盛音集」、句集「墨多川集」「花袋」のほか、
「秋野七草考」「春野七草考」「梅屋花品」「墨水遊覧誌」「都鳥考」などがある。】(「墨田区企画展『開園200年記念百花園』」)
(参考三)「名所江戸百景・亀戸梅屋舗」(歌川広重筆)
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
「名所江戸百景・亀戸梅屋舗」(歌川広重筆)奈良県立美術館蔵
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/112047
【 歌川広重 (1797~1858) 江戸時代/1857/竪大判錦絵/37.2×24.3㎝
(解説) 前景に当時有名であった「臥竜梅」を大きく描く構図は、新鮮で印象的な詩情を求めた『名所江戸百景』の新しい試みをよく示している。赤・紫・緑を背景に純白の梅が馥郁と薫っている。装飾的で象徴的な日本の伝統的表現法が生かされ、早春の気配が巧みに描き出されている。印象的で装飾的な表現を多用したこのシリーズは、『東海道五十三次』などに見られる繊細な写実を脱し、歌川広重の新しい詩境を示すものであった。判形もたて形を用い、緊張感と動性をよくあらわすものである。 】(「文化遺産オンライン」)
(参考四)「第六 潮のおと」の「潮(しお)のおと」の由来
【 浅草寺周辺に居た頃の句集名は「潮(しお)の音(おと)。浅草寺の祀る観音菩薩像にちなみ、「法華経観世音菩薩普門品偈(ぼんげ)」の「妙音観世音、梵音海潮(かいちょう)音」を出典とする。ごく短期間の移住だったようで、『軽挙館句藻』現存第四冊目の「千束のゐね」の後半に書き付けられている。居住場所は、「等覚院殿御一代」に「浅草観音の境内弁天池のほとり」とあることから、浅草寺境内東南の弁天社付近であったことが分かる。」】
(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/6-1.html
「江戸名所之内 浅草金竜山弁天山之図」(絵師:歌川広重/出版者:丸甚/収載資料名:東都名所/国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」)
https://www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail287.html?sights=sensoji;tokyo=taito
第五 千づかのいね(5-1) [第五 千づかのいね]
5-1 春雨のほろほろ和えや御もの棚
季語=春雨=春雨(はるさめ)三春
https://kigosai.sub.jp/001/archives/1920
【子季語】 膏雨、春の雨
【関連季語】 春霖
【解説】 春に降る雨の中でも、こまやかに降りつづく雨をいう。一雨ごとに木の芽、花の芽がふくらみ生き物達が活発に動き出す。「三冊子」では旧暦の正月から二月の初めに降るのを春の雨。それ以降は春雨と区別している。
【来歴】 『増山の井』(寛文7年、1667年)に所出。
【文学での言及】
わがせこが衣春雨ふるごとに野辺のみどりぞ色まさりける 紀貫之『古今集』
【例句】
春雨や蓬をのばす草の道 芭蕉「草の道」
春雨の木下にかかる雫かな 芭蕉「小文庫」
春雨やふた葉にもゆる茄子種 芭蕉「岨の古畑」
笠寺やもらぬいはやも春の雨 芭蕉「千鳥掛」
春雨や蜂の巣つたふ屋ねの漏 芭蕉「炭俵」
春雨や蓑吹きかへす川柳 芭蕉「はだか麦」
春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」
物種の袋ぬらしつ春のあめ 蕪村「蕪村句集」
春雨の中を流るゝ大河かな 蕪村「蕪村遺稿」
春雨や人住ミて煙壁を洩る 蕪村「蕪村句集」
春雨や身にふる頭巾着たりけり 蕪村「蕪村句集」
春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」
滝口に燈を呼ぶ聲や春の雨 蕪村「蕪村句集」
春雨やもの書ぬ身のあハれなる 蕪村「蕪村句集」
はるさめや暮なんとしてけふも有 蕪村「蕪村句集」
春雨やものがたりゆく簑と傘 蕪村「蕪村句集」
柴漬の沈みもやらで春の雨 蕪村「蕪村句集」
春雨やいさよふ月の海半(なかば) 蕪村「蕪村句集」
はるさめや綱が袂に小ぢようちん 蕪村「蕪村句集」
春雨の中におぼろの清水哉 蕪村「蕪村句集」
※「春雨のほろほろ和え」周辺
「春雨」=① 春の季節に静かに降る雨。《季・春》
② 緑豆(りょくとう)の澱粉からとった、透明、線状の食品。まめそうめん。
[2] 端唄(はうた)・うた沢の曲名。二上がり。肥前小城(佐賀県小城市)藩士柴田花守作詞。長崎丸山の遊女の作曲という。嘉永年間(一八四八‐五四)江戸で流行。上方系端唄の代表曲。別名「鶯宿梅」。(「精選版 日本国語大辞典」)
「ほろほろ」=① 葉や花などが散ったり落ちたりするさまを表わす語。
※枕(10C終)一九九「きなる葉どものほろほろとこぼれおつる」
② 涙や水滴などがこぼれ落ちるさまを表わす語。また、激しく泣くさまを表わす語。
※蜻蛉(974頃)上「又ほろほろとうち泣きていでぬ」
③ 集まっていた人々が分かれ散るさまを表わす語。
※源氏(1001‐14頃)若菜下「さるべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを」
④ 物が裂け破れるさま、こなごなになるさまを表わす語。ぼろぼろ。
※源氏(1001‐14頃)宿木「栗やなどやうの物にや、ほろほろと食ふも」
⑤ 雉子(きじ)、山鳥などの鳴く声を表わす語。ほろろ。
※源賢集(1020頃)「御狩野に朝たつきじのほろほろと鳴きつつぞふる身を恨みつつ」
⑥ 砧(きぬた)を打つ音を表わす語。
※歌謡・閑吟集(1518)「衣々の、砧の音が、枕にほろほろほろほろとか、それをしたふは、涙よなふ」(「精選版 日本国語大辞典」)
「ほろほろ和え」=「切和(きりあえ)」=料理法の一つ。食べ物を細かく切ってあえること。また、その料理。特に、蕗(ふき)の若葉、または藤の若芽などをゆでて細かく刻み、焼みそであえたもの。ほろほろ。〔俚言集覧(1797頃)〕(「精選版 日本国語大辞典」)
※「御もの棚」=「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚。
※枕(10C終)五六「御厨子(みづし)所のおものだなに沓(くつ)おきて」(「精選版 日本国語大辞典」)
「句意」(その周辺)
下記のアドレスで、抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)周辺について、次のとおり紹介した。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-10-18
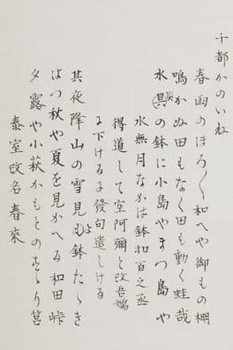
抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)
https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/ogai/document/15dd5a92-e055-4dcb-a302-1ed3adc3716f#?c=0&m=0&s=0&cv=18&xywh=-825%2C0%2C6602%2C3937
【「千都かのいね」(「千づかのいね」「千束の稲」)は、『軽挙観(館)句藻』(静嘉堂文庫所蔵・二十一巻十冊)収録の「千づかのいね」(自筆句集の題名)を、刊本の自撰句集『屠龍之技』の第五編に収載したものなのであろう。
この第五編「千づかのいね」(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』)の六句目「夕露や小萩かもとのすずり筥」が、冒頭の、抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」の賛(発句=俳句)ということになろう。(略)
そして、四句目の「其夜降(る)山の雪見よ鉢たゝき」の前書き「水無月なかば鉢叩百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」は、六句目の「夕露や小萩がもとのすゞり筥」にも掛かるものと解したい。(略)】
「第五 千づかのいね」の「千(ち)づか」は、寛政十年(一七九八)、抱一、三十八歳頃に移住した、隅田川西岸の、「浅草寺」北方一帯の「千束(せんぞく)村」(現在の台東区・荒川区にまたがるエリア)の「「千束(せんぞく)」を「「千(ち)づか」と、抱一は、抱一流の詠みで、それを『屠龍之技』の第五編に、その「自薦(選)句」を収載して、この句が、そのトップの巻頭(「編・章」のトップ)の一句ということになる。
この句も、当時の抱一の、趣向に趣向を凝らして、自信作の一つなのであろう。この句の「春雨」は、「春雨」(季語=三春)・「春雨」(食用)・「春雨」(端唄・小唄)を掛けての措辞のようである。
この「ほろほろ」も、「(季語の春雨の)ほろほろ」・「(食用の春雨の)ほろほろ(ほろほろ和え)」を掛けての措辞ということになる。
そして、この「ほろほろ和え」の「和え」(混ぜ合わせたもの)は、当時の「吉原文化」の、その底流を流れているものと通ずるのものなのであろう。
https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-11.html
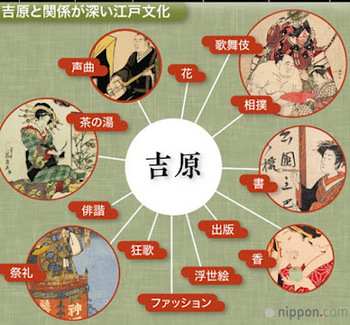
すなわち、この「御もの棚」も、「「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚」の、「宮中(禁中)=隔離された別世界」ならず「吉原(郭中)=隔離された別世界」の「御もの棚」(御大尽の食膳を載せておく棚)と解すると、この句の全体像が、その正体を現してくるような雰囲気なのである。
さらに、それらに加えて、上記の「吉原文化」の「声曲」に関連しても、下記のアドレスで紹介したとおり、抱一は、当時の「荻江節」「河東節」の、名だたる名手で知られていたのである。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03
【 (追記二)抱一作「朝顔」(荻江節)
https://www.kyosendo.co.jp/essay/125_tamaya_1/
見しをりのつゆわすられぬ、
あさがほのはなの盛は、
ももとせもかはらぬ今のかたみとて、
むかしかたりにあらばこそ、
見れば、
うつつに水くきのあとは尽せぬ玉菊の、
ひとよふた代ををなしなの、
あいよりいでてなをあをきるりのせかいや、
花のおもか」
「玉菊が描き置し香包ありて、朝顔の花を描きて最しほらかりしを、不図雨花庵(抱一)
の大人に見せければ、元来好事といひ常々廓中に入ひたりて画に用ひられて取はやさるる
身は人々のすすめも黙止(もだし)がたく、彼香包の色絵より朝顔といふめりやすの唄を
作り、名ある画客会合し衆評の上節を付、伊能永鯉もたびたび引出されて、一節伐(ひと
よぎり)を合せ、その外鼓弓筝笛尺八つづみ太鼓にいたるまで、名だたる人々一同に合奏
して、夜な夜な遊君ひともとの座敷に錬磨しけるが、その後はなばなしく追善の式ありし
沙汰を聞ず、伝え聞に、それぞれの配(くばり)もの四季着(しきせ)付届振舞以下弐百
両余の失墜あればなり、依て玉菊が墓所を修理して苔提所に於て読経作善いと念頃なりし
とかや」
(追記三)「抱一と河東節」
≪抱一は声曲の中では当時の通人の多くがそうであったように河東節(かとうでし)を好
み、しばしば仲間と会を催した。河東の新曲を幾つか作り、「青すだれ」「江戸うぐいす」
「夜の編笠」「火とり虫」等、抱一作として後代にのこっている曲も幾つかある。≫(『本
朝画人伝巻一・村松梢風』所収「酒井抱一」)
↑
https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-09-07
↓
(追記) 酒井抱一作詞『江戸鶯』(一冊 文政七年=一八二四 「東京都立中央図書館
加賀文庫」蔵)
≪ 抱一は河東節を好み、その名手でもあったという。自ら新作もし、この「江戸鶯」
「青簾春の曙」の作詞のほか、「七草」「秋のぬるで」などの数曲が知られている。平生愛
用の河東節三味線で「箱」に「盂東野」と題し、自身の下絵、羊遊斎の蒔絵がある一棹な
ども有名であった。≫(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図
版解説一〇一」(松尾知子稿)」) 】
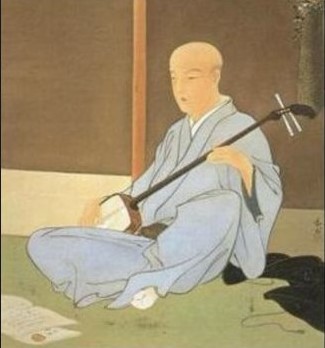
「抱一上人」鏑木清方筆(三幅対の中幅/縦四〇・五㎝ 横三五・〇㎝/明治四十二年<一九〇九>永青文庫蔵 )
句意は、「この吉原も、今や「ほろほろと降る春雨」の中にある。その妓楼の亭主や御大尽用の食膳用の「御もの棚」に、「春雨のほろほろ和え」などが用意されている。どこからともなく、それらの「ほろほろと降る春雨や、春雨のほろほろ和(あ)えに和(わ)した声曲」が聞こえてくる。」
季語=春雨=春雨(はるさめ)三春
https://kigosai.sub.jp/001/archives/1920
【子季語】 膏雨、春の雨
【関連季語】 春霖
【解説】 春に降る雨の中でも、こまやかに降りつづく雨をいう。一雨ごとに木の芽、花の芽がふくらみ生き物達が活発に動き出す。「三冊子」では旧暦の正月から二月の初めに降るのを春の雨。それ以降は春雨と区別している。
【来歴】 『増山の井』(寛文7年、1667年)に所出。
【文学での言及】
わがせこが衣春雨ふるごとに野辺のみどりぞ色まさりける 紀貫之『古今集』
【例句】
春雨や蓬をのばす草の道 芭蕉「草の道」
春雨の木下にかかる雫かな 芭蕉「小文庫」
春雨やふた葉にもゆる茄子種 芭蕉「岨の古畑」
笠寺やもらぬいはやも春の雨 芭蕉「千鳥掛」
春雨や蜂の巣つたふ屋ねの漏 芭蕉「炭俵」
春雨や蓑吹きかへす川柳 芭蕉「はだか麦」
春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」
物種の袋ぬらしつ春のあめ 蕪村「蕪村句集」
春雨の中を流るゝ大河かな 蕪村「蕪村遺稿」
春雨や人住ミて煙壁を洩る 蕪村「蕪村句集」
春雨や身にふる頭巾着たりけり 蕪村「蕪村句集」
春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」
滝口に燈を呼ぶ聲や春の雨 蕪村「蕪村句集」
春雨やもの書ぬ身のあハれなる 蕪村「蕪村句集」
はるさめや暮なんとしてけふも有 蕪村「蕪村句集」
春雨やものがたりゆく簑と傘 蕪村「蕪村句集」
柴漬の沈みもやらで春の雨 蕪村「蕪村句集」
春雨やいさよふ月の海半(なかば) 蕪村「蕪村句集」
はるさめや綱が袂に小ぢようちん 蕪村「蕪村句集」
春雨の中におぼろの清水哉 蕪村「蕪村句集」
※「春雨のほろほろ和え」周辺
「春雨」=① 春の季節に静かに降る雨。《季・春》
② 緑豆(りょくとう)の澱粉からとった、透明、線状の食品。まめそうめん。
[2] 端唄(はうた)・うた沢の曲名。二上がり。肥前小城(佐賀県小城市)藩士柴田花守作詞。長崎丸山の遊女の作曲という。嘉永年間(一八四八‐五四)江戸で流行。上方系端唄の代表曲。別名「鶯宿梅」。(「精選版 日本国語大辞典」)
「ほろほろ」=① 葉や花などが散ったり落ちたりするさまを表わす語。
※枕(10C終)一九九「きなる葉どものほろほろとこぼれおつる」
② 涙や水滴などがこぼれ落ちるさまを表わす語。また、激しく泣くさまを表わす語。
※蜻蛉(974頃)上「又ほろほろとうち泣きていでぬ」
③ 集まっていた人々が分かれ散るさまを表わす語。
※源氏(1001‐14頃)若菜下「さるべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを」
④ 物が裂け破れるさま、こなごなになるさまを表わす語。ぼろぼろ。
※源氏(1001‐14頃)宿木「栗やなどやうの物にや、ほろほろと食ふも」
⑤ 雉子(きじ)、山鳥などの鳴く声を表わす語。ほろろ。
※源賢集(1020頃)「御狩野に朝たつきじのほろほろと鳴きつつぞふる身を恨みつつ」
⑥ 砧(きぬた)を打つ音を表わす語。
※歌謡・閑吟集(1518)「衣々の、砧の音が、枕にほろほろほろほろとか、それをしたふは、涙よなふ」(「精選版 日本国語大辞典」)
「ほろほろ和え」=「切和(きりあえ)」=料理法の一つ。食べ物を細かく切ってあえること。また、その料理。特に、蕗(ふき)の若葉、または藤の若芽などをゆでて細かく刻み、焼みそであえたもの。ほろほろ。〔俚言集覧(1797頃)〕(「精選版 日本国語大辞典」)
※「御もの棚」=「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚。
※枕(10C終)五六「御厨子(みづし)所のおものだなに沓(くつ)おきて」(「精選版 日本国語大辞典」)
「句意」(その周辺)
下記のアドレスで、抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)周辺について、次のとおり紹介した。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-10-18
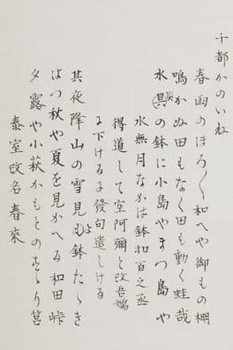
抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)
https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/ogai/document/15dd5a92-e055-4dcb-a302-1ed3adc3716f#?c=0&m=0&s=0&cv=18&xywh=-825%2C0%2C6602%2C3937
【「千都かのいね」(「千づかのいね」「千束の稲」)は、『軽挙観(館)句藻』(静嘉堂文庫所蔵・二十一巻十冊)収録の「千づかのいね」(自筆句集の題名)を、刊本の自撰句集『屠龍之技』の第五編に収載したものなのであろう。
この第五編「千づかのいね」(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』)の六句目「夕露や小萩かもとのすずり筥」が、冒頭の、抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」の賛(発句=俳句)ということになろう。(略)
そして、四句目の「其夜降(る)山の雪見よ鉢たゝき」の前書き「水無月なかば鉢叩百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」は、六句目の「夕露や小萩がもとのすゞり筥」にも掛かるものと解したい。(略)】
「第五 千づかのいね」の「千(ち)づか」は、寛政十年(一七九八)、抱一、三十八歳頃に移住した、隅田川西岸の、「浅草寺」北方一帯の「千束(せんぞく)村」(現在の台東区・荒川区にまたがるエリア)の「「千束(せんぞく)」を「「千(ち)づか」と、抱一は、抱一流の詠みで、それを『屠龍之技』の第五編に、その「自薦(選)句」を収載して、この句が、そのトップの巻頭(「編・章」のトップ)の一句ということになる。
この句も、当時の抱一の、趣向に趣向を凝らして、自信作の一つなのであろう。この句の「春雨」は、「春雨」(季語=三春)・「春雨」(食用)・「春雨」(端唄・小唄)を掛けての措辞のようである。
この「ほろほろ」も、「(季語の春雨の)ほろほろ」・「(食用の春雨の)ほろほろ(ほろほろ和え)」を掛けての措辞ということになる。
そして、この「ほろほろ和え」の「和え」(混ぜ合わせたもの)は、当時の「吉原文化」の、その底流を流れているものと通ずるのものなのであろう。
https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-11.html
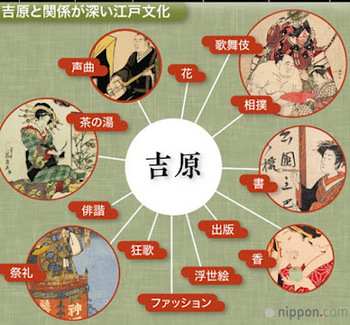
すなわち、この「御もの棚」も、「「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚」の、「宮中(禁中)=隔離された別世界」ならず「吉原(郭中)=隔離された別世界」の「御もの棚」(御大尽の食膳を載せておく棚)と解すると、この句の全体像が、その正体を現してくるような雰囲気なのである。
さらに、それらに加えて、上記の「吉原文化」の「声曲」に関連しても、下記のアドレスで紹介したとおり、抱一は、当時の「荻江節」「河東節」の、名だたる名手で知られていたのである。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03
【 (追記二)抱一作「朝顔」(荻江節)
https://www.kyosendo.co.jp/essay/125_tamaya_1/
見しをりのつゆわすられぬ、
あさがほのはなの盛は、
ももとせもかはらぬ今のかたみとて、
むかしかたりにあらばこそ、
見れば、
うつつに水くきのあとは尽せぬ玉菊の、
ひとよふた代ををなしなの、
あいよりいでてなをあをきるりのせかいや、
花のおもか」
「玉菊が描き置し香包ありて、朝顔の花を描きて最しほらかりしを、不図雨花庵(抱一)
の大人に見せければ、元来好事といひ常々廓中に入ひたりて画に用ひられて取はやさるる
身は人々のすすめも黙止(もだし)がたく、彼香包の色絵より朝顔といふめりやすの唄を
作り、名ある画客会合し衆評の上節を付、伊能永鯉もたびたび引出されて、一節伐(ひと
よぎり)を合せ、その外鼓弓筝笛尺八つづみ太鼓にいたるまで、名だたる人々一同に合奏
して、夜な夜な遊君ひともとの座敷に錬磨しけるが、その後はなばなしく追善の式ありし
沙汰を聞ず、伝え聞に、それぞれの配(くばり)もの四季着(しきせ)付届振舞以下弐百
両余の失墜あればなり、依て玉菊が墓所を修理して苔提所に於て読経作善いと念頃なりし
とかや」
(追記三)「抱一と河東節」
≪抱一は声曲の中では当時の通人の多くがそうであったように河東節(かとうでし)を好
み、しばしば仲間と会を催した。河東の新曲を幾つか作り、「青すだれ」「江戸うぐいす」
「夜の編笠」「火とり虫」等、抱一作として後代にのこっている曲も幾つかある。≫(『本
朝画人伝巻一・村松梢風』所収「酒井抱一」)
↑
https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-09-07
↓
(追記) 酒井抱一作詞『江戸鶯』(一冊 文政七年=一八二四 「東京都立中央図書館
加賀文庫」蔵)
≪ 抱一は河東節を好み、その名手でもあったという。自ら新作もし、この「江戸鶯」
「青簾春の曙」の作詞のほか、「七草」「秋のぬるで」などの数曲が知られている。平生愛
用の河東節三味線で「箱」に「盂東野」と題し、自身の下絵、羊遊斎の蒔絵がある一棹な
ども有名であった。≫(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図
版解説一〇一」(松尾知子稿)」) 】
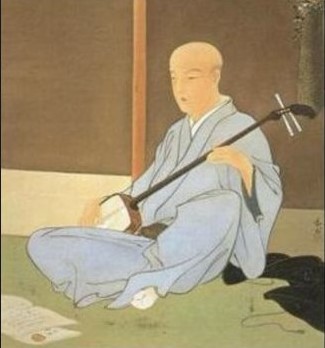
「抱一上人」鏑木清方筆(三幅対の中幅/縦四〇・五㎝ 横三五・〇㎝/明治四十二年<一九〇九>永青文庫蔵 )
句意は、「この吉原も、今や「ほろほろと降る春雨」の中にある。その妓楼の亭主や御大尽用の食膳用の「御もの棚」に、「春雨のほろほろ和え」などが用意されている。どこからともなく、それらの「ほろほろと降る春雨や、春雨のほろほろ和(あ)えに和(わ)した声曲」が聞こえてくる。」
第四 椎の木かげ(4-11) [第四 椎の木かげ]
4-11 夕立や静(か)に歩行筏さし
季語=夕立=夕立(ゆうだち、ゆふだち)三夏
https://kigosai.sub.jp/kigo500a/250.html
【子季語】 ゆだち、よだち、白雨、驟雨、夕立雲、夕立晴、村雨、スコール
【関連季語】 夏の雨、虹
【解説】 夏の午後のにわか雨、ときに雷をともない激しく降るが短時間で止み、涼しい風が吹きわたる。
【来歴 】 『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。
【文学での言及】 よられつるのもせの草のかげろひて涼しく曇る夕立の空 西行法師 『千載集』巻三夏
【実証的見解】 夏の強い日差しで生じる上昇気流によって積乱雲が急激に成長し、局部的に激しい雨をもたらす現象。
【例句】
夕立にやけ石寒浅間山 素堂 「素堂句集」
夕立のあと柚の薫る日陰かな 北枝 「猿丸宮集」
夕立や草葉を掴むむら雀 蕪村 「蕪村句集」
夕立が始まる海のはずれかな 一茶 「七番日記」
「句意」(その周辺)
この句は、抱一の趣向に趣向を凝らした一句である。この句にも、前書の「十鳥千句独吟」が掛かっているようなのだが、肝心の「十鳥」の「鳥」が「ヌケ(ヌキ・抜け・抜句)」(俳諧で、ある語を句の表面に出さないで、余意においてそれをとききかせる句作りの手法。また、その句)の、いわゆる「抜句」の雰囲気なのである。
さらに、前書の「十鳥千句独吟」の「十鳥」は、この句の前の十句(「4-1」~「4-10」)
で、「鶯・雉・燕・杜鵑・翡翠・雁・鵲・木菟・鴛鴦・蒼鷹」で、これらを発句として、「十百韻」
千句)が巻かれていると解しても差し支えなかろう。
とすると、「ヌケ」の手法が「余意を利かせる」手法とすると、これは、「正式(しょうしき・せいしき)俳諧」(「十百韻」)成就後の、その余勢の余章的な「余興(興を添える)俳諧」との範疇に入る、そのような一句(発句)のような雰囲気を有している。
そして、ずばり、この句は、次の其角の句の、「反転化・捩り・見立て・抜け」などの一句と解したい。
※「日の春をさすがに鶴の歩みかな(其角)」=(「丙寅初懐紙」)季語=日の春(新年)の「鶴」を「夕立」(夏)の「鶴」の句に反転化(「反転・捩り・見立て・抜け」)しているか?
其角の造語による「日の春」(新年)→ 抱一の「夕立」(三夏)→反転
其角の「さすがに」 → 抱一の「静かに」(捩り)
其角の「鶴」 → 抱一の「筏さし(筏士)」(見立て)
其角の「歩み」→ 抱一の「歩行」の造語的詠み(あゆむ)→捩り
句意は、「猛烈な夕立が襲ってきた。その中を、少しも慌てず、静かに、筏士が、筏の上を歩みながら、筏を漕いでいる。それは、まるで、私淑する其角師匠の『日の春をさすがに鶴の歩みかな』のような風情である。」
(参考その一) 抱一の「鶴」図周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-11-21

酒井抱一画「群鶴図屏風」二曲一双 紙本金地著色 (ウースター美術館蔵)

瀬戸民吉製「色絵双鶴図小皿」十枚一組 (国立歴史民族博物館蔵)
https://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/rekihaku/110/witness.html
【この小皿は「文政九戌十一月瀬戸民吉製」とあり、文政九年(一八二六)の瀬戸焼(愛知県瀬戸焼き)の一つということになる。この文政九年は、抱一、六十六歳の時で、その六月には、『光琳百図後編』が刊行された年である。
『鶯邨画譜』が刊行されたのは、文化十四年(一八一七)、五十七歳の時で、その後、十年足らずして、陶器に意匠化されて、抱一ブランドが製品化されているのは特記して置く必要があろう。】

抱一画集『鶯邨画譜』所収「双鶴図」(「早稲田大学図書館」蔵)
http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html
(参考その二)蕪村の「筏師・筏士」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-06-12

蕪村筆「筏師画賛=B」(出光美術館蔵)
【[【筏師画賛】一幅 与謝蕪村筆 紙本墨画淡彩 江戸時代 二七・二×六六・八㎝
嵐山の桜を愛でている最中に、急に風雨が激しくなって、筏師の蓑が風に吹かれた一瞬を花に見立てた俳画。蓑の部分は、紙を揉んで皺をつけ、その上から渇筆を擦りつけることで、蓑のごわごわとした質感をあらわしている。蓑笠だけで表された筏師のポーズは遊び心にあふれ、ほのぼのとしていながら印象的である。遊歴の俳人画家、蕪村は五十歳になってから京都に安住の地に選び、身も心も京都の人になりきって庶民の風習を楽しんだ。自己を語ることをせずに、筏師一人だけを慎み深く捉えているところに、かえって都会的な香りや郷愁を感じさせる。(出光)
(釈文)
嵐山の花にまかりけるに俄に風雨しけれは
いかたしの みのや あらしの 花衣 蕪村 (花押) ]
「大雅・蕪村・玉堂と仙崖―『笑《わらい》』のこころ」(作品解説38)
上記の「作品解説」の中で、「蓑の部分は、紙を揉んで皺をつけ、その上から渇筆を擦りつけることで、蓑のごわごわとした質感をあらわしている」の、いわゆる、水墨画の「乾筆(かっぴつ)=墨の使用を抑え,半乾きの筆を紙に擦りつけるように描く」の技法を、この「ミの(蓑)」に駆使しているのが、この俳画のポイントのようである。
その「蓑」に比して、「笠」の方は、「潤筆(じゅんぴつ)=十分に墨を含ませて描く」の技法の一筆描きで、この「蓑と笠」だけで「筏師のポーズ」を表現するというのは、「遊歴の俳人画家」たる蕪村の「遊び心」で、「ほのぼのとしていながら印象的である」と鑑賞している(上記の解説)。
ここで、この「筏師画賛=B」は、何時頃制作されたのかということについては、この賛に書かれている発句「いかたしの/ミのや/あらしの/花衣」の成立時期との関連で、凡その見当はついてくるであろう。 】
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-06-08

蕪村筆「筏士自画賛」(百池の箱書きあり・蕪村の署名はなく花押のみ)=A
【寺村百池の「箱書き」(括弧書き=読みと注)は次のとおりである。
[ これは是、老師夜半翁(蕪村)世に在(ま)す頃、四明山下金福寺に諸子会しける日、帰路三本樹(京都市上京区の地名=三本木、その南北に走る東三本木通りは、江戸時代花街として栄えた)なる井筒楼に膝ゆるめて、各三盃を傾く。時に越(こし=北陸道の古名)の桃睡(とうすい)、酔に乗じて衣を脱ぎ師に筆を乞ふ。とみに肯(うべな)ひ、麁墨(そぼく)禿筆(とくひつ)を採(とり)てかいつけ給ふものなり。余(百池)も其(その)傍に有りて燭をとり立廻(たちめぐ)りたりしが、日月梭(ひ)の如く三十年を経て、さらに軸をつけ壁上の観となし、其(その)よしをしるせよと責(せめ)けるこそ、そゞろ懐古の情に堪へず、たゞ老師の磊落(らいらく)なる事を述(のべ)て今のぬしにあたへ侍りぬ。 ]
(『蕪村全集一 発句)』所収「2377 左注・頭注・脚注」)
さらに、『大来堂発句集』(百池の発句集)』の天明三年(一七八三)三月二十三日に、「金福寺芭蕉庵、追善之俳諧興行(風蘿念仏)に、蕪村、桃睡、百池一座」として、「雨日嵐山
に春を惜しむ」との前書きのある「み尽して雨もつ春の山のかひ」という句が所出されている。
すなわち、蕪村が亡くなる天明三年(一七八三)の三月二十三日、上記の百池の「箱書き」に記載されている句会が、金福寺芭蕉庵で開かれて、その帰途に、三本樹の井筒楼で宴会があり、その宴席での、即興的な「席画」(宴席や会合の席上で、求めに応じて即興的に絵を描かくこと。また、その絵)が、上記の「筏士自画賛=A」なのである。
これは、百池の「箱書き」によって、桃睡の「衣」に描いた、すなわち、「絹本墨画」の「筏士自画賛」ということになる。ところが、「紙本墨画淡彩」の「筏師画賛=B」(出光美術館蔵)も現存するのである。これは、後述することとして、その前に、上記の「筏士自画賛=A」の賛の発句や落款について触れて置きたい。
この画中の右の冒頭に、「嵐山の花見に/まかりけるに/俄(にわか)に風雨しければ」として、「いかだしの/みのや/あらしの/花衣」の句が中央に書かれている。それに続いて、画面の左に、「酔蕪村/三本樹/井筒屋に/おいて写」と落款し、その最後に、蕪村常用の「花押」が捺されている。
このことから、蕪村は、亡くなる最晩年にも、この独特の花押を常用していたことが明瞭となって来る。
ここで、蕪村が最晩年の立場に立って、生涯の発句の中から後世に残すに足るものとして自撰した『自筆句帳』の内容を伝える『蕪村句集(几董編)』の「巻之上・春之部」では、「雨日嵐山にあそぶ」として「筏士(いかだし)の蓑(みの)やあらしの花衣(はなごろも)」の句形で採られている。
この句形からすると、出光美術館所蔵の「筏師画賛=B」(「大雅・蕪村・玉堂と仙崖―『笑《わらい》のこころ』」図録中「作品38」)も「筏士画賛」のネーミングも当然に想定されたものであろう。おそらく、「筏士自画賛=A」と区別したいという意図があるのかも知れない。】
(参考その三)其角の「日の春を」(貞享三丙寅年正月『初懐紙』)周辺
https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E8%95%89%E9%96%80%E4%BF%B3%E8%AB%A7%E9%9B%86-%E4%B8%8A/%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%98%A5%E3%82%92-%E3%81%AE%E5%B7%BB/
「日の春を」の巻(貞享三丙寅年正月『初懐紙』)
初表
日の春をさすがに鶴の歩ミ哉 其角
砌に高き去年の桐の実 文鱗
雪村が柳見にゆく棹さして 枳風
酒の幌に入あひの月 コ斎
秋の山手束の弓の鳥売ん 芳重
炭竃こねて冬のこしらへ 杉風
里々の麦ほのかなるむら緑 仙花
我のる駒に雨おほひせよ 李下
初裏
朝まだき三嶋を拝む道なれば 挙白
念仏にくるふ僧いづくより 朱絃
あさましく連歌の興をさます覧 蚊足
敵よせ来るむら松の声 ちり
有明の梨打烏帽子着たりける 芭蕉
うき世の露を宴の見おさめ 筆
にくまれし宿の木槿の散たびに 文鱗
後住む女きぬたうちうち 其角
山ふかみ乳をのむ猿の声悲し コ斎
命を甲斐の筏ともみよ 枳風
法の土我剃リ髪を埋ミ置ん 杉風
はづかしの記をとづる草の戸 芳重
さく日より車かぞゆる花の陰 李下
橋は小雨をもゆるかげろふ 仙花
ニ表
残る雪のこる案山子のめづらしく 朱絃
しづかに酔て蝶をとる歌 挙白
殿守がねぶたがりつるあさぼらけ ちり
はげたる眉をかくすきぬぎぬ 芭蕉
罌子咲て情に見ゆる宿なれや 枳風
はわけの風よ矢箆切に入 コ斎
かかれとて下手のかけたる狐わな 其角
あられ月夜のくもる傘 文鱗
石の戸樋鞍馬の坊に音すみて 挙白
われ三代の刀うつ鍛冶 李下
永禄は金乏しく松の風 仙花
近江の田植美濃に耻らん 朱絃
とく起て聞勝にせん時鳥 芳重
船に茶の湯の浦あはれ也 其角
二裏
つくしまで人の娘をめしつれて 李下
弥勒の堂におもひうちふし 枳風
待かひの鐘は墜たる草の上 はせを
友よぶ蟾の物うきの声 仙花
雨さへぞいやしかりける鄙ぐもり コ斎
門は魚ほす磯ぎはの寺 挙白
理不尽に物くふ武者等六七騎 芳重
あら野の牧の御召撰ミに 其角
鵙の一声夕日を月にあらためて 文鱗
糺の飴屋秋さむきなり 李下
電の木の間を花のこころせば 挙白
つれなきひじり野に笈をとく 枳風
人あまた年とる物をかつぎ行 揚水
さかもりいさむ金山がはら 朱絃
三表
此国の武仙を名ある絵にかかせ 其角
京に汲する醒井の水 コ斎
玉川やをのをの六ツの所みて 芭蕉
江湖江湖に年よりにけり 仙花
卯花の皆精にもよめるかな 芳重
竹うごかせば雀かたよる 揚水
南むく葛屋の畑の霜消て 不卜
親と碁をうつ昼のつれづれ 文鱗
餅作る奈良の広葉を打合セ 枳風
贅に買るる秋の心は はせを
鹿の音を物いはぬ人も聞つらめ 朱絃
にくき男の鼾すむ月 不卜
苫の雨袂七里をぬらす覧 李下
生駒河内の冬の川づら 揚水
三裏
水車米つく音はあらしにて 其角
梅はさかりの院々を閉 千春
二月の蓬莱人もすさめずや コ斎
姉待牛のおそき日の影 芳重
胸あはぬ越の縮をおりかねて 芭蕉
おもひあらはに菅の刈さし 枳風
菱のはをしがらみふせてたかべ嶋 文鱗
木魚きこゆる山陰にしも 李下
囚をやがて休むる朝月夜 コ斎
萩さし出す長がつれあひ 不卜
問し時露と禿に名を付て 千春
心なからん世は蝉のから 朱絃
三度ふむよし野の桜芳野山 仙化
あるじは春か草の崩れ屋 李下
名表
傾城を忘れぬきのふけふことし 文鱗
経よみ習ふ声のうつくし 芳重
竹深き笋折に駕籠かりて 挙白
梅まだ苦キ匂ひなりけり コ斎
村雨に石の灯ふき消ぬ 峡水
鮑とる夜の沖も静に 仙化
伊勢を乗ル月に朝日の有がたき 不卜
欅よりきて橋造る秋 李下
信長の治れる代や聞ゆらん 揚水
居士とよばるるから国の児 文鱗
紅に牡丹十里の香を分て 千春
雲すむ谷に出る湯をきく 峡水
岩ねふみ重き地蔵を荷ひ捨 其角
笑へや三井の若法師ども コ斎
名裏
逢ぬ恋よしなきやつに返歌して 仙化
管弦をさます宵は泣るる 芳重
足引の廬山に泊るさびしさよ 揚水
千声となふる観音の御名 其角
舟いくつ涼みながらの川伝い 枳風
をなごにまじる松の白鷺 峡水
寝筵の七府に契る花匂へ 不卜
連衆くははる春ぞ久しき 挙白
季語=夕立=夕立(ゆうだち、ゆふだち)三夏
https://kigosai.sub.jp/kigo500a/250.html
【子季語】 ゆだち、よだち、白雨、驟雨、夕立雲、夕立晴、村雨、スコール
【関連季語】 夏の雨、虹
【解説】 夏の午後のにわか雨、ときに雷をともない激しく降るが短時間で止み、涼しい風が吹きわたる。
【来歴 】 『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。
【文学での言及】 よられつるのもせの草のかげろひて涼しく曇る夕立の空 西行法師 『千載集』巻三夏
【実証的見解】 夏の強い日差しで生じる上昇気流によって積乱雲が急激に成長し、局部的に激しい雨をもたらす現象。
【例句】
夕立にやけ石寒浅間山 素堂 「素堂句集」
夕立のあと柚の薫る日陰かな 北枝 「猿丸宮集」
夕立や草葉を掴むむら雀 蕪村 「蕪村句集」
夕立が始まる海のはずれかな 一茶 「七番日記」
「句意」(その周辺)
この句は、抱一の趣向に趣向を凝らした一句である。この句にも、前書の「十鳥千句独吟」が掛かっているようなのだが、肝心の「十鳥」の「鳥」が「ヌケ(ヌキ・抜け・抜句)」(俳諧で、ある語を句の表面に出さないで、余意においてそれをとききかせる句作りの手法。また、その句)の、いわゆる「抜句」の雰囲気なのである。
さらに、前書の「十鳥千句独吟」の「十鳥」は、この句の前の十句(「4-1」~「4-10」)
で、「鶯・雉・燕・杜鵑・翡翠・雁・鵲・木菟・鴛鴦・蒼鷹」で、これらを発句として、「十百韻」
千句)が巻かれていると解しても差し支えなかろう。
とすると、「ヌケ」の手法が「余意を利かせる」手法とすると、これは、「正式(しょうしき・せいしき)俳諧」(「十百韻」)成就後の、その余勢の余章的な「余興(興を添える)俳諧」との範疇に入る、そのような一句(発句)のような雰囲気を有している。
そして、ずばり、この句は、次の其角の句の、「反転化・捩り・見立て・抜け」などの一句と解したい。
※「日の春をさすがに鶴の歩みかな(其角)」=(「丙寅初懐紙」)季語=日の春(新年)の「鶴」を「夕立」(夏)の「鶴」の句に反転化(「反転・捩り・見立て・抜け」)しているか?
其角の造語による「日の春」(新年)→ 抱一の「夕立」(三夏)→反転
其角の「さすがに」 → 抱一の「静かに」(捩り)
其角の「鶴」 → 抱一の「筏さし(筏士)」(見立て)
其角の「歩み」→ 抱一の「歩行」の造語的詠み(あゆむ)→捩り
句意は、「猛烈な夕立が襲ってきた。その中を、少しも慌てず、静かに、筏士が、筏の上を歩みながら、筏を漕いでいる。それは、まるで、私淑する其角師匠の『日の春をさすがに鶴の歩みかな』のような風情である。」
(参考その一) 抱一の「鶴」図周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-11-21

酒井抱一画「群鶴図屏風」二曲一双 紙本金地著色 (ウースター美術館蔵)

瀬戸民吉製「色絵双鶴図小皿」十枚一組 (国立歴史民族博物館蔵)
https://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/rekihaku/110/witness.html
【この小皿は「文政九戌十一月瀬戸民吉製」とあり、文政九年(一八二六)の瀬戸焼(愛知県瀬戸焼き)の一つということになる。この文政九年は、抱一、六十六歳の時で、その六月には、『光琳百図後編』が刊行された年である。
『鶯邨画譜』が刊行されたのは、文化十四年(一八一七)、五十七歳の時で、その後、十年足らずして、陶器に意匠化されて、抱一ブランドが製品化されているのは特記して置く必要があろう。】

抱一画集『鶯邨画譜』所収「双鶴図」(「早稲田大学図書館」蔵)
http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html
(参考その二)蕪村の「筏師・筏士」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-06-12

蕪村筆「筏師画賛=B」(出光美術館蔵)
【[【筏師画賛】一幅 与謝蕪村筆 紙本墨画淡彩 江戸時代 二七・二×六六・八㎝
嵐山の桜を愛でている最中に、急に風雨が激しくなって、筏師の蓑が風に吹かれた一瞬を花に見立てた俳画。蓑の部分は、紙を揉んで皺をつけ、その上から渇筆を擦りつけることで、蓑のごわごわとした質感をあらわしている。蓑笠だけで表された筏師のポーズは遊び心にあふれ、ほのぼのとしていながら印象的である。遊歴の俳人画家、蕪村は五十歳になってから京都に安住の地に選び、身も心も京都の人になりきって庶民の風習を楽しんだ。自己を語ることをせずに、筏師一人だけを慎み深く捉えているところに、かえって都会的な香りや郷愁を感じさせる。(出光)
(釈文)
嵐山の花にまかりけるに俄に風雨しけれは
いかたしの みのや あらしの 花衣 蕪村 (花押) ]
「大雅・蕪村・玉堂と仙崖―『笑《わらい》』のこころ」(作品解説38)
上記の「作品解説」の中で、「蓑の部分は、紙を揉んで皺をつけ、その上から渇筆を擦りつけることで、蓑のごわごわとした質感をあらわしている」の、いわゆる、水墨画の「乾筆(かっぴつ)=墨の使用を抑え,半乾きの筆を紙に擦りつけるように描く」の技法を、この「ミの(蓑)」に駆使しているのが、この俳画のポイントのようである。
その「蓑」に比して、「笠」の方は、「潤筆(じゅんぴつ)=十分に墨を含ませて描く」の技法の一筆描きで、この「蓑と笠」だけで「筏師のポーズ」を表現するというのは、「遊歴の俳人画家」たる蕪村の「遊び心」で、「ほのぼのとしていながら印象的である」と鑑賞している(上記の解説)。
ここで、この「筏師画賛=B」は、何時頃制作されたのかということについては、この賛に書かれている発句「いかたしの/ミのや/あらしの/花衣」の成立時期との関連で、凡その見当はついてくるであろう。 】
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-06-08

蕪村筆「筏士自画賛」(百池の箱書きあり・蕪村の署名はなく花押のみ)=A
【寺村百池の「箱書き」(括弧書き=読みと注)は次のとおりである。
[ これは是、老師夜半翁(蕪村)世に在(ま)す頃、四明山下金福寺に諸子会しける日、帰路三本樹(京都市上京区の地名=三本木、その南北に走る東三本木通りは、江戸時代花街として栄えた)なる井筒楼に膝ゆるめて、各三盃を傾く。時に越(こし=北陸道の古名)の桃睡(とうすい)、酔に乗じて衣を脱ぎ師に筆を乞ふ。とみに肯(うべな)ひ、麁墨(そぼく)禿筆(とくひつ)を採(とり)てかいつけ給ふものなり。余(百池)も其(その)傍に有りて燭をとり立廻(たちめぐ)りたりしが、日月梭(ひ)の如く三十年を経て、さらに軸をつけ壁上の観となし、其(その)よしをしるせよと責(せめ)けるこそ、そゞろ懐古の情に堪へず、たゞ老師の磊落(らいらく)なる事を述(のべ)て今のぬしにあたへ侍りぬ。 ]
(『蕪村全集一 発句)』所収「2377 左注・頭注・脚注」)
さらに、『大来堂発句集』(百池の発句集)』の天明三年(一七八三)三月二十三日に、「金福寺芭蕉庵、追善之俳諧興行(風蘿念仏)に、蕪村、桃睡、百池一座」として、「雨日嵐山
に春を惜しむ」との前書きのある「み尽して雨もつ春の山のかひ」という句が所出されている。
すなわち、蕪村が亡くなる天明三年(一七八三)の三月二十三日、上記の百池の「箱書き」に記載されている句会が、金福寺芭蕉庵で開かれて、その帰途に、三本樹の井筒楼で宴会があり、その宴席での、即興的な「席画」(宴席や会合の席上で、求めに応じて即興的に絵を描かくこと。また、その絵)が、上記の「筏士自画賛=A」なのである。
これは、百池の「箱書き」によって、桃睡の「衣」に描いた、すなわち、「絹本墨画」の「筏士自画賛」ということになる。ところが、「紙本墨画淡彩」の「筏師画賛=B」(出光美術館蔵)も現存するのである。これは、後述することとして、その前に、上記の「筏士自画賛=A」の賛の発句や落款について触れて置きたい。
この画中の右の冒頭に、「嵐山の花見に/まかりけるに/俄(にわか)に風雨しければ」として、「いかだしの/みのや/あらしの/花衣」の句が中央に書かれている。それに続いて、画面の左に、「酔蕪村/三本樹/井筒屋に/おいて写」と落款し、その最後に、蕪村常用の「花押」が捺されている。
このことから、蕪村は、亡くなる最晩年にも、この独特の花押を常用していたことが明瞭となって来る。
ここで、蕪村が最晩年の立場に立って、生涯の発句の中から後世に残すに足るものとして自撰した『自筆句帳』の内容を伝える『蕪村句集(几董編)』の「巻之上・春之部」では、「雨日嵐山にあそぶ」として「筏士(いかだし)の蓑(みの)やあらしの花衣(はなごろも)」の句形で採られている。
この句形からすると、出光美術館所蔵の「筏師画賛=B」(「大雅・蕪村・玉堂と仙崖―『笑《わらい》のこころ』」図録中「作品38」)も「筏士画賛」のネーミングも当然に想定されたものであろう。おそらく、「筏士自画賛=A」と区別したいという意図があるのかも知れない。】
(参考その三)其角の「日の春を」(貞享三丙寅年正月『初懐紙』)周辺
https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E8%95%89%E9%96%80%E4%BF%B3%E8%AB%A7%E9%9B%86-%E4%B8%8A/%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%98%A5%E3%82%92-%E3%81%AE%E5%B7%BB/
「日の春を」の巻(貞享三丙寅年正月『初懐紙』)
初表
日の春をさすがに鶴の歩ミ哉 其角
砌に高き去年の桐の実 文鱗
雪村が柳見にゆく棹さして 枳風
酒の幌に入あひの月 コ斎
秋の山手束の弓の鳥売ん 芳重
炭竃こねて冬のこしらへ 杉風
里々の麦ほのかなるむら緑 仙花
我のる駒に雨おほひせよ 李下
初裏
朝まだき三嶋を拝む道なれば 挙白
念仏にくるふ僧いづくより 朱絃
あさましく連歌の興をさます覧 蚊足
敵よせ来るむら松の声 ちり
有明の梨打烏帽子着たりける 芭蕉
うき世の露を宴の見おさめ 筆
にくまれし宿の木槿の散たびに 文鱗
後住む女きぬたうちうち 其角
山ふかみ乳をのむ猿の声悲し コ斎
命を甲斐の筏ともみよ 枳風
法の土我剃リ髪を埋ミ置ん 杉風
はづかしの記をとづる草の戸 芳重
さく日より車かぞゆる花の陰 李下
橋は小雨をもゆるかげろふ 仙花
ニ表
残る雪のこる案山子のめづらしく 朱絃
しづかに酔て蝶をとる歌 挙白
殿守がねぶたがりつるあさぼらけ ちり
はげたる眉をかくすきぬぎぬ 芭蕉
罌子咲て情に見ゆる宿なれや 枳風
はわけの風よ矢箆切に入 コ斎
かかれとて下手のかけたる狐わな 其角
あられ月夜のくもる傘 文鱗
石の戸樋鞍馬の坊に音すみて 挙白
われ三代の刀うつ鍛冶 李下
永禄は金乏しく松の風 仙花
近江の田植美濃に耻らん 朱絃
とく起て聞勝にせん時鳥 芳重
船に茶の湯の浦あはれ也 其角
二裏
つくしまで人の娘をめしつれて 李下
弥勒の堂におもひうちふし 枳風
待かひの鐘は墜たる草の上 はせを
友よぶ蟾の物うきの声 仙花
雨さへぞいやしかりける鄙ぐもり コ斎
門は魚ほす磯ぎはの寺 挙白
理不尽に物くふ武者等六七騎 芳重
あら野の牧の御召撰ミに 其角
鵙の一声夕日を月にあらためて 文鱗
糺の飴屋秋さむきなり 李下
電の木の間を花のこころせば 挙白
つれなきひじり野に笈をとく 枳風
人あまた年とる物をかつぎ行 揚水
さかもりいさむ金山がはら 朱絃
三表
此国の武仙を名ある絵にかかせ 其角
京に汲する醒井の水 コ斎
玉川やをのをの六ツの所みて 芭蕉
江湖江湖に年よりにけり 仙花
卯花の皆精にもよめるかな 芳重
竹うごかせば雀かたよる 揚水
南むく葛屋の畑の霜消て 不卜
親と碁をうつ昼のつれづれ 文鱗
餅作る奈良の広葉を打合セ 枳風
贅に買るる秋の心は はせを
鹿の音を物いはぬ人も聞つらめ 朱絃
にくき男の鼾すむ月 不卜
苫の雨袂七里をぬらす覧 李下
生駒河内の冬の川づら 揚水
三裏
水車米つく音はあらしにて 其角
梅はさかりの院々を閉 千春
二月の蓬莱人もすさめずや コ斎
姉待牛のおそき日の影 芳重
胸あはぬ越の縮をおりかねて 芭蕉
おもひあらはに菅の刈さし 枳風
菱のはをしがらみふせてたかべ嶋 文鱗
木魚きこゆる山陰にしも 李下
囚をやがて休むる朝月夜 コ斎
萩さし出す長がつれあひ 不卜
問し時露と禿に名を付て 千春
心なからん世は蝉のから 朱絃
三度ふむよし野の桜芳野山 仙化
あるじは春か草の崩れ屋 李下
名表
傾城を忘れぬきのふけふことし 文鱗
経よみ習ふ声のうつくし 芳重
竹深き笋折に駕籠かりて 挙白
梅まだ苦キ匂ひなりけり コ斎
村雨に石の灯ふき消ぬ 峡水
鮑とる夜の沖も静に 仙化
伊勢を乗ル月に朝日の有がたき 不卜
欅よりきて橋造る秋 李下
信長の治れる代や聞ゆらん 揚水
居士とよばるるから国の児 文鱗
紅に牡丹十里の香を分て 千春
雲すむ谷に出る湯をきく 峡水
岩ねふみ重き地蔵を荷ひ捨 其角
笑へや三井の若法師ども コ斎
名裏
逢ぬ恋よしなきやつに返歌して 仙化
管弦をさます宵は泣るる 芳重
足引の廬山に泊るさびしさよ 揚水
千声となふる観音の御名 其角
舟いくつ涼みながらの川伝い 枳風
をなごにまじる松の白鷺 峡水
寝筵の七府に契る花匂へ 不卜
連衆くははる春ぞ久しき 挙白
第四 椎の木かげ(4-10) [第四 椎の木かげ]
4-10 蒼鷹(そうよう)の拳はなれて江戸の色
季語=蒼鷹(そうよう)=鷹(たか)三冬
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2878
【子季語】 のすり、八角鷹、熊鷹、鶚、青鷹、蒼鷹、もろがへり、大鷹
【解説】 ワシ、タカ科の中形の鳥類の総称で、色彩は主に暗褐色。嘴は強く鋭く曲がり、脚には強い大きな鉤爪があり小動物を襲って食べる。鷹狩に使われているのは主に大鷹である。蒼鷹(もろがえり)は、生後三年を経たたかのこと。
【例句】
鷹一つ見付けてうれし伊良古崎 芭蕉「笈の小文」
夢よりも現の鷹ぞ頼もしき 芭蕉「鵲尾冠」
鷹の目の枯野にすわるあらしかな 丈草「菊の香」
あら浪に山やはなれて鷹の影 麦水「葛箒」
落し来る鷹にこぼるる松葉かな 白雄「白雄句集」
鷹来るや蝦夷を去る事一百里 一茶「寛政句帖」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-10.html
葛飾北斎「桜に鷹」 天保5年(1834)頃 前北斎為一筆 長大判錦絵 52.0×23.6㎝ 森屋治兵衛
https://intojapanwaraku.com/art/2317/
句意は、「鷹匠(たかじょう)の拳を放れた青鷹(あおたか)は、今まさに、江戸爛漫の宙(そら)に輝いている。」
※「青鷹・蒼鷹(あおたか・あをたか・そうよう)」=「おおたか(大鷹)」の古名。古来、鷹狩り用として、最も珍重された種類。もろがえり。
※万葉(8C後)一七・四〇一一「鷹はしも 数多(あまた)あれども 矢形尾(やかたを)の 吾が大黒に〈大黒は蒼鷹の名なり〉 白塗の 鈴取り附けて」()
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-10.html
酒井抱一筆「植物の上の鷹(カラー木版画)」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-10.html
「同上(部分拡大図)
https://www.meisterdrucke.jp/fine-art-prints/Sakai-Hoitsu/1033857/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%B7%B9%EF%BC%88%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%9C%A8%E7%89%88%E7%94%BB.html
季語=蒼鷹(そうよう)=鷹(たか)三冬
https://kigosai.sub.jp/001/archives/2878
【子季語】 のすり、八角鷹、熊鷹、鶚、青鷹、蒼鷹、もろがへり、大鷹
【解説】 ワシ、タカ科の中形の鳥類の総称で、色彩は主に暗褐色。嘴は強く鋭く曲がり、脚には強い大きな鉤爪があり小動物を襲って食べる。鷹狩に使われているのは主に大鷹である。蒼鷹(もろがえり)は、生後三年を経たたかのこと。
【例句】
鷹一つ見付けてうれし伊良古崎 芭蕉「笈の小文」
夢よりも現の鷹ぞ頼もしき 芭蕉「鵲尾冠」
鷹の目の枯野にすわるあらしかな 丈草「菊の香」
あら浪に山やはなれて鷹の影 麦水「葛箒」
落し来る鷹にこぼるる松葉かな 白雄「白雄句集」
鷹来るや蝦夷を去る事一百里 一茶「寛政句帖」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-10.html
葛飾北斎「桜に鷹」 天保5年(1834)頃 前北斎為一筆 長大判錦絵 52.0×23.6㎝ 森屋治兵衛
https://intojapanwaraku.com/art/2317/
句意は、「鷹匠(たかじょう)の拳を放れた青鷹(あおたか)は、今まさに、江戸爛漫の宙(そら)に輝いている。」
※「青鷹・蒼鷹(あおたか・あをたか・そうよう)」=「おおたか(大鷹)」の古名。古来、鷹狩り用として、最も珍重された種類。もろがえり。
※万葉(8C後)一七・四〇一一「鷹はしも 数多(あまた)あれども 矢形尾(やかたを)の 吾が大黒に〈大黒は蒼鷹の名なり〉 白塗の 鈴取り附けて」()
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-10.html
酒井抱一筆「植物の上の鷹(カラー木版画)」
(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-10.html
「同上(部分拡大図)
https://www.meisterdrucke.jp/fine-art-prints/Sakai-Hoitsu/1033857/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%B7%B9%EF%BC%88%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%9C%A8%E7%89%88%E7%94%BB.html



